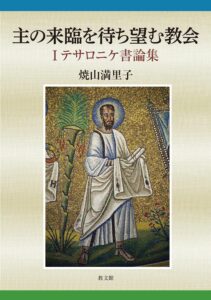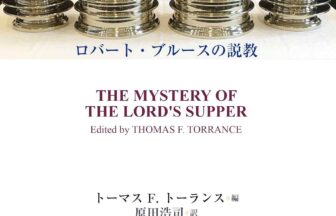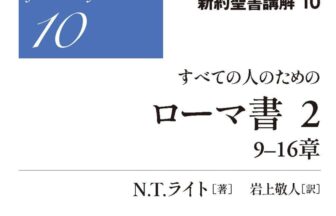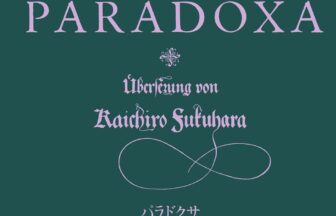黙示思想とパウロ
〈評者〉大貫隆
本書は著者が二〇一八年以降最近までの間に発表してきたⅠテサロニケ書(以下Ⅰと略記)に関する七つの論考を集成したものである。まず著者は「黙示はすべてのキリスト教神学の母」という有名な命題(E・ケーゼマン)を意識して、Ⅰでも救いが「われらの外側で」起きた出来事であることを論証する。第1章ではⅠ一5の「福音がなった」の文言、第2章では現実の苦難の下での忍耐の勧告に含まれる「十字架の神学」、第3章では、「われらの外側で」宇宙大の広がりで生じているキリストの出来事への参与」(ゴシックは大貫)、内面的回心よりもパウロにとって重要であることが論じられる。
第4─7章は、現在有力な学説に逆らって、来臨についてのⅠとⅡの見方が「終末の遅延」の状況と無関係であることを繰り返し論じる。「無秩序ではなく静かに働く勧め」がⅠとⅡの両方に出てくることも、切迫待望の沈静化を意図したものではなく、「一般的な〔中略〕教えである」(七九頁)。Ⅱ二2の「私たちからのような手紙」が何を指すかという周知の難問については、著者は他の研究者と同様、Ⅰと同定する。ただし、Ⅰでのパウロの真意は希望をもって今を生きることの勧めであったが、どうしたわけか「主の日はすでに来た」という意味に誤解されてしまった。Ⅱの著者はⅠの後継者として、その誤解を正そうとしている(九七頁)。第6章は私(大貫)の言うイエスの「神の国」のイメージ・ネットワークをさらに広げつつ、ⅠとⅡの天使論をⅠエノク書の終末審判の場面から読解することを試みる。第7章は旧約預言者たちの言う「ヤハウェの日」と「主の日」が元来共同の礼拝への参加を促す呼びかけであって、終末論とは関係がないという学説を紹介する。そしてパウロも同じ見方を踏襲しているとする。
パウロにとって一貫して「終末の遅延」の問題が存在しなかったとする点で、著者はJ・C・ベカーの研究(一九八〇年)に沿って、パウロがユダヤ教黙示思想をストレートに受容せず、重要な変更を加えているからだと考える。とりわけ、今の時代と来るべき時代という二元論、およびその境目で悪が増大するという観念を放棄し(二六頁)、信徒は「今すでに、来臨に際して完全にされる救いに参与している」(ゴシックは大貫)と考えているからだと言う(五八頁)。「時は縮まっている」(Ⅰ七29)というパウロの文言も、単に終末の切迫のことではなく、古い時間と新しい時間が重複した現在のことである(一二〇頁)。要するに、パウロにとって終末の遅延の問題はそもそも前提にならないのである(序論九頁)。
全体にわたって、外国語文献に偏らず日本人による研究が幅広く真摯に参照され、焦眉の論争点について著者自身の見解が明瞭に示される。それは読者を説得すると同時に、新たな問いも喚起する。まさにそれゆえに本書は、日本の読者にとっても、稀に見るアクチュアルな論文集となっている。著者の粘り強い思考が印象に残る。