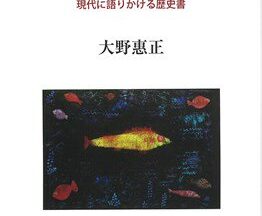キリスト教思想史を読み継ぎ・語り継ぐ意義を「人間学」の視点から解明
〈評者〉阿部善彦
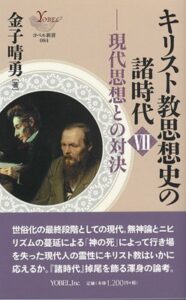
キリスト教思想史の諸時代 Ⅶ
現代思想との対決
金子晴勇著
新書判・280頁・定価1320円・ヨベル
(本巻全7巻完結・平均272頁・各巻定価1320円・別巻2冊は編集中)
教文館AmazonBIBLE HOUSE書店一覧
同書をもって『キリスト教思想史の諸時代』(全七巻)が完結した。全七巻を貫く「キリスト教思想史」というテーマについて、第一巻「序論」では「思想史は人間学の宝庫である」と述べられる。それに従えば全七巻の一連の思想史解明は「人間とは何か」を根本的に問い直すものである。著者を全七巻の完結にまで導いた「人間」をめぐる問題意識の深い部分はこの第七巻でさらに研ぎ澄まされる。それは著者が生きてきた時代、歩んできた研究生活の実存的体験に裏づけられ、深められてきた人間をめぐる今日的状況の徹底的な把握によるものであって第七巻の「はじめに」のほか随所で明らかにされる。なかでも第七巻の第一章「世俗化とは何か」は本シリーズ全体を見通す上で重要である。
「世俗化」は信仰生活の回復・刷新を求めた宗教改革とともに生じる事態である。矛盾するように見えるこの事態がどのように進むのかというと、マルティン・ルターの職業召命説に顕著であるように信仰生活から世俗生活を分離・切断するのではなく、むしろ、聖化して結合することが宗教改革を通じてかつてない仕方で推奨・推進され、そこにキリスト教や宗教を肯定する「世俗化」が生じる。しかし、その世俗化の過程に近代的自己・近代的個人主義の性格が増し加わると、信仰生活を内面的・個人的なものとして追求する動きが一転して、内面的・個人的なものを信仰から解放する自由・自律を追求する真逆の動きが加速し、キリスト教を否定的に捉えて社会や文化から排除する、脱宗教化・非宗教化的な「世俗化」が生じる。ここに「世俗化の両義性」が見られる。
また近代諸国に見られる領邦教会制度や国教会制度によって、信仰は君主が領民・国民に強制的に課すものとなり、支配体制に組み込まれた教会は、個人の内的信仰の受け皿としての役割や社会正義を求める批判的性格を急速に失っていった。この点は本書のもう一つのテーマであるアウシュヴィッツの審問という現代の根本問題にも通じるもので、その問題性は、本書第八章「ヒトラーのファッシズムとの対決─ボンヘッファーとヴェイユ」および「談話室:ヒトラーの批判者と迎合者」で論じられる。こうした近代世界の世俗化の過程において、宗教の社会的・文化的意義が希薄・空洞化する一方で、それを埋め合わせるように、自らの意志的・理性的・合理的能力によって自律的に自己を形成・陶冶する教養文化が開花し、読書、趣味、学問が盛んになり、キリスト教や信仰への依存・従属から目覚めた啓蒙主義がもてはやされる脱宗教的・非宗教的世俗文化が定着する(ロマン主義、ドイツ観念論もそれに含まれる)。
しかし信仰なしで理性などの人間的能力のみによって自律した個人という近代的人間は、果たして真に人間的なものでありうるのか。キリスト教思想史を古代・中世に遡れば、アウグスティヌスの『告白』にあるように人間は神に呼びかけ「あなたに向けて造られ」「あなたにおいて安らうまで」安らぎを得ることがない存在であり、そこには、自分ひとりでは自分自身を存在させることも、満足させることもできない根源的な渇きについての強烈な自覚があった(本シリーズ第二巻第三章参照)。しかし今や近代人は自己の人間的能力だけを根拠とするあまり神も他者も排除する「排他的な自律」に至り、自己を神の代わりに絶対化し、もはや躊躇うことなく理性的・意志的能力を最大限に活用して他者を蹂躙する。この傲慢で「排他的な自律」の出現に著者は古代・中世キリスト教思想世界との断絶を見るとともに、「近代人の運命を破滅」へと導いた「元凶」を見る(第七巻「はじめに」参照)。
終焉を迎えた古代・中世キリスト教思想世界とともに近代世界から退場したものは人間の無能・無力の自覚であろう。被造物として人間は自己自身で存在を造り出せないという根源的な無能・無力を抱える。また、神の似姿に造られたものとして、神との関係なしに自己自身だけで自己の存在意味・幸福を実現できないという根源的な無能・無力を抱える。被造性さらには神の似姿であることによって印づけられた人間のこのいかんともしがたい根源的無能・無力の深淵に立たされ、うめき、なげき、へりくだるとき、人間は自らの霊性的次元の最深部に触れるのであり、そこにアウグスティヌスの神への告白・賛美が生まれ、溢れ出る恩寵に満たされた人間本性の完成・救済の道行がひらかれる。しかし神が死んだ近代人はもはや自らの無能・無力を自覚し訴える宛先を持たず、恩寵と霊性的次元を拒絶し、神も他者もなく独りでその無能・無力を抱え、自己のみを絶対化して、神がいなければ全てが自由であるという虚無的自由・エゴイズムに身を委ね自己をさらに虚無化し、その虚無にアウシュヴィッツという近代的根源悪が炸裂する(第七巻第九章「ヨーロッパのニヒリズム」および「談話室:ドストエフスキーの『悪霊』を読む」参照)。
確かに、近代的な合理主義、科学技術、政治経済はこれまでになく人間の活動可能性を拡張した。しかし何のために人間は存在し、何のために生きるのか。近代人は人間的能力として最高のものとされる理性や意志によって自己自身でそれに答え、実現できるとするが、果たしてそうであろうか。アウシュヴィッツが示したように、自らの理性と意志が築き上げた合理的システム、科学技術、政治経済は、かえって人間をたんなる労働生産力あるいはたんなる遺伝情報(ただし擬似科学的な優生学による)にまで還元・破壊・解体してその歯車の中に組み入れ、誇るべき人間の理性は冷徹な計算的合理性(AIによって用済みになるかもしれない)に、意志の力はただ自己の信念・願望のみを盲目的に連呼しながら他者に強制し、相容れない主張には耳を閉ざして断固拒絶する頑なさに、あるいはただの偶然的恣意や自発的隷従にまで切り下げられていることを第七巻は人間学的観点から明らかにする。
そうした近現代の人間による人間的尊厳の貶めを通じて人間自身が自分から切り捨ててきたものとは、古代・中世世界そして宗教改革および敬虔主義の思想に息づいてきた人間の霊性的次元、そして、神と他者に呼びかけ真理を求めて対話する交わりであり、それは本シリーズ第一巻から第六巻を貫く中心テーマに他ならない。第七巻では近現代の問題状況の中で苦闘した哲学者・神学者の思想を通じて、霊性的次元と対話と交わりの人間学的意義が論じられる。著者はこれら全体を読み継ぎ・語り継がれるべき古典・名著の豊富な引用とともにわたしたちに贈り届けた。そのために著者と志を同じくする出版・編集者の存在が不可欠であったのはいうまでもない。困難な出版状況の中でこのような著作集が生み出されたことに感謝をささげつつ、わたしたちがキリスト教思想史を読み継ぎ・語り継ぐ今日的な意義を多くの読者とともにうけとめたい。