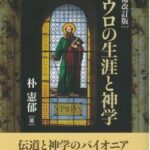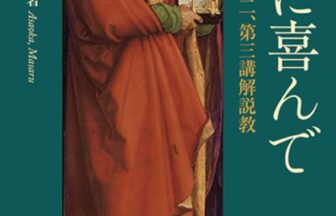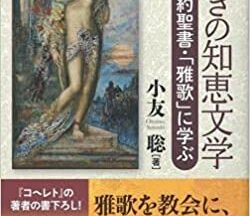神の〈まこと〉から来るキリスト信仰
〈評者〉廣石 望
2011年に公刊が始まった『小川修 パウロ書簡講義録』(全十巻)も、本書の後は『ガラテヤ書講義Ⅱ』を残すのみとなった。編者は、小川修氏(1940~2011年)の教え子たちである。講義の録音音声を忠実に文字化するという独特の編集スタイルには、亡き師への深い敬慕の念が溢れている(「あとがき」参照)。
小川氏が中心に据える「神の<まこと>から人間の<まこと>へ」という解釈原理は、ふつう「信仰」と訳されるギリシア語ピスティスを「まこと」と訳すことで、人の「信仰」に先立つ神の<まこと>を確保する。これは滝沢克己のインマヌエル論の継承であり、パウロのピスティス概念に「神の信実」を含める立場は古くはカール・バルト、現代新約学では太田修司氏その他の賛同者がいる。
パウロが召命体験を述べる件は、「母の胎内にある時からわたしを聖別し、み恵みをもってわたしをお呼び(お召し)になっていた方が、異邦人の間に宣べ伝えさせるために、わたしの中において・わたしの中なる御子を啓示することをよしとしたもうた」(ガラ一・15~16)と訳される。先行する神の「聖別」と「召し」が第一のピスティスないし「イエス・キリストの<まこと>」である一方で、「わたしの中に御子がいる」という認識の成立、つまりダマスコ体験が第二のピスティスである(35頁以下)。人の信心は、神の救いの現実への応答なのである。このつながりは「第一」と「第二の義認」とも言われ、前者(選びと召し)は万人に妥当する原事実である(101頁他)。
したがって「生きているのは、もはやわたしではない。キリストが、わたしのうちに生きておられる」(ガラ2・20)という発言も、信仰者とは、「キリストの<まこと>」から「我が内なるキリスト」への転換を経た「わたしでないわたし」であるという消息を伝える(109頁以下)。
同じことはアブラハムにも当てはまる。「(聖書に)アブラハムは『神を信じた。それ(=アブラハムの信仰・彼の内なるキリストcf.V16)が彼には義と認められた(=第二の義認)』とある〔中略〕。他方聖書は、神が諸国民を<まこと>により義とされていること(第一のピスティス〔中
略〕)を、あらかじめ知っていて、(この原福音を)アブラハムに対し、『万(よろず)の国民(くにたみ)、汝によりて〔中略〕祝福せられん』〔中略〕と予告(=約束)したのである」(ガラ3・6と8)と言われるとき、アブラハムに向けられる「汝によりて」は、彼の内なる「キリストにあって」の意である(208頁以下他)。キリストの<まこと>は、神と人を─時を超えて─相互に媒介する。
それゆえ、重いしょうがいを抱えてキリスト者として生きた座古愛子さん(1878~1945年)の姿もまた「その十字架の、十字架のすぐ裏っ側にこの復活がある」ことを教えてくれる(206頁)。私たちにとっても「十字架が復活」なのである(107頁以下他)。
宗教哲学者としての小川氏の面目躍如たる解釈である。評者に残る問いのひとつは、死せるイエスの起こし(復活)という神の行為の歴史的な個別性と、新しい世界の出現という終末論的な位相を、神の<まこと>という構想の中にどう位置づけるかである。

廣石望
ひろいし・のぞむ=立教大学教授
Warning: Undefined variable $post_types in /home/hiram2/honhiro.com/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/author.php on line 1447
Warning: Undefined variable $post_types in /home/hiram2/honhiro.com/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/author.php on line 1486