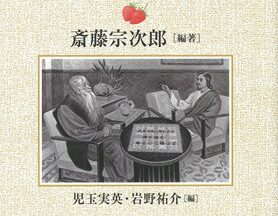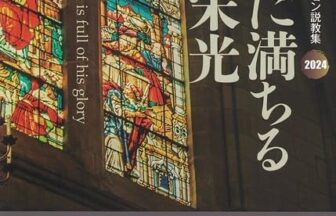ルター神学の核心を真正面から見事に論じた研究
〈評者〉江口再起
核心をついたルター研究である。ルターを本当に学びたいならば、繙きたい一冊。
従来、ルターと言えば、教科書風な「九五ヵ条」の信仰の英雄ということになりがちである。しかし、ルターの、ルターたるゆえんは、もちろんそういうことではない。
須藤氏は、ルターの核心を彼の「神学的突破」とそれに続く「十字架の神学」と見定める。つまり前期ルターである(もちろん、それは後期にも一貫していく)。
ルターの「神学的突破」とは何か(今まで塔の体験とか宗教改革的転回とか、やや曖昧に言われてきた)。須藤氏は次のように定義する。《功績による救済論から恩恵と信仰による救済論への転換》(九〇頁)。もう少し詳しく言えば《ルターの救済論は、アウグスティヌスの「恩恵的救済」を「信仰義認」の面から徹底させて、義の所在をどこまでもキリストの側に保持させたものであり、それゆえ、それは神を求め続ける卑賎な人間が信仰を通して受けたキリストの義とその成長とによる救済論なのだと言える》(一一五頁)。つまり、《恩恵的救済の発見と信仰義認の確立》(同頁)である。ここからルターの神学、更に改革運動が展開していく。
ルターの「十字架の神学」とは何か。彼は一五一八年修道院総会で自らの十字架の神学を説明した。それが『ハイデルベルク討論』である。須藤氏はこの討論を分析し、「十字架の神学」とは、十字架の下に隠された神(キリスト!)という神認識と、その十字架のキリストに自己の生き方を重ねる倫理であるという(そして「十字架の神学」はルター義認論の一部を形成)。
「神学的突破」と「十字架の神学」。まさにルター神学の核心である。同感。(なお私のコメントを一つ。「信仰義認」という言い方は誤解を招きやすい。神の恵みと、それへの人の応答である信仰は、滝沢克己の用語を使えば「不可分・不可同・不可逆」であるので「恩寵義認」という言い方を私はしている)。
さて、本書の意義について更に二点。第一に、パウロ→アウグスティヌス→ルターをつなぐ、なにはなくともまず「神の恵み」というキリスト教神学の王道を、鮮明に打ち出していること。すべては、ここから始まる。
第二点。ルターはこうした核心的論点を、ヴィッテンベルク大学での初期聖書講義(詩編、ロマ書、へブル書など)や、アウグスティヌス(『シンプリキアヌスへ』、『霊と文字』)研究、またドイツ神秘主義への学びを通して熟成させていったのだが、須藤氏はそうした形成の歩みを原典に一つ一つ丁寧に当りつつ検討していく。実に手堅い神学研究である。
最後に言及したいことは、須藤氏が、かかるルター神学が現代社会に対しても重要な意味を持っていることに触れている点である。効率主義と自己過信に満ちた現代社会の中で、我々はルターから何を学ぶべきか。須藤氏は「受動性」と「主体性」を挙げる。まず神の恵みを受容(受動)する。それが「神学的突破」の中味だ。そして、その恵みを主体的に、つまり十字架のキリストに自らを重ねつつ生きる。これが「十字架の神学」なのだ。まことに的をえた指摘だと思う。