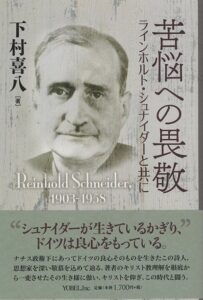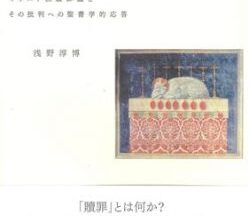精神的な抵抗の声を発し続けた生涯に触れながら
〈評者〉片柳榮一
著者の秘められた「信」の熱情ともいえるものが伝わっってくる書である。この書は下村氏が、長年研究してきたドイツのカトリック系詩人、思想家ラインホルト・シュナイダー(1903−1958)に関して、主に雑誌『共助』に書き記してきたものをまとめたものである。ファシズムに抵抗し、ドイツの悲劇を身に負い、次第に「裸の十字架」へと追い詰められていったシュナイダーの苦悩に寄り添い、自らの苦悩の場所に立とうとする下村氏の決意が、この本のいたるところに滲み出ている。シュナイダーは生来病弱で、鬱病に苦しみ、また胃腸の障がいに苛まれ続けた。しかし彼は国家社会の病といえるものにも鋭敏に反応している。彼はナチスが権力を掌握する2年前に友人に宛てて書いている。「今やヒトラーとその第三帝国のせいで、この上なくひどい幻滅がドイツの前に差し迫っている」(20頁)。シュナイダーの抵抗活動は、ボンヘッファーと同じように国内にとどまってのものであった。
代表作『カール五世の前に立つラス・カサス』は、16世紀南米のスペイン植民地で、原住民の解放と人権擁護のために戦ったカサスを主人公にして、ナチスのユダヤ人迫害と侵略戦争に対して抗議した書であり、1940年の評論集『権力と恩寵』を最後に出版権を奪われ、多くの人々の協力で「非合法出版によって精神的な抵抗の声を発し続け」(25頁)たという。「ドイツ軍の従軍神父たちの手を経て当時としては実に夥しい数の出版物が前線の兵士たちの間に広がった」(26頁)。その数は100万を越えるものだったという。「東部の収容所の捕虜たちは、地面に横たわりながらこれらの文章を紙袋に書き写していた。他の者たちは、破り取られた数ページを鉄条網しにこっそり手に入れることに成功した時、自分は幸せ者だと思った」(26頁)という。シュナイダーは兵士が置かれた苦悩の状況をよく知っている。「兵士は(戦場において)行動しても、あるいはしなくても罪を犯すことになることを知りつつ個人的に決断しなければならない。自分を相手に殺させれば、その相手を殺人者にしてしまう。自分が相手を殺せば、自分が殺人者になる」(54頁)。この苦悩は兵士だけのものではないとシュナイダーは言う。「今生じている事態を是認する人間は、たとえ彼が(個人としては)あらゆる悪を厳しく批判する人間であっても、この事態に対する同罪を免れることはできない。他方また、それらを是認しない人間は、どのように生きればよいのであろうか。事態を拒否した場合も、罪を新たに呼び起こすことにならないであろうか……私は裸の十字架の前に追いやられるのを知った。そしてその場所に立ち尽くしている」(55頁)。下村氏によれば「彼(シュナイダー)の生きた時代は人間を十字架の悲劇へ導く時代であった。……この時代は一人一人の人間の生がキリストの犠牲死に近づくこと、キリストの生と同じ形を取ることを求めているのであると彼は言う。彼は祈る『キリストの生が犠牲であったのと同じようにわれわれの生を犠牲であらしめてください』(『主の祈り』)」(100頁)。今世界はウクライナ侵攻に加え、パレスティナをめぐる絶望的な戦いを目の当たりにしている。世界の混乱と苦悩が一層深まりつつあるように思えるこのような時代に、シュナイダーの言葉は、私たちに重い問いかけとなって迫ってくる。