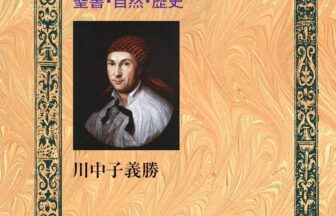神学的貢献の可能性とその限界を鮮明にし、今後にも期待する一書
〈評者〉大貫 隆
本書は二〇一七年春に南山大学大学院人間文化研究科に提出された学位申請論文に基づき、その後新たに序論、最終第五章、結論を書き下ろして増補したものである。後二世紀のリヨンの司教エイレナイオスが『使徒的宣教の証明』と『異端反駁』で構築した救済史の神学を聖霊論の観点から詳細に記述しようという意欲的な試みである。
第一章「エイレナイオスにおける〈神の両手〉の置き換えの思想 ─ 〈御言葉と知恵〉から〈御子と聖霊〉へ」では、先達の教父から〈神の両手〉としての〈御言葉(logos)と知恵(sohpia)〉の観念を受け取ったエイレナイオスがそれを〈御子と聖霊〉へ置き換えたのだとされる。その意図は〈肉の救い(を)軽視〉し、〈御父以外の別の神の存在を主張〉するグノーシス主義を反駁して、人間が〈神との類似性〉へ完成されるべきこと、そして〈御父の優位性〉を示すことであったとされる。
第二章「エイレナイオスにおける善き神と人間の成長」は、第一節でエイレナイオスの神観を取り上げる。それは人間の自立性を尊重する神であり、〈神の両手〉である御子と聖霊はその見守り役である。第二節は、エイレナイオスの救済史の構想の中核を論述する。すなわち、神は人間を原初から〈神の子ら〉として創造したが、人間は堕罪によって〈不滅性〉を喪失してしまった。しかし神は時の満ちるに及んで御子を受肉させ(遣り直し)、再び〈神との類似性〉の回復へと道を開く。御国において〈肉体〉、〈魂〉、〈聖霊〉からなる〈完全な人間〉への〈神化〉が最終的に実現する。第三節は、エイレナイオスの洗礼論に当たるもので、〈不滅性〉と〈不死性〉の回復のために〈洗礼〉の重要性が指摘される。
第三章「エイレナイオスにおける聖霊の人間への臨在」では、エイレナイオスの救済史を〈人間の創造〉、〈旧約時代〉、〈御子の受肉の時代〉、〈教会の時代〉の四つに分け、この順で聖霊の臨在と働きが分析される。
第四章は「聖霊の内在による信者の刷新」と題されて、〈教会の時代〉に洗礼をとおして聖霊が人間に内在すること、その主要な働きは〈助言〉であること、エイレナイオスはそのために繰り返し好んでイザヤ一一2−3を適用することが明らかにされる。それはエイレナイオスが聖霊は教会に、すなわち洗礼を受けた信者のみに内在すると考えている証拠だと言う。
第五章「人間を完成へと至らせる聖霊の働き」は、伝統的な言い方に直せば、エイレナイオスの人間論(三つの構成部分:肉、魂、聖霊)とキリスト教倫理(罪、聖霊による刷新、善とは何か、使徒への従順、使徒継承、創造の完成としての神化)を扱っている。続く最後の結論は、本書全体の論旨を章ごとに再度要約している。
私が見るところ、エイレナイオスの救済史の神学はそれ自体が物語性に富んでいる。そのため、それを論述する『異端反駁』第三−五巻は、グノーシス主義諸派の神話への反駁を繰り広げる第一−二巻とは独立に読むことができる。事実、これまでのエイレナイオス研究の多くが『異端反駁』第三−五巻の物語の分析と記述の形で行われてきた。大庭氏の本書もその線に沿うもので、欧米の研究のみならず、園部不二夫、大貫隆、ハンス・ユルゲン・マルクス(元南山大学長、現藤女子大学長)、鳥巣義文、ペトロ・ネメシェギ、塩谷惇子他による日本語での主な先行研究も丁寧かつ綿密に参照している。『異端反駁』第三−五巻の本文も、既刊の邦訳を吟味した上で、常に私訳で掲出している。
すでにこれらの先行研究の焦点の一つとなっていたものが聖霊論である。これは神論、キリスト論、終末論などに比べるとこれまでのエイレナイオス研究では比較的陽が当たらずにきたテーマである。私自身のことを振り返っても、聖霊論への関心は希薄だったことを認めざるをえない。その後の鳥巣義文、P・ネメシェギ、A・ブリッグマン(二〇一二年)、J・ベアー(二〇一八年)において聖霊論に焦点が当て直されてきたのは当然のなりゆきであった。大庭氏の本書はこの趨勢を受けて、エイレナイオスの救済史全体の中で聖霊が果たす最も重要な働きを見事に明らかにする。それは肉および魂と合体することで、人間を〈神化〉、すなわち〈完全なる人間〉へ上昇させることにある。
著者自身の「あとがき」によれば、学位論文提出後の口頭試問では、指導教授の鳥巣義文氏他から、「グノーシス主義との対決をより明確にし、〈今日〉の解釈学的地平におけるエイレナイオスの神学的貢献の可能性とその限界を鮮明にする」ことを将来の課題として指摘されたとのことである(二八四頁)。事実、その後五年の歳月をかけて仕上げられた本書にも、その課題に取り組んだ跡が認められる(第一章と第五章)。それでも著者は、これは今後に残された課題だと言う。私としてはその課題に向けて、一点に絞ってエールを送りたい。
私見では、エイレナイオスの救済史の神学には、そのストーリーを整理して記述するだけでは見えてこない次元が潜んでいる。それは現代の言葉で言えば、非神話論化によって初めて取り出される実存理解の次元である。かたやエイレナイオスが自分の聖霊論の中核とみなす〈完全な人間〉は、こなたグノーシス神話(物語)にも現れる。それは神話の冒頭で延々と否定詞を連ねて表現される〈至高神〉そのものの正体に他ならない。グノーシス神話は実は神話ではなく、人間論なのである。この観点からすると、多くのグノーシス神話に典型的な〈ソフィアの過失〉の定型場面が興味深い。ソフィアは最下位とは言え、超越的な天満界の存在の一つである。それが過失を犯して流産の子を産む。それが悪の権化、つまり可視的世界の創造神である。しかし、この過失はソフィアだけの責任ではない。至高神〈完全な人間〉がソフィアにとって知ろうにも知りえない神であること、そもそもその至高神が自分の思考を働かせて、認識主体と認識対象に自己分化を始めたことの責任が問題になる。天満界のもろもろの存在(アイオーン)の生成はいわばその自己分化の進展にほかならず、その極点がソフィアの生成だからである。とすれば、可視的な悪の世界の生成もソフィアの過失にとどまらず、至高神のそもそもの自己認識の行為にまでさかのぼるわけである。至高神は〈完全なる人間〉とも呼ばれるのだから、悪は他でもない人間が自分自身のなかに、自分が〈知〉の主体と客体に分かれたことに、淵源するのである。
実存論的に見れば、分化を始めた人間の自己が、その分化のゆえに生み出される悪との欠乏の世界に落下し、そこで本来の自己と非本来的な自己の間の分裂にまで昂進する。やがてその本来の自己について、〈我(人間)即神也〉が成り立つことを〈認識〉して、元の自己に回帰するという円環運動が成り立っている。この回帰を可能にする〈認識〉が 〈グノーシス〉(gnôsis)と呼ばれる。しかし、グノーシス主義は、前述のように、そのソフィアの過失に知への欲求がはらむ危険性の認識も込めている。こうして〈知〉に対するグノーシス主義の両義的な理解が明らかになる。〈知〉は悪を生むと同時に救うもの、救うと同時に悪を生むものなのだ。
おそらくエイレナイオスは、グノーシス主義の言う「御父以外の別の神」(至高神)が、実は〈完全な(第一の)人間〉の別名にすぎないこと、グノーシス主義神話の冒頭の否定神学のトポスはそれを神話(物語)で表現するにすぎないことを、少なくとも感知していたのではないか。これが私の推測である。先行の教父テオフィロス(『アウトリュコス』二18)では〈神の両手〉の一つが〈ソフィア〉であったものを、大庭氏が言うように、エイレナイオスが意図して〈聖霊〉に置き換えたというのも、さもありなんと思われる。
グノーシス主義は単純な主知主義ではない。否定形でしか表現できない至高神が実は〈人間〉に他ならないという発想は、超越なき現代の人神の思想(人間即神也)そのものであり、その現代的アクチュアリティーはあまりに明瞭である。エイレナイオスがこのアクチュアリティーを保っているのも、一見〈低級な下手物〉としか見えないグノーシス神話をどこまでも朴訥に書き留めたがゆえである。是非その朴訥を引き継いで、グノーシス神話への単純なレッテル貼りを打破していただきたい。本書の著者の今後に期待するところ大である。