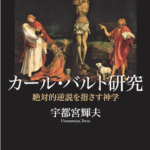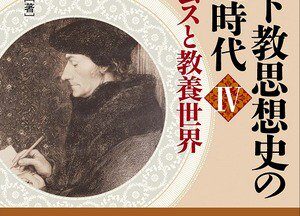ロシア・ウクライナ戦争の現実の中で平和憲法が問う
〈評者〉寺園喜基
「客観性に逃げるな、主観性に責任を持て、という言葉がありますよ」、こう教えてくれたのは著者の木村公一氏である。では著者自身はこの言葉をどう実践しているのか。それについては明白である。
著者が責任を持つ視座は「虐げられた人々」への関与である。破壊と殺傷の犠牲者たちや平和的生存権が剥ぎ取られた人々の叫びへの関心である。これには理由となる幾つかの経験があった。小学生のころ祖父から日露戦争での地獄体験を聞いたこと、また宣教師として派遣されたインドネシアの神学校で十七年間教鞭を取っていた間に、旧日本軍の従軍慰安婦問題やスハルト独裁政権打倒運動に関わったこと、またその間アジア・バプテスト平和委員会の委員長として働いたこと、そしてまた、その後に「人間の盾」としてバグダッドで経験したこと、などである。
本書は二部から構成されている。第Ⅰ部ではウクライナ侵攻に、第Ⅱ部では日本国憲法に焦点が当てられる。だが、この二つを二元的に分離して理解してはならない。むしろ相互に作用し合っている。そして、ロシア・ウクライナ戦争の現実の中で日本の平和憲法が何を問いかけているのか、ということを聞こうとしているのである。憲法を、大人が肩越しに子どもの作文を見て「どれどれ」と手を加えようとするように読むのではなく、憲法という学校の生徒として、憲法が問いかけていることを現在の平和ならざる状況との関連で聞こうとしているのである。
内容を見てみよう。第Ⅰ部は「なぜ『軍事侵攻』は起こったのか」と題されている。ウクライナとロシアの戦争が十八世紀以降に今回を含めて五回起きていること、そこには背景として宗教地政学的な歴史があることが述べられ、また、プーチンとロシア知識人たちに「ウクライナ蔑視」があることが指摘される。これは見逃し得ない指摘である。戦争という大河の激流もこのような心情を泉としている。著者はこれをプーチンの論文「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性」と「開戦演説」から解き明かす。そしてこの流れの中で、一九九一年のウクライナ独立から現今の戦争状況を分析している。この第・部で特筆すべきは、著者がロシアの軍事侵攻を高みから批判するのではなく、日本の負の歴史と重ねつつ加害者意識をもって記述していることである。
第Ⅱ部では「平和に生きる道と『国家安全保障』」について憲法の平和に焦点を当てつつ述べる。筆者は憲法を論じるに際して「戦争責任」からアプローチして、「加害性の自覚なしに講釈するいかなる憲法論も私は否定する」(七三頁)と主張する。そして憲法が想定していない平和と想定している平和を示して、後者は「歴史の終末論的ゴールとしての平和」であるとする。それは安全を平和と混同しないというボンヘッファーの主張とつながる。具体的には「核なき世界の実現」、「民衆の社会安全保障」等が提案され、「非暴力による平和創造」へと導かれるのである。
筆者の的確な神学的洞察に基づく戦争と平和構築に関する分析および提言は、この暗い時代にあって行くべき道を照らしていると思う。