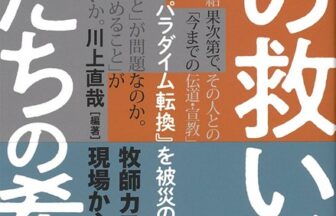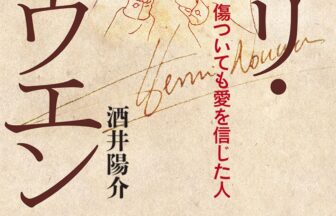時代の危機に抗する哲学的思索の書
〈評者〉江口再起
深い思索の書である。時代の危機に対する鋭い洞察。その思索はルオーの描く名画『キリストと漁夫たち』に至る。もう少し言えば、かかる現代社会の危機に抗して、宗教とくに「生命の宗教」たるキリスト教に、役割はあるのか、と竹田氏は問う。この問いに対して、彼は、実に意想外の角度(ラインナップ)から光をあて迫っていく。それが本書の醍醐味である。(ちなみに本書は、前著『生命の宗教 キリスト教』の姉妹編だというが、その前著のラインナップも迫力があった。レッシング、シュライアーマッハー、ディルタイ、ニーチェ、ウェーバー、カミュ、田辺元が論じられたのだ!)。
本書の全体構成(目次)は、次のとおり。
第一章 カニバリズム─武田泰淳の文学作品に即して
第二章 ナルシシズム
第三章 オリエンタリズムの彼方─シモーヌ・ヴェイユに即して
第四章 責任倫理─D.ボンヘッファーに即して
第五章 技術時代における宗教、キリスト教
終章 いつも場末にいるキリスト
竹田氏は、戦後、人肉食いをテーマにした小説『ひかりごけ』を書いた武田泰淳を論じ、ナルシシズムとグノーシスに根をもつ全体主義を風刺するカミュを論じ、シモーヌ・ヴェイユの思索の遍歴をオリエンタリズム克服として論じ、ボンヘッファーの責任倫理を「共に生きる生」の構築と論じる。意想外の展開である。そして本書の中核論文に当たるのが、第五章である。そこでは現代社会が真正面から論じられる。竹田氏は現代社会を「技術的世界」と捉え、その現代の技術の本質を「総駆り立て体制(Gestell)」と断じたハイデガーに注目する。そして、かかる「総駆り立て体制」に抗するところにこそ、「生命の宗教」たるキリスト教の公共的世界に対する責任・役割があることを、緻密かつ力強く論じていく。
さて、終章は「いつも場末にいるキリスト」と題されている。論じられているのはフランスの画家ルオーである。一章から五章までの、いわば硬派の哲学・神学的論文から一転して、詩的な美的な調べが響いてくる。ルオーは聖書的風景を描いた画家である。そこに描かれるのは、最も弱く小さくされた人々の苦悩を共にする「いつも場末にいるキリスト」である。具体的には『キリストと漁夫たち』などを分析しつつ、竹田氏は次のように書いている。《彼(ルオー)が、秋の黄昏を好んで描いたように、秋の寂寥のうちに自らの身を委ねきらざるをえない貧しく小さくされた人びとが「苦難のキリスト」と共にいる》。「生命の宗教」であるキリスト教の、現代における社会倫理を問われれば、それは貧しく弱く小さくされた人々への責任こそが、その中軸となると答えるべきだと、本書を読みつつ、私は思った。