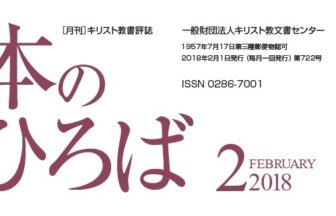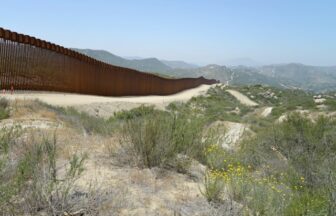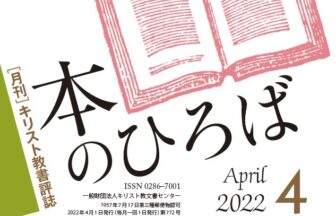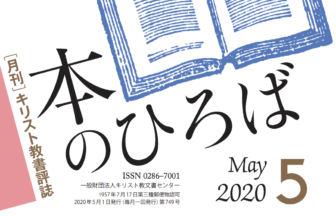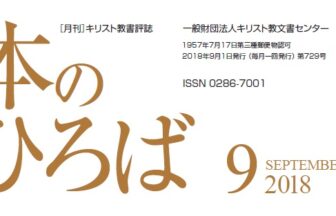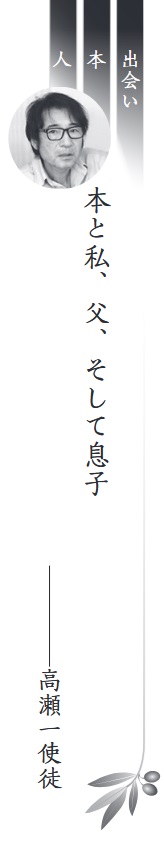
私は、決して読書家ではないし本が好きかどうか問われると、「好き」と即答できる自信もない。そんな私がこのコラムを書くのは不遜の極みと思っている。
私の幼少期から青年期はテレビ全盛の時代であった。娯楽だけでなく知識や情報は殆どテレビから吸収していた。そんな私を見て読書家だった父は、「本を読みなさい」とよく声をかけてくれたが、馬耳東風の態度であった。大学は消去法で文学部に落ち着いたが、専攻は一番楽に思えた日本近代文学を選択した。当然課題として夏目漱石、森鷗外、川端康成、芥川龍之介、太宰治等を読まざるをえなかったが、誰かに陶酔することはなかった。その後受洗して三浦綾子の作品や信仰書を熱心に読んだ時期はあったが、本が好きという境地に至ったとは思えない。
読書スタイルとしては多読より精読が好きで同じ作品や場面を何度も読み返した。今でも遠い昔読んだ本を読み返し新たな発見をしたりして心の潤いになっている。そして若いころに少しだけだが本を読んでおいて良かったとも思っている。
両親が他界し実家を整理していると父の読んだ大量の本が倉庫や押入れから出てきた。小説から俳句、趣味の本から実用書、信仰書から他宗教の本と実にバラエティーに富んでいる。父は児童養護施設を出た後は開拓農民として土と向きあった人生だったが、本を読むことで生活に潤いを与えていたのだろうと想像する。
現代はネットの時代だ。私の子どもたちもSNSやユーチューブを聴視することに時間を費やし、本を読んでいる姿を見かけたことがない。ネットは、AIにより読者を多様な分野や視点の意見を聞くことから遠ざける危険性がある。また情報をいち早く得ることはできるが、文学作品のように後々読者の心が潤うような体験を与えてはくれない。そんな大学生の息子が心配になり「本を読みなさい」と父からの受け売り言葉で諭すが、その言葉に馬耳東風だった若かりし日の我を思い出し内心苦笑している。
(たかせ・かずしと=児童養護施設さんあい理事長(前園長))