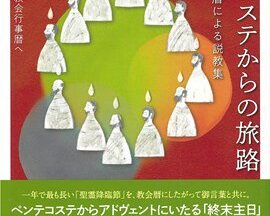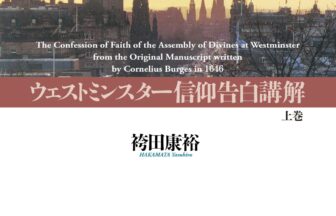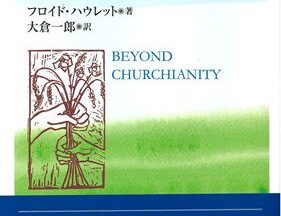さあ、書を持ち、旅に出よう!
〈評者〉小海 基
本書は、三九歳でディートリヒ・ボンヘッファーが強制絶滅収容所で絞首刑となって80年となる本年に、新全集版『倫理』(新教出版社)の名邦訳を四人のお弟子さん(全員が宮田聖書研究会出身者や元ゼミ・メンバー)と共に出された九七歳の宮田光雄先生の、おそらくは最後の著作となる(あくまで非公式声明。九月に行われた日本ボンヘッファー研究会全国研修会で内容深いご挨拶をいただいた感じでは、まだまだ出されると期待させるが…)そうである。七二頁の小さな美しい書物であるが、出版したのが、岩波書店、新教出版社といった大手ではなく、決して大きくない仙台のキリスト教書店である「エッサイの木」というのもいかにも先生らしい。またこの本を企画した大越美穂社長のセンスと英断にも敬意を表したい。
「活字離れ」と言われる風潮が私たち日本のキリスト教界にも広がっている。しかし真実に繰り返し読まれる出会いというものがある。書物は単なる「情報」源ではない。一人の人の全人生を「旅」しながら、繰り返し味わうべきものである。そうした書物との幸せな出会いを本書から改めて知らされる。そうした「人生の一冊」と出会ってほしいものである。本書に収められている写真の中で、何度も読み込まれて装丁もボロボロになった独語版『倫理』や『抵抗と信従』(獄中書簡集)がとりわけ印象的である。「私たちは、生涯かけて長い道程を歩いていかねばなりません。それは、本来、さまざまな出合いの旅なのです。素晴らしい友人、あるいは素晴らしい書物との出合いによって、これまでとは違った自分に変えられ、新しい世界に開かれていく旅でもあります。…」と語り出される本書の前半は、そもそも「エッサイの木」の開店記念講演であった。宮田先生の書物の出会い方は、活字を一人で読むだけに留まらないで、若い仲間と分かち合い、討論し合い、更には書物を片手にボンヘッファー終焉の地であるフロッセンビュルク強制収容所跡、ボンにある友人のベートゲ宅、ボンヘッファーが収監された今は取り壊されてしまったベルリンのテーゲルの刑務所の九二号室(ここまで入った日本人研究者は他にいない)…と、本書と共に、まるで私たちも著者と共に旅しているかのようだ。
実際に旅し、ボンヘッファー直接に出会った人たちと話してきたからこそ知らされる意外な姿にも出会えるのも魅力。「ボンヘッファーの声には『人びとを魅惑するような響き渡る調子』がなかった」(一七頁)。弁舌家どころか、「冷たさ」、「よそよそしさ」を感じる人もいた位だったというのだ。一方で当時「悪魔のゲストハウス」と呼ばれたテーゲル刑務所の監視人さえも、「この人のような…囚人を、まだ見たことがありませんよ」と感嘆させた(二七頁)「厳粛な真実さ」の姿。
本書後半は私も参加した二〇〇七年年のボンヘッファー生誕百年記念講演。年齢差では圧倒的に若い婚約者マリーアとディートリヒが〔特にリルケの詩等をめぐって〕いかに対等に対話していたか、二人の『往復書簡』の終わりあたりでは、むしろ「二人の立場は逆転していくかに見える」と、先生は読み解かれていく(五一〜五五頁)。若い人たちと読書会を続けてきたからこその発見だと感嘆する。