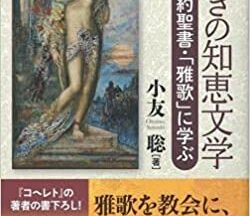信徒の貢献とその信仰を掘り起こす
〈評者〉小海 基
「日本の教会で何故ドイツのような闘い、取り組みがなせなかったのか」という強い問題意識をもって生涯をかけてドイツ教会闘争の研究に取り組み、二〇一九年に逝去された雨宮栄一牧師の遺稿が、待望の出版となった。
闘争史に分け入る誰もが抱く疑問に、ヒトラー暗殺への関与の是非がある。国防軍軍人を中心としたボンヘッファーたちのゲルデラー・サークルは暗殺計画を繰り返し、ついに七月二〇日事件(ワルキューレ作戦)の失敗によって多数の犠牲者を出した。「暗殺計画にあまりに依存しすぎ」た(一九二頁)と本書でも指摘されている抵抗運動の弱点もあった。人生で一度は平和主義に立っていたはずの牧師や信徒たちが自分の信仰の中でどのように心の整理をつけていたのかという問いは今も残り続ける。敗戦後、抵抗権が法的に整備され、名誉回復の再審裁判が次々と起こされるはるか以前の時代である。
ドイツ教会闘争研究は、ニーメラー、バルト、ボンヘッファー等々、どうしても牧師や神学者を中心に追いがちである。その中で、神学的に語ることのない信徒たちが(著者が前著で扱ったペーレルス弁護士も含めて)牧師に優るとも劣らないどころか、過酷な最期を遂げながらも重要な役割を担っていったという事実を掘り起こし、ひとつひとつ明らかにしていったのが著者最晩年の諸著作だったのだなと、改めて思う。読み応えのある一冊である。
本書で扱われるジェームズ・フォン・モルトケ伯らのクラウザウ・サークルは、ヒトラー暗殺やクーデターを志向せず平和主義に徹した抵抗グループである。若いころから英語が堪能な弁護士で海外に広くネットワークを持つ彼のもとで、一九四〇年代に形成されたこのサークルには、社会主義者、労働運動指導者、官僚、カトリックとプロテスタントの違いを超えた聖職者と信徒、抵抗派の国防軍軍人、ヴァイマール共和国支持者等などと、他の抵抗グループには見られない多彩な顔触れの、主に三〇代の人々が集まった。敗戦後の新生ドイツの再建計画を練り、連合国に抵抗運動の存在を知らせ、敗戦工作を行った(五~七章に収められた三回にわたる協議会報告の詳細は圧巻! なるほどこれが六七年のヨーロッパ共同体ECや九三年のヨーロッパ連合につながったという指摘も納得!)。巻末に挙げられているモルトケ伯以外の主要人物二一名中生き残った者はわずかである。その中にはテーゲル刑務所付牧師としてボンヘッファーたちを支えたベルヒャウ牧師もいて、その広がりには驚かされる(ティリッヒの神学がその広がりに貢献していたことも本書から得た発見の一つ)。
それにしてもこれはドイツ教会闘争の全体像を俯瞰していた著者だからこそ書ける一冊である。その行間からうかがえるのは、残された資料発掘の苦労である。ゲシュタポの厳しい捜査や逮捕の連鎖を避けるため本人たちが証拠文書を残さなかったことに加え、逆にナチも連合国側の追及を避けるために敗戦直前に重要資料を処分した。
敗戦後のドイツ国内では五〇年代まで彼らに対する犯罪者扱いが続き、年金申請も退けられ、遺産も凍結され、モルトケの妻フライヤはまだアパルトヘイト政策が始まっていなかった南アフリカに移住を余儀なくされた。更に東西分断が再評価の足かせとなった。五〇年代には暗殺計画グループの再評価が始まっていたのに、モルトケらの非暗殺計画グループの再評価は八〇年代になってからだという。巻末に収められている二八の重要文献の三分の二はようやく二一世紀になってから出版された。教会闘争の全貌に迫ることの困難さがうかがえる。
ベルヒャウ牧師の仲介で交わされたモルトケ夫妻の往復書簡は、二〇〇九年にようやく公開が許可され、二〇一〇年刊行された。六〇〇頁に及ぶというこの『テーゲル刑務所からの別れの手紙』を今私は心底読みたいと願っている。