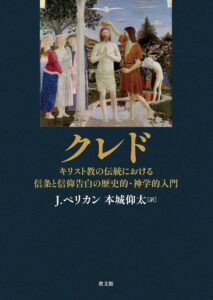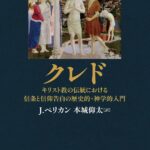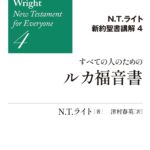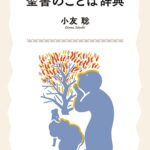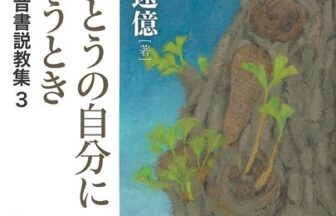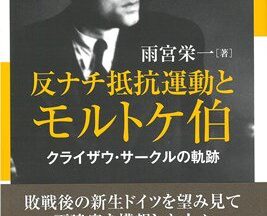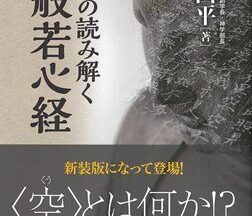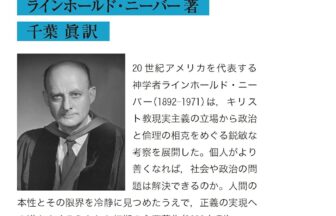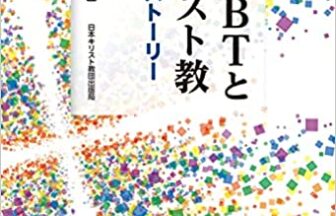第一ニカイア公会議から一七〇〇年の今、信条と信仰告白の意味を問う
〈評者〉小高 毅
本書の帯には「古代から現代までの膨大な文献を渉猟し、信条と信仰告白の定義・起源・権威・歴史を詳述した記念碑的著作」と謳われている。
本書冒頭に、ここで取り上げられる「信条と信仰告白の略語」が表記されているが、その数は二六五に及ぶ。そこには宗教改革期に出された諸「信仰告白」のみならず、トリエント、第一、第二ヴァティカン公会議の公文書、さらには「教皇ピウス九世の誤謬表」まで含まれている。ローマ・カトリック者である筆者としては意想外のことである。
著者は信条と信仰告白の二語の意味を、信条(creed)は「宗教的信仰の短い権威的な定式」、信仰告白(confession)は「宗教的信仰の公式な声明」として用いるとしている(五四頁)。その意味で考えると、たとえば、第二ヴァティカン公会議のその後の流れを決定づけたものとして『典礼憲章』に注目し、「信者が、キリストの神秘や真の教会がどのようなものであるか、生活の中で表現し他者に示すための主要な手段である」と典礼について宣言しているとの指摘(六五六頁)はまさしく正鵠を射ており、他の文書も含めてそれらはローマ・カトリック者のみならずプロテスタント諸教会と東方正教会のキリスト者、さらにはすべての現代人に対する信仰告白である。同じことが本書で取り上げられている、すべての信仰告白に言えるであろう。ここに「二〇〇〇年にわたってキリスト教会やキリスト者を生かしてきた信仰こそが伝統である」(六七四頁)とするペリカンの主張の表れを見ることができよう。
二〇二五年。三二五年にニカイアで第一回公会議が開催されてから一七〇〇年を迎えている。この節目の年にあたり、我が国でもそれを記念する催しが企画されているようである。この時期に本書が刊行されたのは、その意義を再考するためにも、真に時宜を得たこと、訳者ならびに出版社に感謝を申し上げたい。
当然ながら一七〇〇年前の公会議の信仰宣言が今如何なる意義を持つのか、との問いが発せられるであろう。本書の著者は「信仰告白宣言を欠くことができるのか」という問いに対して「たとえ以前の信仰告白宣言がもはや規範的なものとは考えられないと述べるだけのものであっても」、「できると考えるのは本質的に困難なこと」であると指摘し、譬えをあげて次のように本書を結んでいる、「レコードショップやリビングルームの棚にコンパクト・ディスクが積み上げられている時、CDほど静的なものはないだろう。その形式で出荷されて保存されれば、親から子、孫へと演奏されることも聴かれることもなく手渡され、不活性で字義どおりに何世紀にもわたって保存されるだろう。それらはカタログに記載されている売買商品である。それでも、まさにそれらの『不活性さ』と静的さが継続していることが、瞬時に、ベートーヴェンのカルテット、モーツァルトの魔笛、あるいはヨハン・セバスティアン・バッハのミサ曲ロ単調の『ニカイア信条』といった響きの中で突然、動的なものとなるのである。歴史的には、まさしくこのことこそ、信条と信仰告白が何世紀にもわたって繰り返し行ってきたことなのである。
そして、信条と信仰告白は、なおもこれを継続していくことができるのである」(六七〇─六七一頁)。