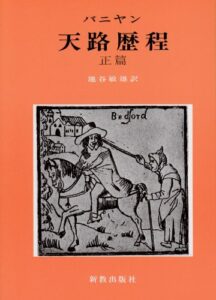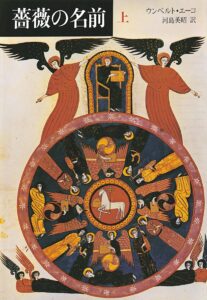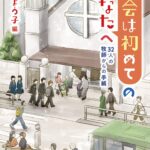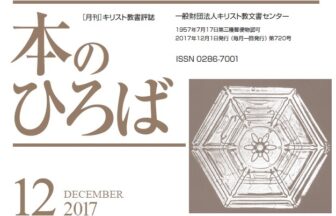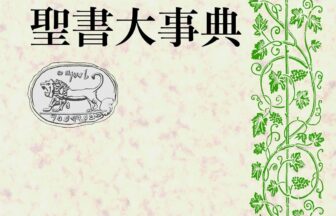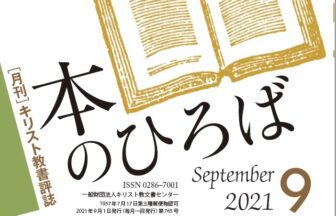ノーベル賞作家ジョン・スタインベックは、『アーサー王と気高い騎士たちの行伝』(多賀谷悟ほか訳、大阪教育図書、二〇〇一年)の序文で、こう書いている。
「聖書をわたしは肌を通して吸収した。わたしの叔父たちはシェイクスピアを発散したし、『天路歴程』は母の乳と混ざっていた。(中略)聖書とシェイクスピアと『天路歴程』は万人のものである」。
生涯のベスト3を選ぶなら、私はやはりこの三冊にするだろう。生まれた時から、聖書は私の人生に織り込まれていた。牧師である父の説教を通し、母の賛美歌を通し、日曜学校の先生たちの教材─絵本は紙芝居は勿論のこと、本物のうずらと手作りマナ、ビニール袋のヨナごっこ、紙パックを繫げた等身大の十字架などなどを通し、私は聖書に書かれたことを本当だと知った。二〇一一年の震災のあと、仙台からやってきたキリスト教書店の移動販売車で買った、青いジッパー付の小型聖書が今に至るまでのマイ聖書である。一年で通読し、爾来何度もあちこちに蛍光鉛筆で線を引き、書き込みした跡が残っている。
本に関するあらゆるランキングの一位が不動だから、今度はそれに次いで読まれた、あるいは、それに次いで有名な本を読む、というのが、私の読書歴となった。ダンテの『神曲』、ゲーテの『ファウスト』、それにシェイクスピアと出会ったのは小学六年生の頃。『神曲』を通して、W・ブレイク、J・L・ボルヘス、大江健三郎らと出会った。『ファウスト』はそれをテーマに一冊の本を書いてしまった。シェイクスピアは目下苦闘中の修士論文のテーマである。とはいえ、自分にとって文学的出発点となった一冊といえば、私は迷わずジョン・バンヤン『天路歴程』を採る。
そもそも、私の考えでは、文学とは一つの樹のようなものだから、その根っこである聖書から生まれなかった物語などない、と言いたくなる。のだが、確かに、「聖書から生まれた」というテーマに、これ以上に相応しい本も他にあるまい。私が本作と出会ったのは、小学四年の頃。図書室で『天路歴程 光を求める心の旅路』(関根文之助訳、小学館、一九八一年)という児童向けのリライト版を手に取った。
主人公は、基督者という男である。彼は一冊の本(勿論、聖書のことだ)を読んで、巨大な「罪」という荷物を背負うことになる。絶望する基督者の前に、伝道者という人物が現れ、「天の国」を目指すよう言う……幼い私はたちまち、その物語に魅了された。そこにあったのが、お馴染みの聖書のイメージだったからだ。聖書に出てくる武器を使い、基督者は戦う。道中、モーセが登場したり、ロトの妻の塩の柱が立っていたり……言うなれば、それは聖書の一大テーマパークなのだ!それもそのはず、作者のジョン・バンヤンは牧師であり、本作の文章はすべて聖書の箇所に由来しているのだから。同時代のジョン・ミルトン『失楽園』と比較すると、バンヤンはそもそも文学的な素養がある人間ではなかった。だからこそ、聖書を読み込み、誰より使い熟して、文学史上類を見ない作品を生み出すことができた。
本作は「小説」という文芸ジャンルの始祖の一つとなり、トールキン『指輪物語』やC・S・ルイス『ナルニア国物語』などのファンタジー小説、現代のRPGゲームの嚆矢となった。その影響力は、世界中で聖書に次いで翻訳された、とされるほどだが、なぜか日本での一般的な知名度は皆無に近い。芥川龍之介が「愛読書の印象」という随筆で、「名高いバンヤンの『天路歴程』なども到底この『西遊記』の敵ではない」と語っていることから、大正の知識層には一応「名高」かったのかもしれないが、少なくとも現代の文学者やクリスチャンで『天路歴程』を愛読する、という人はついぞ聞かない……と思っていたら、数年前、リービ英雄氏が『天路』(講談社、二〇二一年)という作品を発表され、今年の三月から、池澤夏樹氏が『すばる』(集英社)上で『天路歴程』という連載を開始された。
私もまた、最新小説『携帯遺産』(朝日新聞出版)では本作にオマージュを捧げている(カバー装画にはずばり『天路歴程』の地図を使った)。願わくは、より多くの人が『天路歴程』の巡礼の旅に出られんことを。
次はハーマン・メルヴィル『白鯨』。ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』とも迷ったが、こちらはゾシマ長老の説教の部分だけ読んで貰えたらいいし、既に多くの人が読んでいると思うので。対する『白鯨』は、名前は聞いたことがあっても、実際は読んだことのない本ランキング第七位(鈴木調べ。ちなみに一位はプルースト『失われた時を求めて』、二位は紫式部『源氏物語』、三位は……)。その割に、好きな人は兎に角好きで、かくいう私もその一人である。実はこれ、聖書とシェイクスピアから生まれた小説なのだ。主人公の名はイシュメール。老船長はエイハブ。ここから既に聖書模倣が始まっている。途中で、唐突にシェイクスピア劇を思わせる、科白が始まり、独白が挿入される。この感じ、すごくよく分かる。というのも、私自身ずっとそういうふうに小説を書いてきたのだ。小四で聖書を通読し、小六でシェイクスピアと出会って以来、私はいつも構成や精神性は聖書を、表現や人物造形はシェイクスピアを基に、一冊の本を作ってきた。これでは到底他人に読んでもらえない、と薄々気が付いてはいたが、気が済むまで書き、大学に入ってから改めて思想的・文学的な基礎固めを始めた。そうして何とか小説家になった。とはいえ、未だにあの二刀流時代が懐かしくもあり、当時の作品を読むと、その無手勝流ぶりが羨ましい。『白鯨』はそんな私の、ありえたかもしれない未来を先取っていた。
最後に、定番ながらウンベルト・エーコ『薔薇の名前』を挙げないわけにはいかない。中世の修道院を舞台に、「黙示録」に準じた連続殺人事件が起こる……というあらすじは、巷に溢れるオカルト本やB級クライム映画めいて聞こえるが、そうした類の作品は皆、本作を目指して失敗したのであって、本作自体は断じてそういう物語ではない。中世史の専門家が、持てる限りの知識を総動員し、しかし生来の遊び心は失わずに、究極のエンターテインメントとして書いたのが本作だ。惜しむらくは、未だ文庫化されることなく、単行本が上下巻合わせるとかなり高価な点で、そのせいで私も手に取るのが遅れた節がある。が、『構造と力』も『百年の孤独』も文庫化された。いずれきっと文庫化されるだろう、と信じて待ちつつ、今はやはり単行本上下巻を買い揃えて、その知の迷宮を堪能しよう。本作で重要なモチーフとなるのが、写本という営みだ。我々はグーテンベルク以後の世界に生きており、聖書はどれも同じように読むことができるが、当時の聖書はすべて一字一句人の手で書き写され、限られた人間にしか読むことはできなかった。私はいつも、自分の手元にある一冊の聖書が、どれほどの人の手を経て、自分の手に届いたのか、ということを想像するたび、神の愛を実感する。
色々な本を紹介してきたが、結局一番は聖書を読むことだ。当然ながら、これ以上によく書けた本はない。つい先日も「ヨハネの福音書」のラストを読んでいて、はあ〜格好良すぎるでしょ、と溜息をついてしまった。今は「ガラテヤの信徒への手紙」を読んでいる。パウロの筆致の〝近さ〟と言ったらもう……。これからも、聖書と格闘しつつ、小説を書いていきたい。