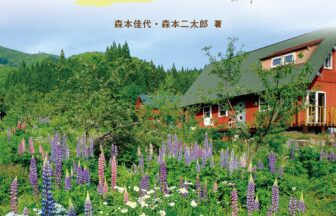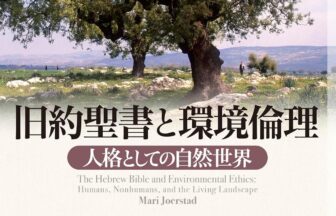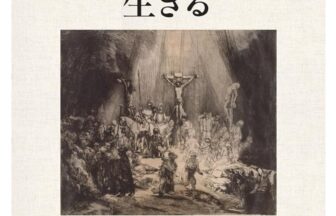現代に与える多くのヒント
〈評者〉小檜山ルイ

ヴェーバーとフランクリン
神と富と公共善
梅津順一著
四六判・456頁・定価4950円・新教出版社
教文館AmazonBIBLE HOUSE書店一覧
「われわれは、以下の事実を自明のことと信じる。すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている……。」一七七六年に出たアメリカ独立宣言の中で最も有名な一文。起草者は理神論者トマス・ジェファソン。当初の草稿には傍線部の創造主への言及はなかった。入れるよう助言したのは、庶民を知るベンジャミン・フランクリンではないか。大学院生の時、齋藤眞先生がそう推測されたことが、読後、鮮明に思い出された。
本書は、マックス・ヴェーバーが有名な『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』においてフランクリンに「資本主義の精神」の典型を見たことに着想を得て、通常は啓蒙主義の申し子とされるフランクリンの宗教的側面に光を当てる。第一部は、フランクリンのピューリタン的出自を父の世代から説き起こし、理神論に傾斜した若き時代を経て、道徳の実践という形での独自の信仰生活に至った道程が描かれる。第二部は、印刷所経営者としてのフランクリンが、禁欲的生活態度を獲得する上で、ピューリタン的自省習慣を採用したことなどが紹介され、その禁欲主義と職業観の宗教性が論じられる。また、彼の経済構想が、中産層の利益を重視していたことを論じ、ヴェーバーが資本主義発生時の担い手として中産層を特定したことに重ね合わせる。第三部は、社会企業家、政治家としてのフランクリンを扱い、その「公共善」への志向がピューリタニズムの伝統から引き出されたことを明らかにする。大学設置など、アメリカ植民地で通常宗教的企画として立ち上がったものが、ペンシルヴァニアでは市民的企画として立ち上がり、その中心にフランクリンがいたといった指摘は、なるほど、と思わせる説得力がある。著者は、フランクリンのキリスト教の中に、後にロバート・ベラが構築したアメリカの「市民宗教」の萌芽を見て、本書を終えている。
ヴェーバーやフランクリンの専門家ではない筆者は、この二人の著名人、また前者の「倫理論文」をめぐる長い研究を踏まえて本書に向き合うことはできないのだが、『フランクリン自伝』の読み直しとして多くの示唆を得た。一七八〇年代以降の建国期に共和国市民の属性として「公徳心(virtue)」の必要が盛んに議論された。その起源は通常古代ギリシャ・ローマの共和制におけるvirtus(男らしさを含意)に求められる。筆者はそれが、第二次大覚醒を通じ、キリスト教道徳と接合され、また、女性化されたと考えてきたが、フランクリンにおいては、すでに公徳心はピューリタニズム的公共善と接合されていた可能性を教えられた。
アメリカでは、近年ずっと、「権利」の主張とその擁護を軸に「正義」が追求されてきたが、今、その限界が意識されつつある。個人および多様な集団の「権利」を制限しうる「公共善」をどう見いだし、どう設定しうるのか。現代のアメリカ、そしておそらく世界の喫緊の課題に一八世紀を生きたフランクリンがヒントを与えうる点は多い。
蛇足。フランクリンのキリスト教への接近の仕方は御儒者中村正直のそれ、社会起業家としての生き方は今度一万円札になる渋沢栄一のそれを想わせる。日本でフランクリンを知る学生は今日ほとんどいないが、もっと学ばれて良い人物である。