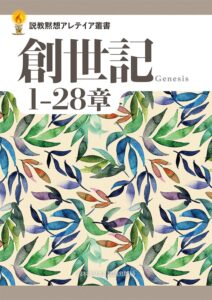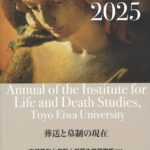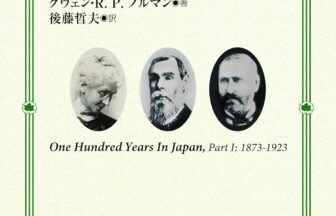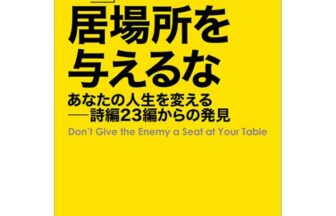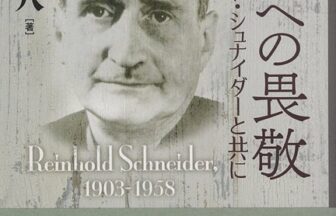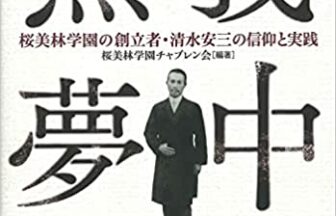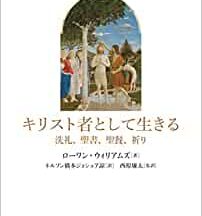創世記を救済史的文脈で捉えて語るための説教者必携の書
〈評者〉朝岡 勝
『説教黙想アレテイア叢書 創世記』の出版を説教者の一人として心から感謝します。
本書では創世記1章から28章が、14名の執筆者により27回に分けられて記されています。叢書化にあたって加筆されているとのことで信徒が読み手であることも想定されているでしょう。聖書の傍らに本書を開き、じっくりと創世記を味わいたいと思います。
まず熟読すべきは小友聡先生による「序論」です。そこでは創世記が「終末の『神の国』の到来をほのかに見通す」、「救済史的ベクトル」(7頁) を持ち、モーセ五書の冒頭に「約束」として置かれるゆえに「すでに『成就』をも暗に指し示すことになる」(同) 書物とされ、「創世記を語るということは、創世記をどのようなより大きな救済史的文脈で捉えるかという聖書神学的展望なしではありえない」(同) と言われます。創世記を読む構えとしたい言葉です。
創世記解釈のポイントの一つは「創造の歴史性」の理解でしょう。神話的表象と読むか歴史的現実と読むか、執筆者の多くが前提とする批評学的な立場で読むか聖書の十全性を重んじる保守的な立場で読むか、その際にすべてを字義通り読むか啓示の中心性を捉えて読むかなど様々な解釈の立場がありますが、「創造の歴史性」が「終末の歴史性」を担保し、それでこそ「救済史」のリアリティを展望する読み方が可能になると思われます。
評者が興味深く読んだのは「原初史」の区切り方です。「創世記の11章までが原歴史として扱われることもあるが、むしろ洪水までが原歴史である」(小泉、88頁) との理解もあれば、「バベルの塔は、原初史の最後を飾るエピソードである。……〔他方〕 この塔は信仰の父と称されるアブラハム (アブラム) が神によって呼び出されるその舞台設定を仕上げる役割を果たしている」(蔦田、89頁) との理解もあり、「彼〔フォン・ラート〕 は、原初史と呼ばれる創世記1章から11章の結末が、11章ではなく、12章1~3節であると考える。世界の始まり、人類が罪に陥ってしまう歴史の結末は、アブラハムから始まる救済史、救済のはじまりであると言うのである」(楠原、101頁) との理解も示されます。執筆者の聖書全体への展望が見て取れる箇所です。
またハガル・イシュマエル物語を巡るキリスト論的解釈(本城、130頁以下)、ソドムの出来事を巡る道徳主義的解釈への警鐘(高橋、166頁)、イサク奉献の山行についての深い黙想 (小泉、202頁以下) から示唆を受けました。
評者もかつて創世記の連続講解説教に取り組み、全92回のうち28章を扱ったのは61回目でした。その経験からすると本書で扱われない箇所 (5章、10章、11章後半、12章後半、14章、19章後半、21章後半、22章後半、25章前半、26章)を読んでみたいとも思いました。しかし「説教黙想」が本来教会闘争の中で奮闘する説教者の助けであったことを思うと、本書は説教準備の「あんちょこ」でなく、「今、この時」に緊張感をもって聖書と向き合う際の対話の相手とするのが相応しいのでしょう。
なおこの拙文が読まれる頃には『創世記29─50章』も出版されているはず。故大島力先生の論考「創世記の説教」も含め、心待ちにしています。