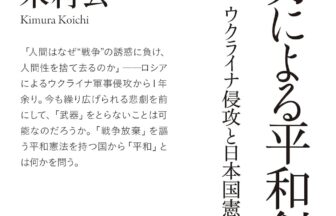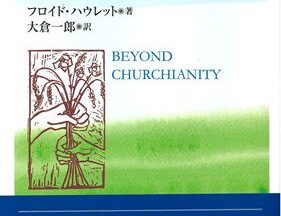牧師の人生を、面白く、深く、易しく語る
〈評者〉阿部志郎
静岡県牧之原にある牧ノ原やまばと学園の機関紙を編纂した50年誌が、一般の読者に向けて刊行された。学園の50年の歴史を綴ったものだが、同時に、東京大学哲学科から東京神学大学をへて牧師になり、静岡で牧会とともにやまばと学園という最重度の知的障がい児の施設を建設、運営に当たった長沢巌という男の生涯とその哲学をまとめたものだとも言える。圧巻なのは、長沢のキリスト者としての、逸れない生き方である。
ノーベル賞を受賞したインドの詩人タゴールは、「すべての子どもは、神が未だ人間に絶望していない証である」と言った。また、ドイツでは、てんかんをもつ子ども達のためのベーテル(神の家)という施設がある。人々はそうした障がいを持つ子ども達を「ベーテルの子(神の家の子)」と呼ぶ。
長沢もまた、子どもの中に神を見、子ども達を深く愛した。やまばと学園が対象としたのは、社会における弱者である子どもの中でも、最も弱い、最重度の知的障がいを持った子ども達であったことは、特筆に値する。しかも、彼は、社会における弱者を強者の側から守ろうとしたのではない。彼らと同じ地平に立ち、彼らと共に生きることを目指したのだ。仏教に信行説法という言葉があるが、長沢の行動の一つ一つが、キリストへの愛を実践していたと言える。
彼の生き方を語る非常に印象的なエピソードが本書に出てくる。行政機関への陳情である。町役場で関係者に知的障がい者施設の建設の話をすると、「たわごとだ」と嘲笑された。県庁でも扱いは同様だった。面会さえしてもらえない。それでも長沢は、同じ時間に窓口を訪れ、一時間ほど黙ってそこに座り、立ち去る。それを毎日続けたという。普通なら、正論を一席かませようと、相手に議論を吹きかけたくなるところだ。しかし、彼はひたすら静かにそこに座り続けた。
最後には、たまりかねた部長が「会ってやれ」と言いだし、事態が動き始める。長沢の無言の中にブレない姿勢に、役人が動かされ、やまばとの味方となっていく。そこに、静かな、しかし、逸れないキリスト者としての生き様がある。
この後、長沢は道半ばにして病に倒れる。学園を引き継いだのが妻の道子だ。日本の場合、キリスト者の多くは、教会を離れ、個人で福祉の事業を立ち上げていることもあり、創設者の強い個性とリーダーシップで運営されてきた施設は、リーダーを失うことで本来の招命から離れてしまうことがある。施設の規模が大きくなるにつれて、制度の上に安住し、出発点から逸れてしまうことも珍しくはない。
しかし、道子は、最も弱い人達と「共に生きる」という長沢の理念を貫きつつ、学園の運営を続けた。そうしながらも、学園は規模を拡大し、成長を続けている。長沢亡き後のやまばと学園の動きを見ていると、50年の長い歴史の中に長沢の魂が躍動し続けているのを感じる。
かつて、「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく」と言った作家がいたが、本書は、ヨーロッパのような教会というコミュニティ基盤を持たなかった日本の歴史の中で、教会を基礎に弱者と共に生きる共同体を作ろうと額に汗した、一人のキリスト者の生き様を、易しく、深く、面白く、語ってくれる。そして、読む者に静かにこう問いかけてくる。
さて、あなたはどうでしょうか。

阿部志郎
あべ・しろう=社会福祉法人横須賀基督教社会館会長