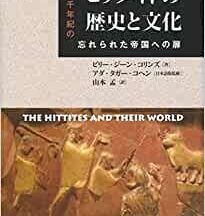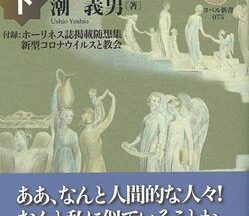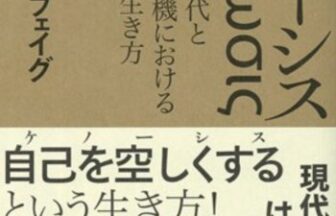贖罪論をめぐる現時点での最も包括的な考察
〈評者〉村山盛葦
本書は、日本の代表的な新約聖書学者によって手がけられた、キリスト教贖罪論の「解体新書」である。贖罪論に関する神学書は数多く存在するが、聖書テキストに堅実に基づいた包括的な研究書は、評者が知る限り出版されていない。
全体は、プロローグ「移行性と加虐性」、第1章「苦難の僕と移行性(移行主題か啓発主題か)」、第2章「マカバイ殉教者の記憶」、第3章「イエスと神の国」、第4章「原始教会の伝承」、第5章「パウロの回心とその神学的特徴」、第6章「パウロからその後の初期文献へ」、第7章「2世紀殉教者の証言」、エピローグ「畑を耕す」からなる。補論として「塵芥について(一コリ4・13b):イエスの死を説明するメタファに関する一考察」がある。構成上の特徴として、各章の冒頭に中心課題の明示、各項に要約のボックス、章末に三択問題やショート・エッセイ問題があり、学習用に工夫が施されている。
本書は一貫して「犠牲のメタファ」という概念でユダヤ・キリスト教のテキストを読み解いていく。つまり、犠牲が何を象徴するかである。浅野氏によると、それは「移行主題」(人の違反行為の責任と結果とが他者に移行する)と「啓発主題」(人に悔い改めと誠実さ(義)を啓発する)の二つの側面をもっている。前者は人身御供的な思想であり「責任の転嫁」を促す。そこでは、多数者が個人や少数者を犠牲とし、これに責任を押し付け(スケープ・ゴート的)、人の死や犠牲に満足するという神のサディズム「加虐性」が認められる。それに対して、「啓発主題」は、悔い改めと「責任の自覚」を促す。そこでは、死や犠牲の衝撃によって信仰者の「パラダイム転換」が生じることがポイントとなる。この方向転換によって、その死と犠牲が自分たちの代わり(代理贖罪)ではなく、自分たちのせいで、生じたことを悟る(「パラダイム転換的な悟り」)。つまり、イザヤ書の「苦難の僕」の詩の「わたしたち」のように、「僕が苦しんだのはじつに私たちのためだったので私たちは悔いた」という責任の自覚が促されるのである。
浅野氏は、ユダヤ教の神殿犠牲には、そもそも共同体成員の敬神と道徳性を向上させる「啓発主題」が内包されていると論じる。その主題は、イザヤ書の「苦難の僕」において顕著に展開され、マカバイ殉教物語へと引き継がれ、殉教者の死の救済的意義が「社会的記憶」として形成されて行った。そして、そのようなユダヤ人共同体で共有された記憶の中で、歴史のイエスは神の国運動を展開し、彼自身の犠牲と死が弟子たちと「多くの人」にこの運動を継承させる啓発主題として機能することを希求した。その後、パウロを始めキリスト信仰者たちも悔恨と回心を経て、神の国運動によって示されたイエスの生き様に参与して行った。ただ、ヘブライ書において、イエスと神殿犠牲とが一体化し、1世紀末頃からイエスの死の説明に「移行主題」が含意され始めた。伝統的なキリスト教贖罪論は、まさにこの「移行主題」の側面と「加虐主題」を包含して展開して行った。そこでは、キリストがあらゆる罪をかぶって犠牲となったため、私たちの罪が赦され、私たちの罪に対する神の怒りが回避された(「移行主題」)。それゆえ、キリストの犠牲は、怒りに満ちて復讐する神の裁きの結果と見なされる(「加虐主題」)。そして、このような贖罪論が「犠牲のシステム」としてキリスト教神学において現在に至るまで稼働してきている。
本書は、「はじめに」でふれているように、高橋哲哉の『犠牲のシステム福島・沖縄』(集英社新書)の読後感の悪さに刺激され執筆された面があるという。高橋氏が批判するキリスト教贖罪論は、イエスの死についての「移行主題」と「加虐主題」とが包含された贖罪論のことである。しかし、このような贖罪論は聖書テキストの思想を代表しているのか、浅野氏は粘り強く問いかける。著者のキリスト信仰とこの世への自覚的なコミットメントが本書全体に底流しているがゆえに、本書は本格的な研究書でありつつ、一冊の信仰の書としての風貌も見せている。多くの学びと気づき、問いが与えられる良書である。以上はほんの一部の紹介である。ぜひ、多くの人々にじっくりと読んでもらいたい。