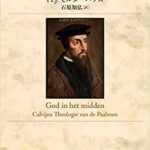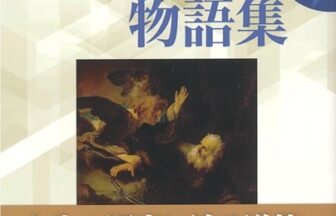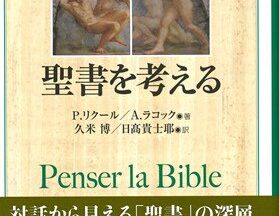忙しい一般庶民のためのレビ記入門
〈評者〉手島勲矢
『レビ記』は、モーセ5書の三番目の本で、祭司自身が執り行うべき様々な犠牲の定めや、イスラエルの民が守るべき戒めが細かく述べられている。福音とは真逆の厳しい律法の世界を、『神の物語』(ロダール著)の翻訳で知られる大頭眞一が、日曜礼拝で読み解くとどうなるのか? 意外にも、レビ記本文の塊が各章の冒頭に正面から引用され、真面目に聖書の言葉そのものと向き合うことになる。しかし、「神に会うために」「神に近づくために」他の平易な見出しのおかげで、なぜ罪を犯したアロンが祭壇に近づくのか等、レビ記のエッセンスが、著者の率直な人柄が滲み出す語り口を通して、最初からすんなりと心に入ってくる。
実は、レビ記の冒頭一章二節に出てくる、ヘブライ語「コルバン(供物)」という名詞は、「近づく」という意味の語根から派生した言葉であり、「供物を捧げる」という動詞(ヒクリーブ)も語根「近づく」の使役動詞の形を取る。つまり、供物を捧げるという行為は、人は自分では神に近づくことができないので、自分たちの身代わりとして何かを神に近づけようとする代替行為とも理解できるのである。
ちなみにレビ記一章二節の「アダム・キー・ヤクリーブ・ミケム・コルバン・ラドナイ」は、文構造上、二人称の「ミケム(あなた方の中より)」の役割が不明なために、「キー・ヤクリーブ(供物を捧げる)」の主語である三人称「アダム(人)」を修飾する語と理解して、「あなた方の中で誰かが主に捧げ物を捧げるときは…」等と訳される。
しかし二人称「ミケム」は、「コルバン(主の供物)」を修飾していると取ることも可能である。すると、「人が、あなた方の中から主のためのお供えを(選んで)するときは…」という含意が生まれ、つまり犠牲となる動物たち牛や羊は「自分たちの中から出すべきお供え」の代わりに捧
げられ、その動物の流される犠牲の血のゆえに神に近づくという話になる。
現代人にとって、この様な、近づくために血の犠牲が求められる「聖なるもの」という概念は、よく分からない、むしろ反発したくなる価値観ではある。それでも、なぜか人は神に近づこうとする? ことについては、隠された祭司の役割があるのだろう。
ユダヤ教ではレビ記を「祭司のトーラー」と呼ぶが、「主語は神様。動機は愛」と著者が繰り返し言うときに、確かに、著者は聖職者であり、俗世の塵の中で生きる一人として自らの弱さを晒しながらも、その神への「恐れ」の向こうには大きな神の「愛」があることを訴える。その様は、聖所に入るとき、大祭司は一番傷つきやすい部分「心臓」の上でイスラエルの子らの名前を背負うべし(出エジプト28・29)という大祭司の胸当ての様を想起させる。「聖者って、清い、っていうよりか、はみ出すほどに激しく愛しちゃう人」、帯の文字のジャブも心に染みる。本書は、まさに忙しい一般庶民のためのレビ記入門でもある。
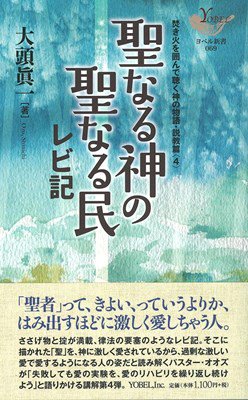
聖なる神の聖なる民-レビ記
大頭眞一著
新書判・192頁・定価1210円・ヨベル
教文館AmazonBIBLE HOUSE書店一覧

手島勲矢
てしま・いざや=大阪大学COデザインセンター招聘教授
Warning: Undefined variable $post_types in /home/hiram2/honhiro.com/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/author.php on line 1447
Warning: Undefined variable $post_types in /home/hiram2/honhiro.com/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/author.php on line 1486