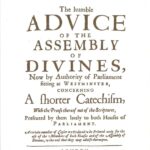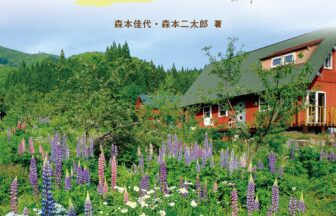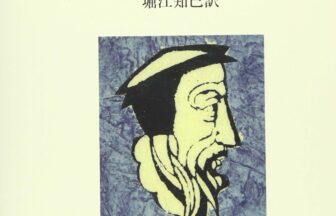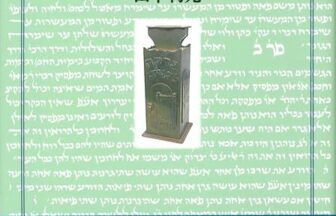教会改革の示す普遍性
〈評者〉齋藤五十三
本書は、カルヴァン・改革派神学研究所主催の「公開リレー講座」として二〇二一年六月一一日から一年八か月をかけて行われた中の十回の講演をまとめた講演録である。世界がコロナ禍で苦悩する中、スイス宗教改革から近現代まで、様々な災禍の中で改革に取り組んだ教会の姿から学びつつ、今の時代の課題を掘り下げるという実に印象深いリレー講座が書籍となったことをまずは歓迎したい。
本書が「災禍」という言葉をもって捉えようとする射程は多方面にわたる。同研究所長の大石周平氏によれば、「自然災害や感染症」の他、「人災」と、そこから「剥き出しになる社会構造」、さらには「戦時の暴力・破壊」も災禍の中に含まれている(七頁)。そうした広がりを持つとなれば、災禍はもはや特別のものではあり得ず、むしろ時代や地域を超えて教会は絶えず災禍と向き合い、その中で神の言葉に聴きつつ改革の汗を流してきたのだと、本書を手にした読者は気づかされるであろう。
紙幅の関係で個々の講演タイトルや講演者の背景に言及することは叶わないが、順を追いながら印象に残った点を綴ってみたい。
ツヴィングリの「ペストの詩」を扱う大石周平氏の講演は本書全体の基調を成し、チューリヒの人文主義者が改革者へと転じた転換点にペスト罹患の災禍があったとの視座が斬新である。ニクラウス・ペーター氏は、過去の歴史に根差した信仰告白の遺産が、災禍の中で新たな聖書の光に照らされつつ刷新されるべきと訴えかける。吉田隆氏は、東日本大震災における神学の役割を問いつつ、苦難を神の訓練と受け止め、そこに再生の希望をも見出したカルヴァンの摂理の信仰に注目する。キャサリン・マクミラン氏は、ヨーロッパの改革を目指したツヴィングリの再評価を呼びかけ、森島豊氏は、キケロまで遡るカルヴァンの抵抗権の系譜が、日本国憲法誕生にも影響を及ぼしたことを、丁寧な歴史考察を通して論じている。吉岡契典氏はヨハネス・ア・ラスコに注目しつつ、ロンドンの亡命者による教会が苦難渦中における「逃れの町」となり、教会の自律を求める中で長老主義政治を生み出したことを解き明かした。朝岡勝氏と石原知弘氏の対談では、「唯一の御言葉」であるキリストのみに聴く「バルメン宣言」の命題が今日も有効であり、教会を励まし続けていることが例証をもって語られる。リタ・ファモス氏は、現在も続く教会の改革が、災禍の中でさらに顕在化していることを指摘しつつ、改革とは人々の活気あふれる「ふるまい」であるとの主張がユニークである。松谷曄介氏は、絶えず形を変えながら中国で継続している「信教の自由」をめぐる戦いを紹介している。最後を飾る渡辺祐子氏は、関東大震災前後の在日中国人キリスト者たちの姿に着目し、負の歴史に光を当てながら教会の新たな課題を明らかにしている。
以上の講演内容には、スイス宗教改革五百年や関東大震災百年、そして東日本大震災から十年等の時代の節目を意識したものが多い。それぞれが歴史における個別の出来事を扱っているのだが、そうした個々の論考の後に見えてくる光景が、いずれも普遍的な真理契機を帯びており、深い印象を心に残したことであった。