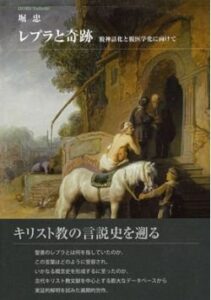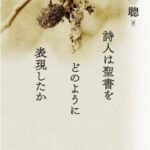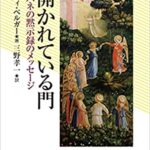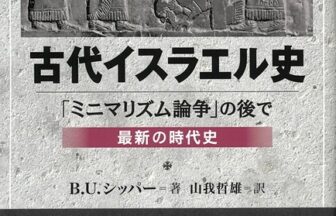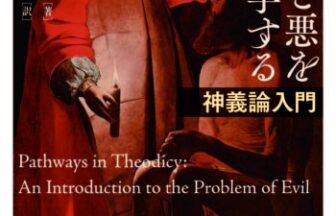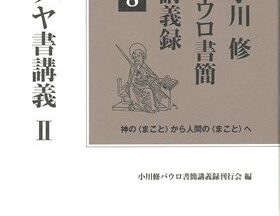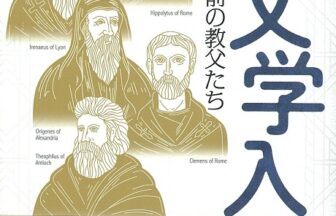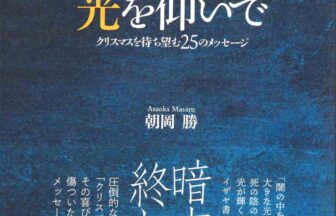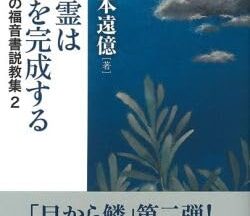「このひとつのことば」をめぐる粘り強い探求
〈評者〉大嶋得雄
本著の序論の冒頭には、デュフェリン侯爵夫人(一九世紀のインドにおける「救らい」運動の後援者)の、「『このひとつのことば』ほど、完全な悲惨と孤独を連想させるものは考えられもしないでしょう」という一文が引用されている。「このひとつのことば」とは、医学名「レプラ」であり、英語名「レプロシー」、日本語名「らい病」である。現在では、差別・偏見を伴うことから、「ハンセン病」と呼ぶように啓発されている。
昭和初期から、ハンセン病者は法律により、主に国の療養所に隔離されてきた。この隔離に加担した宗教のひとつがキリスト教である。このことは、わが国の「ハンセン病問題に関する検証会議」の報告書の中にも書かれている。
国立ハンセン病療養所多磨全生園内の単立・秋津教会で奉仕された故荒井英子牧師の著作『ハンセン病とキリスト教』(一九九九年)のあとがきの一文を引用させていただく。「初めて会う私にこう語りかけてきた一人の老人がいた。『あんた、キリスト教の牧師やてな。なんで聖書にはあんなに《らい病、らい病》と書いてあるんや。あんなに《らい、らい》と言うから、わしら差別されるんや。なんとか言うてみい』。……聖書に引き続き注解書も非難されたりする前に、反省し、誤りを詫びて、誤訳や注解を正しいものにしておくことを切望する」。
評者は長島曙教会の牧師として実質三十六年間在籍させていただき、これらの差別・偏見・隔離の原因の根源が、キリスト教の教典である聖書の原語、「ツァラアト」=「レプラ」の誤訳にあると考えてきた。評者はまた、入園者の病状がレビ記の「らい」と記述されている状態と異なることから、主な出版社にこの誤訳を原語の音読の「ツァラアト」に置き換えるように訴え続けてきた。だから本著の著者がキリスト教の信徒・医師・学者として、「このひとつのことば」にこだわり、誤訳を決定的に指し示すことを自らの使命・責任と感じ、学問されてきたことがよく理解できる。レビ記だけでなく、イエスが語られたレプラもツァラアトを指し、医学上の含意を読み取るべきものではないことをも明示されている。
「ツァラアト」を世に有らしめ、イエスの働きを通してそれを癒そうとされたことも、神の奇跡であろう。しかし後世、「ツァラアト」がハンセン病と理解されたことによってながらく傷つけられてきた神の名誉は、回復されなければならない。
まず、牧師や神父など聖職者、神学生、神学者、そして聖書科教諭や教会役員の方々に読んでいただきたい。この語にまつわる古代、中世からの言説や用語をめぐる混乱、論争なども記されているが、これらを含む書の題名があらわす『レプラと奇跡─脱神話化と脱医学化』の意味するところを理解していただきたい。
旧・新約聖書にはこの語の誤訳が合計六六か所も出てくる。キリスト信者としては、避けては通れないところである。聖書のらいの誤訳を示す書としては、ブラウン著『聖書の中のらい』(石館守三訳、一九八一年)と犀川一夫著『聖書のらい』(一九九四年)がある。良書であるが、誤訳をめぐる歴史的な経緯についての検討という点には、十分でないうらみがあった。この画期的な著書が世界各国語に翻訳されていくことを願う。
そのうえで著者にはいつか、古代から現在に至る、「ツァラアト」、「レプラ」として差別を受けたひとびとの系譜を明らかにしていただきたい。イエスの時代までは存在したが、共観福音書以外の新約聖書にこの言葉は出てこない。では「ツァラアト」とはいかなるものであったか、本著でもこのことについての検討は避けられている。それはいつの時代まで、どのようなかたちであったのであろうか、そして現在は?