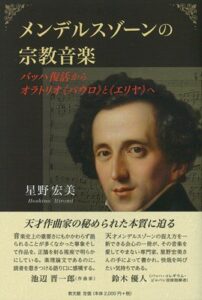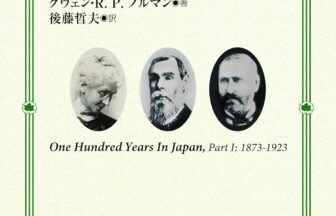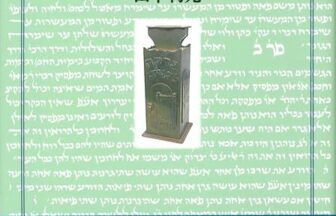天才作曲家の宗教観とその源泉
〈評者〉樋口隆一
いまでは西洋音楽史を代表する作曲家として知られているヨハン・セバスティアン・バッハ(一六八五─一七五〇)であるが、その死後は一般に忘れられ、一八二九年、当時まだ二〇歳の若者だったメンデルスゾーンによる《マタイ受難曲》BWV二四四の復活上演を契機として蘇ったことはそれほど知られていない。当時は作曲家と演奏家が基本的に同一だったので、作曲家本人が世を去るとその作品も演奏の機会を失うことが多かった。
本書は、作曲家であり指揮者でもあったフェーリクス・メンデルスゾーン(一八〇九─四七)によるバッハ復活について詳しく論じるだけでなく、その影響のもとに生み出された彼自身の宗教曲、特に《パウロ》と《エリヤ》というふたつのオラトリオについて深掘りしてくれている。
私自身、バッハの音楽、特にカンタータや受難曲の研究に携わってきたので、メンデルスゾーンの作曲の師カール・フリードリヒ・ツェルター(一七五八─一八三二)が主宰するベルリン・ジングアカデミーの活動や、メンデルスゾーン指揮による《マタイ受難曲》の復活上演については調べもし、書いてもきた。しかし、メンデルスゾーンの専門家である星野氏は、後年、ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者となったメンデルスゾーンによる一八四一年ライプツィヒでの上演についても詳しく調べている。
現代とは異なり、当時はまだ《マタイ受難曲》のみならずバッハのほとんどの宗教曲は未出版だったので、メンデルスゾーンはベルリンでもライプツィヒでも、まず指揮用の総譜と厖大なパート譜を揃える必要があった。楽器も、特に管楽器はバッハの時代とは大きく異なっていた。だから指揮者メンデルスゾーンは、一九世紀当時の演奏家と聴衆に合わせた改訂も余儀なくされた。そのあたりの事情を知るだけでも興味は尽きない。
メンデルスゾーンはまた《マタイ受難曲》のみならず、《ミサ曲ロ短調》BWV二三二の上演をめざして苦労している。実際に上演してみるとわかるのだが、こちらは《マタイ》よりも技術的にはるかに難しく、指揮者メンデルスゾーンの苦労も大きかった。
こうしたさまざまな苦労が、作曲家メンデルスゾーンの成長を助けた。彼自身の宗教作品であるオラトリオ《パウロ》(一八三六年初演)と《エリヤ》(一八四六年初演)こそはその成果ともいえる。それぞれ新約聖書と旧約聖書に題材を取った二曲のために、メンデルスゾーンはみずから台本も書いている。音楽的には《マタイ》の影響が大きい《パウロ》に対して、《エリヤ》はより独創的だ。それぞれの詳しい楽曲解説には、メンデルスゾーン研究家としての著者の情熱が溢れている。
補章として挿入されたシュテーリン論文の翻訳からは、メンデルスゾーンが台本作成にあたって当時の神学者クルムマッハーの説教集の影響を受けていたという興味深い事実が浮き彫りとなった。
終章「神とは何か、真理とは何か」において著者は、ユダヤ人の名家の出でありながら七歳でルター派プロテスタントの洗礼を受けたメンデルスゾーンのエキュメニカルな宗教観を、「心の声に聞き従えば、すべてを見いだすだろう」という父アブラハムの言葉を借りて提示している。