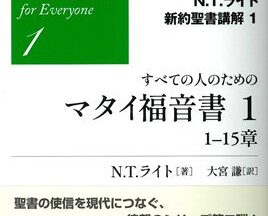慈善を実践するキリスト者の信仰の内面を描き出す
〈評者〉今井小の実
皆さんはコナン・ドイルの『唇のねじれた男』という物語をご存じだろうか。探偵を訪ねた御婦人の夫が実は「物乞い」で一家を支えていたという、現代では想像しがたい話である。ホームズが活躍したビクトリア時代のイギリスでは繁栄の陰で貧富の格差が深刻化していた。また貧困は個人の責任とされ、かつ救貧費の高騰もあり、ポーパー(pauper)にはもはや「神の貧民」という“まなざし”は向けられない。それでも冒頭の話にリアリティがあったのは、チャリティが社会のなかで一定の市民権を持っていたからである。それゆえに民間の慈善事業が活発に行われ、慈善組織協会(COS)も生まれたのであった。社会福祉の通説では、この時期のイギリスは資本主義が進行し、従来の救貧法体制の限界から、貧民救済が教区から本格的に行政へと移行していく時期にあたる。
本書の対象となるのは、キリスト教の隣人愛(カリタス)による慈善に支えられてきた救貧事業が産業化・工業化に伴い、教会や修道院から自治体や国へと移り、「世俗化」が進んだ一八世紀から二〇世紀初頭の社会である。しかしそれはイエスの教えにそった信仰心や隣人への同情心からというよりも、市民としての道徳的義務が涵養された結果であった。本書は、このような時代において、慈善を実践する敬虔なキリスト者が苦悩する姿を描き出した。
第一章「慈善活動でのJ・ウェスレーとW・ブースの『信仰ゆえの苦悩』」では、一八世紀のメソディスト派創設者ウェスレーと、一九世紀後半、救世軍を創設したブースを比較し、彼らの慈善活動があくまでも福音と結びついた「聖化」にあったことを検証した。
第二章「近代黎明期のドイツ都市におけるキリスト教社9会事業」では、一九世紀後半のカトリックの二都市における慈善活動の変遷を比較した。救貧事業の拠り所が、アーヘンではキリスト者としての信念にあったのに対して、ケルンではリベラルな議員らが議会をリードし市民的エートスへと移行していった様子が明らかにされた。
第三章「一九世紀中盤~二〇世紀初頭英米の慈善事業とキリスト教」では、イギリスで孤児事業を行ったG・ミュラーと、アメリカでセツルメント事業を行ったJ・アダムズの実践を、信仰面に焦点を当て比較した。そしてミュラーの実践が「世俗化」への抵抗だったのに対し、アダムズは逆にそれによって慈善を社会事業へと転化させたと結論づけた。
第四章「海を渡るキリスト教社会事業」では、一八世紀を中心に特に貧しい子どもの教育事業をめぐるドイツ(ハレ、ハンブルク)とイングランド間の交流を主にルター派のつながりからとりあげ、貧民のための宗教的教育から、しだいに勤勉な市民を養成する教育へと反転した状況を明らかにした。
本書のベースとなったのはキリスト教史学会のシンポジウムである。これまで社会福祉学界の歴史研究では、その発展にキリスト教が寄与した表面的な事実は明らかにされても、信仰の内面まで踏み込んだ研究は決して多くなかったように思う。社会事業黎明期の慈善活動に対する「信仰ゆえの苦悩」を描いた本書はキリスト者の内面を可視化し、新たな福祉の歴史像を提供してくれる一冊である。