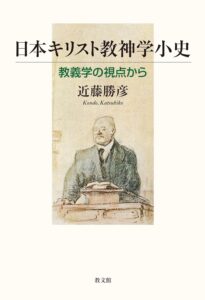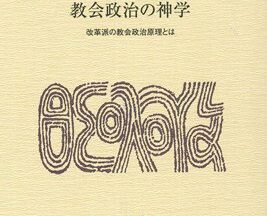日本伝道の閉塞感を打ち破る教義学的思索
〈評者〉森島豊
こんなに面白い本に出会えることは、人生でもそう多くはありません。ページを閉じた後も余韻が長く心に残ります。なぜこれほど惹きつけられたのか、その理由を私なりにたどってみたいと思います。
本書が焦点を当てるのは、日本におけるキリスト教神学の歴史、とりわけ「教義学」です。それは「教会の伝道」のために行われる神学の営みです。ゆえに本書は、福音を伝えようとする人に信仰の原点を思い起こさせ、課題解決への道筋を示し、深い励ましと希望を与えてくれます。
注目すべきは、大著『キリスト教教義学』上下巻を著した当代屈指の著者が、日本の神学史に足跡を残した五人の神学者に光を当てている点です。「神学小史」として厳選されたのは、植村正久、高倉徳太郎、熊野義孝、北森嘉蔵、大木英夫です。次の言葉は、この五名を選んだ理由の一つと思われます。
「立場をまったく異にする者との対論は、神学的探求の歩みを深化させるものではない。しかし類似の関心や同じ神学姿勢にある先輩や同僚との対論は、自らの神学的探求を深め、自己の神学的主張をさらに正確化させるであろう」(七三─七四頁)。
五人はいずれも著者が敬意を抱く先輩であり、同じ神学的関心を共有しています。しかし、称賛に終始することなく、「神を神とする」神学を深めるために真摯な対話を重ね、ときには手厳しい批判もためらいません。その緊張感が、本書に独自の迫力と読み応えを与えています。
読み進めるうちに、私自身、自らの神学理解の甘さを思い知らされました。たとえば「神の痛み」を主題とした北森嘉蔵について、著者はモルトマンとの相違点を明確にし、贖罪論や神義論を含まずに十字架から神の愛の認識へと至る北森神学の構造と欠点を緻密に描きます。その厳密さと深い洞察力に圧倒され、神学するとはこういうことかと教えられました。
著者が示すのは、相手を一刀打尽に斬り捨てるのではなく、その神学を深く理解しようとする姿勢です。北森がエレミヤ書から受けた「神の痛み」の発見の驚きを、日本的心性から説明しようとする他者の試みに対しては、「『神の痛みの神学』の驚きの衝撃力をむしろ日本的に一般化する方向で弱めて解釈することになる」(一五六頁)と指摘します。北森を十分に理解したうえで、神学の理解をより深めるために批判し、考察を重ねています。
さらに魅力的なのは、著者が「私はどう考えているかと言えば」(一二五頁)と率直に述べ、自らの立場を明確にしていることです。多くの日本の神学者が依拠した「場の論理」や西田幾多郎の影響についても、「私自身は、キリスト教神学、とりわけ教義学の思惟を西田哲学の用語で表現しようとは思いません」(一二八頁)と断言し、その理由を説得力ある論証で示します。結果として本書は、指摘ばかりで結局どうしたらよいのか分からなくなるような議論には終わらず、進むべき道筋をしっかりと提示しています。読み進めるほど近藤神学の核心に迫る興味が湧き、大著『キリスト教教義学』の入門書としても最適です。
そして現在、閉塞感の中でもがいている日本の教会にとって、本書は迷いと行き詰まりを打ち破るための最良の一冊です。