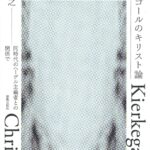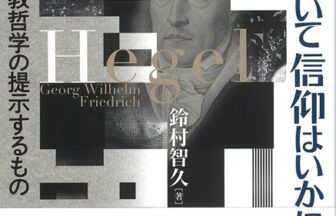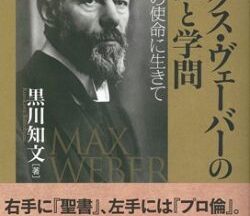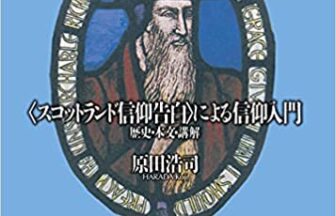状況の中で苦闘する姿を浮き彫りに
〈評者〉須藤孝也
これまでのキルケゴール研究の多くが、論者がその実存をかけてキルケゴールと対決したり、高みにあるキルケゴールを見上げたりする自身の様を記述するものであった。そうした研究は、キルケゴールの思想世界を開示して見せるという長所を確かに備えていたのだが、裏面において、キルケゴールが果たした仕事は何だったのか、という問題に客観的に答えるということに関しては決定的な困難を抱えるものであった。そのことを顧みれば、本書が、キルケゴールが生きた社会的、政治的、思想的、宗教的状況を再現し、その中で苦闘するキルケゴールの姿を浮き彫りにして見せた点は、どんなに高く評価しても、高く評価しすぎることはない。
ハイベアやマーテンセンは、社会の上層部に生きるいわば「勝ち組」として、価値規範を社会のレベルで確定させようとする。彼らにとって伝統宗教たるキリスト教は、既存の「社会秩序」が維持されるためになお有効な宗教、より正確には、有効であらねばならない宗教であった。
他方、一私人たるキルケゴールにしてみれば、キリスト教信仰は、まずもって自身の問題であった。ある種、時代精神のように浸透していたイロニーは、キルケゴール自身のうちにも深く巣くっていたのであり、これを超克することは、同じ社会に生きる他者たちにとっての問題であるよりもまず自身にとっての課題であった。キルケゴールは、自身の実存を刷新するものとして、キリスト教を自ら再発見ないし再構成しなければならなかった。ハイベアやマーテンセンよりもキルケゴールその人の思想が、現代でも少なからずの人々の関心を惹くのは、そのゆえであるとも言える。
キルケゴールはキリスト教に対する自身の関わりを精査していった。そしてその作業は、キリスト教に対する「適切な」関わり方を社会的に明らかにする作業であるとともに、とりわけ教会人たちに対し、キリスト教を「適切に」理解するよう求めるものでもあった。そのキリスト教は、ハイベアやマーテンセン、あるいはヘーゲルが考えたのとは異なる仕方で、人間理性と関わるものであった──あるいは関わらないものであった。キリスト教が19世紀において「危機」を乗り越えるために必要だと考えられた「修正」を、キルケゴールもまた示したのである。
こうした点を明らかにしたことを高く評価した上で、さらに鹿住氏に論じ進めてほしいのは、ハイベアやマーテンセンを振り払うようにして、いわば「人間」の領域から脱却して実定宗教たるキリスト教の領域へと進んでいったキルケゴール思想について、私たちはキリスト教という基準からしか評価しえないものなのか否かという問題についてである。評者もまたこの問題について研究を進めており、決してキルケゴールはキリスト教思想家としてのみ意味をもつのではなかろうと思うのだが、しかしではどういった基準によって評価したらいいのか、なかなか答えが見つからない。今後も鹿住氏が進めていかれる研究に注目したい。