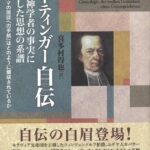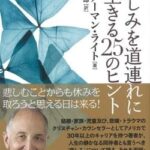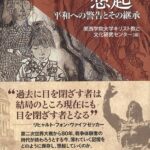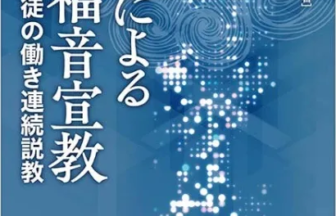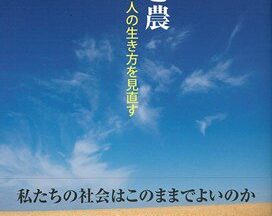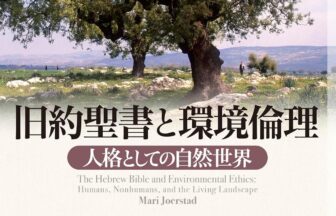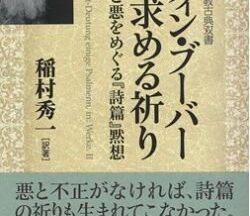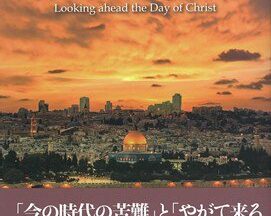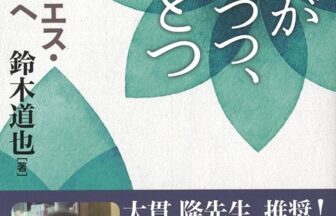キリスト教史に投げかけられた新たな光
〈評者〉若松功一郎
中世にはじまるドイツ神秘主義が、近代の観念論やロマン主義にまで影響を与えているということは、しばしば曖昧な仕方で語られる。この曖昧さを取り除き、ドイツにおけるキリスト教史に新たな光を当てることのできる書物がとうとう登場した。ドイツ敬虔主義の中でも特異な地位を占める神学者、F・C・エーティンガーの自伝がここに出版されたのである。
エーティンガーは当時支配的であったライプニッツ・ヴォルフ学派の哲学が説く単子論的世界観に影響を受けながらも、それのみに満足することはなく、難解をもって知られる神秘家、ヤーコプ・ベーメの神秘主義に触れ、「至純の運動」という力動性において神と世界とを考えるようになる(本書80頁)。しかも、このように神秘主義の影響を受けつつも、彼はつねに聖書の言葉をよりどころとして、正統の信仰に留まっている。こうしたエーティンガーの神学は、シェリング、ヘルダーリン、ヘーゲル、そしてゲーテやノヴァーリスにまで影響を与えたと言われている。エーティンガーの敬虔にして明晰な心が、信仰深き人々の心の底を流れるドイツ神秘主義の精神を捉え、近代人が理解できるよう語り直していく様子を、私たちは本書によって明瞭に確認することができるのである。
以上のことからも分かるとおり、エーティンガーが重要視したのは、世俗の哲学のみならず、聖書そして神の摂理といった神的な事柄であって、これら三つの原理について、彼はそれらが自らの神学の基盤であると述べている。しかし三つの原理はどのように彼の神学を形づくっていったのか。エーティンガー神学の形成過程を知りたいと願う人々のこのような声に応えて記されたのが、まさしく本書なのである(本書18頁、31頁)。こうした性質からして、本書は自伝として、エーティンガーの人物や当時の思想状況を伝える資料的価値を持つだけでなく、これからエーティンガー神学を理解するにあたってのきわめて良き解説書、入門書でもあるといえよう。エーティンガーが言及する思想には、先にも挙げた晦渋をもって知られるベーメのほか、錬金術、ユダヤ教の神秘主義であるカバラ、視霊者スウェーデンボルクの言説など、一筋縄ではいかないものも多い。しかし彼の神学は、当時の南ドイツのこうした特異な思想状況に育まれながらも、多様な思想の森の中で行方を見失うのではなく、かえってそれらを導き手として、キリスト教本来の精神に立ち返ろうとしているという印象を強く与える。
エーティンガーの神学はこのように深遠、ときに難解であるが、本書の訳はあくまで簡明であり、しかも格調を失することがない。訳者である喜多村得也先生が本書に捧げられた努力は大変なものであったのではないかと拝察する。訳者は2023年に召天されたとのことである。先生の努力を思うにつけ、エーティンガーの息子ヨーハンが、亡き父に向け祈ったという次の言葉を思い出さずにはいられない(本書228頁)。
「教師であった人たちは天の輝きのように輝くであろう。そしてその人たちは、多くの人々に義を指し示して、星たちのように不滅にして永遠である」。キリスト教史の重要な断片が、本書をもってまた一つ語られたのである。