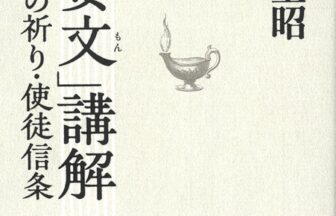犠牲祭儀の本質に近づくと見えてくるイエスの死の意義
〈評者〉淺野淳博
キリスト教界内外からいわゆる「贖罪論」の問題が指摘されて久しい。高橋哲哉氏が『犠牲のシステム』(二〇一二年)において著しく問題のある仕方でキリスト教贖罪論を批判したにもかかわらず、日本のキリスト教研究者らはほんの一部の例外を除いてダンマリを決め込んでいる。教会は贖罪論への違和感を頭の片隅にくすぶらせながら、あるいはまったく意にかけない様子で、「神が罪深い私たちの代理としてイエスを殺して下さり感謝する」あるいはそれに準ずるお題目を繰り返している。そのような状況にあって、エバハルト著『イエスの死の意味 旧約の犠牲祭儀から読み直す』が発刊された意義は非常に大きい。
じつに著者は導入部分において、贖罪論の一般的な問題を、神がその子を殺すことで満足する加虐性と代理による問題解決の倫理性であると指摘し、それらを回避する苦し紛れのキリスト教的応答が自己救済を提唱しているとする(一〇~一三頁)。本著は大きく分けて二つの章から構成されている。第一章は「ヘブライ語聖書を読み直す」と題して、旧約聖書とくにレビ記17章に記される儀礼祭儀を解説する。この第一章での議論を根拠として、著者は第二章「イエスの犠牲」においてイエスの生き様と死に様がいかなる仕方で救済的に意義があると教えられているかを明らかにする。
第一章では犠牲の解釈史を概観し(一七~三〇頁)、さらに聖所と神殿とがいかに神と人との出逢いの場所としてデザインされているかを詳述した後(三〇~五四頁)、五つの犠牲祭儀がいかなる仕方と意図で行われたかを詳述する(五四~八七頁)。すなわち、焼かれる献げ物、穀物の献げ物、幸福の犠牲、浄罪の献げ物、そして罪責の献げ物である。著者は旧約聖書の犠牲祭儀を「多義的な統一体」(八二頁)と表現し、その特徴を以下のように要約する。分離された人が神に接近すること、殺すことに焦点が置かれていないこと、血(の振りかけ)の重要性が限定的であること、植物をも含む多様な素材が用いられること、敬意と関係性を保証するための食事が文脈にあることである。
第二章は旧約聖書における犠牲祭儀を前提として新約聖書における犠牲祭儀への言及の真意を探究する(九〇~一〇六頁)。したがって、イエスが犠牲であるという言説(エフェ5・12)は神の受容を象徴する穀物の献げ物を指しうるし、イエスの血への言及(一ヨハ1・7)は代理死でなくイエスの命の神聖を強調しているし、聖餐における契約の血(マコ14・24)はやはり代理死でなくキリスト者の聖別に焦点がある。さらにヘブライ書における血と犠牲への頻繁な言及はより優れたキリスト論的祭儀を提供するためであり、キリストが贖いの場(ロマ3・25)であるとは血の中の命(レビ17・14)が罪の浄めを可能にすることを教えている。
読者は、旧約聖書への深い理解に立ってイエスの死の意義を探究する著者の明快な議論をとおして、神の加虐性と代理死の倫理性という問題を内包する一般の贖罪理解を考え直す貴重な機会を得るだろう。最後になるが、この重要な著書を明確な日本語にして提供してくださった河野克也氏に感謝をしつつ書評を閉じる。