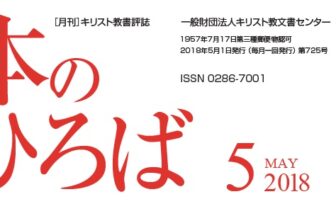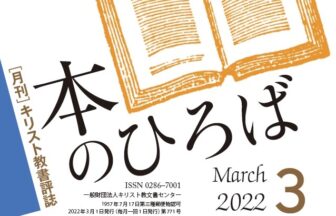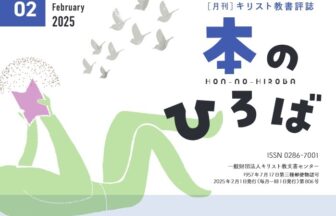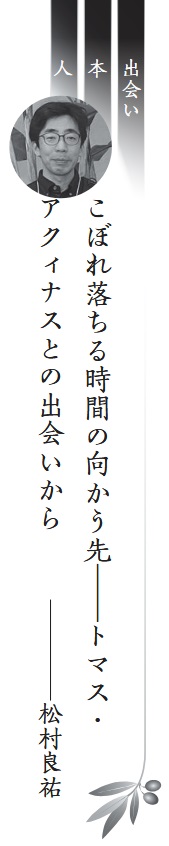
いまから20年ほど前の大学院に入って間もない頃、図書館の書庫の片隅でトマス・アクィナスの『質料の本性について』という本を目にしたことがあった。手にしてみると、それはフリブール大学から出されている哲学シリーズの一冊として校訂・刊行されたものであったが、アクィナスの著作としては偽作の可能性の高いものであった。J.-P.トレルによる『トマス・アクィナス─人と著作』でも「真作ではない著作」のひとつに数えられている。
ふと何気ない話のなかで、その本の話を指導教授の先生にしてみたところ、「人がもっている時間は少ないですよ。しっかりしたものを読むようにしなさい」とおっしゃられた。その言葉は当時からふらふらと関心を変えがちな私をたしなめる言葉であったかもしれない。しかし、それから20年あまりが経ち思い返してみると、その言葉は私をたしなめるだけでなく、その背後には先生ご自身の深い洞察があったように思われてくる。アクィナスやボナヴェントゥラら中世の思想家の著作は一度読んだだけでは理解し尽くせない。何度も繰り返して読み、時間をかけて彼らの言葉を反芻することで、ようやく彼らの思想の一端に触れることができる。そして、それらには時代を超えて人の思考や魂に響く古典としてのちからがあり、それに触れることで、私たちの内面もまた豊かになり、深い理解に至ることができるように思われる。
図書館で目にした本の話を通じて、先生は限られた時間のなかで何に価値を見出し、どのようにそれを使うのかという問いを私に投げかけていたように思われる。「あらゆるものは他人のものであるが、時間だけは私たちのものである」と言われる(セネカ『ルーキーリウス宛道徳書簡集』1.3)。しかし、その時間すらも私たちが手にした途端、すぐに手からこぼれ落ちていってしまう。限りある時間のなかで、彼らのテキストに向かい合い、その言葉を噛みしめながら真摯に読み進めていきたいと思う。
(まつむら・りょうすけ=藤女子大学文学部准教授)