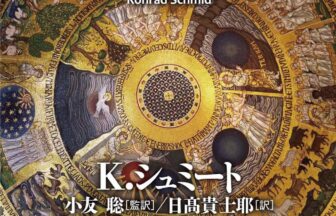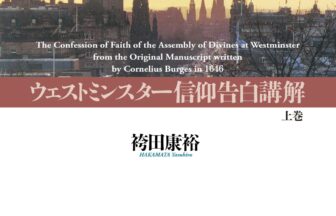暴力・苦しみ・トラウマにあって神学する二人の女性
〈評者〉藤本 満

灰の箴言
暴力、贖罪における苦しみ、救済の探求
リタ・ナカシマ・ブロック、レベッカ・アン・パーカー著
福嶋裕子、堀真理子訳
四六判・452頁・定価4620円・松籟社
教文館AmazonBIBLE HOUSE書店一覧
書評を依頼されて初めて本書を手にした。惹き込まれるように頁を追いながら、線を引き、マーカーをつけ、さらに付箋まで貼って読み返した。書評のためではない。心が震え、一人の男性として思考が揺さぶられたからだ。男も女も同じ神のかたちに創造されているにもかかわらず、人生のあり方が異なる。女性が味わう屈辱は、その尊厳をひどく傷つける。本書は多くの女性の叫びを代表し、癒しを与える。
二人の女性が、自らの子ども時代に経験した虐待や差別の苦い経験を、その後封印した記憶の底から掘り起こし、包み隠さず語り合う。苦しみや屈辱は、過去の出来事として終ったのではなく、無意識のうちに人生を呪縛し続けてきた。何があったのか/なぜ/どのように縛られてきたのか──。当時の辛酸に満ちた出来事と、それが今に至るまで引きずってきた心情が赤裸々に記されている。
牧師・神学者となった二人は、この呪縛を神学的に考察する。十字架という犠牲を尊ぶキリスト教が、時に暴力と共犯関係にあったことを指摘し(19頁)、そこから解き放たれていく。
神学をするとは、このようなことではなかろうか。神学と呼ばれる体系的な知と論理を理解することに多大な時間を費やしても、その労苦が必ずしも、生々しい傷を負った人々を助けることにつながるわけではない。二人は女性として生き、女性に自己犠牲を強いる社会に抗うことで「フェミニスト」であり、男権主義的キリスト教に抗うことで「フェミニスト神学者」である(63〜64頁)。
彼女たちは、自らの問題を単に伝記的に省察しているのではない。「罪人を赦すだけでなく、罪の犠牲となり痛手を負った者を癒す神学」(17頁)を求めている。
すなわち人種差別・性差別・同性愛嫌悪・性的虐待・家庭内暴力──そうしたトラウマの中に生きる人々、暴力的に愛を破壊された人々、その時以来「十全に存在し生きること」(267頁)を妨げられてきた人々すべてに、「いのちに仕える」(77頁)神学を提供しようとしている。
「灰の箴言」というタイトルは、ヨブ記13章12節に由来する。暴力的犯罪・自然災害・病によって家族も自分も犠牲になったヨブに対して、友人たちは、まるでヨブに原因があるかのように責め立てた。
彼らの理屈や原理は、慰めにも励ましにもならなかった。同じ意味で、暴力の犠牲者となった者に対して、十字架の受難と自己犠牲を強いるような神学は、「灰の箴言」となる。
本書は挑戦的でありながらも、乱暴ではない。男権社会の中でサバイブした二人が、柔軟な信仰、包容力ある愛、人の尊厳を蹂躙する伝統を打ち破る勇気をもって、率直な問いを受難の神学に対してぶつけていく。
ヨブは苦難と犠牲に抗い、神に訴えた。その中で、ヨブが「岩間の野やぎが子を産むのを見守っている」神の臨在に触れたように、二人は「自分を照らす光を垣間見るエピファニー」(26、416頁)を経験する。聖霊は、教会にも、地域社会のワークショップにも働いていた。「人間の聖性に尊敬の念を抱き、そのような聖性を世界の中で具現化する人々」が、互いに「強いつながりを築くために、自分という存在を互いに向かって差し出す」(186頁)場に、神は現れる。そのとき、幼児期に性的暴力の犠牲者となった著者の「深いところで何年も続いていたうなり声が静まり、古傷が石のように落ち始めた」(358頁)。性的暴力を振るった男は、人生の偶像となってきたという。だが、神が現れたとき、レベッカは加害者から解放された。こうして父権主義的神を脱構築するとともに、加害者という偶像を脱構築することができた( 326 頁)。第5章に展開される「顕現」の物語は、圧巻である。
訳者二人は、青山学院大学ジェンダー研究センターで活動してきた。同センターが本書の出版を支援したことは尊い。秀逸な翻訳。流れるように大著を読み進めることができる。福嶋裕子氏による「訳者あとがき」は、本書を読むキリスト者には必読である。松籟社(しょうらいしゃ)の本作りのセンスにも感動を覚える。