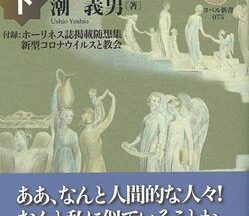箴言研究の未来を指し示す野心作
〈評者〉勝村弘也
本書は箴言の第二部(10・1─22・16)に収集された詞の中から「義人」とその反対語の「邪悪な者」が頻出する冒頭の三章を取り出し、その構成を綿密に考察した研究書である。本書で論じられる箇所が限定されており、しかもヘブライ語原文に関する細かい議論が至る所に出るために、特殊な研究として他分野の聖書の研究者には敬遠されるかもしれない。しかし本書で採用されている詩文テクストの分析法は、聖書文学全般の理解にとってきわめて重要なものであり、またそこで論じられている思想に関しても応報や互恵性のようなアクチュアルな問題を含んでいる。
第6章以下では、小規模ユニット、中規模ユニット、全体の構成の3レベルの区分について説明された後、箴言10─12章の分析がなされる。そこでは10章1節以下の詞集の中に収集されたアフォリズムがランダムに集められたものなのか、一定の「意味ある配列」をしているのかが論じられる。これは小さな形式上の問題ではなく、この詞集全体の解釈に関わる重要な問題である。研究史上重要なフォン・ラートの著作では箴言10章以下に編纂者による意図が一定程度認められるとしたが、配列に関する考察は不十分であり、編纂者の年代設定には問題があった。その後のA・マインホルトの注解書などでは、著者の言う小規模や中規模のユニットへの区分がなされるようになったが、このような区分に十分な説得力があるのかが問題であった。
著者がこのような区分への前提として論じているのが、「聖書ヘブライ詩の並行法」と、これに続く「差異を伴う反復」の部分である。ここは本書全体の理解にとって不可欠であるだけでなく、旧約の詩文学全体に関する理解を深めるはずの箇所である。並行法に関しては18世紀のR・ラウス以来「同義的」「対立的」「総合的(構造的)」の三種類に分類され、これが長くどの注解書でも当然のように使用されてきた。しかし、一九八〇年代以降、構造言語学などの影響下にJ・L・クーゲルやA・バーリンなどによってラウス流の分類が批判されるとともに、より厳密な考察がなされるに至った。バーリンによる「語」と「句」の二つのレベルにおける「文法」「語彙・意味」「音声」の三つのアスペクトによる等価性についての考察は(99頁の表を見よ)箴言以外にも十分応用できるものである。
本論における小規模ユニットの構造を考察する箇所には表がある(189頁など)。そこでは価値の正と負に続いて、人物が単数か複数か、さらに「文の種類・動詞語形」が示されている。正と負というのは、例えば「義人」「勤勉」などが正、「邪悪な者」「怠慢」などが負になる。義人や邪悪な者が単数か複数かが次の項目になる。三つ目に「文の種類・動詞語形」という文法的要素に関する項目を立てたことが本書では重要である。このことによって小規模ユニットへの区分が十分な説得力を示すことになる。
このような綿密なテクストの分析によって、浮かび上がってくるのは、そこで問題になっているのが単なる個人のモラルではなく、共同体全体のあり方だという点である。さらに箴言の語る義人が共同体のために働き善をなす者であるというに留まらず、世界を統治するヤハウェ神への信仰につながっているという点なのである。