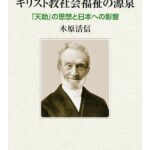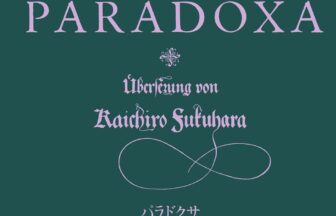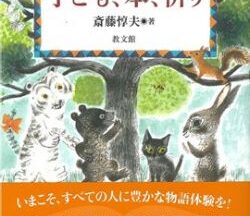歴史の丹念な掘り起こしと現代への貴重な示唆
〈評者〉山口陽一
スペイン風邪が日本を襲ったのは、第一次世界大戦末期の1918年10月から翌年5月(第一波)、同年11月から1920年5月まで(第二波)で、特に20年1月の東京では「地獄の三週間」と言われるほど猖獗を極めた。当時は流行性感冒(流感)と呼ばれ、全国で45万人、台湾・朝鮮・樺太を加えると73万人、世界では五千万人が死亡したとされる。
本書は、これほどの被害にも拘らず、定評ある「日本キリスト教史年表」にも記述されずに忘れ去られた「パンデミックと日本の教会」についての共同研究の成果である。研究を提唱した戒能信生は、教会とキリスト教学校の生徒の死者は百名をはるかに超えると言い、そこには中島力造、ヘンリー・ルーミスの名前もある。カトリック教会を調査した三好千春は、東京大司教区や当時の信者の四分の三を占める長崎教区の史料がないとした上で、函館・大阪教区と札幌知牧区の記録を紹介する。パリ外国宣教会の宣教師95人中34人が召集されており、随所に世界大戦が影を落としている。李元重は、同志社所蔵の豊富な資料を用い、当時「新時局伝道宣言」を揚げて大戦後の伝道と社会改造に邁進していた日本組合基督教会において、スペイン風邪がまったく「課題」となっていないことを検証する。キリスト教学校担当の辻直人は、梅光女学院、北陸学院、東洋英和などを紹介し、感染症に恒常的に直面する時代にあって、宣教師が教える家政学が、栄養や健康への関心を高めたことを論じている。日本幼稚園連盟(JKU)の年報を克明に調べた熊田凡子は、子どもへの衛生指導や医師による健康診断が地域社会を助けたとし、「母の会」の役割に注目する。上中栄の「スペイン風邪と再臨運動」には神学的問いかけがある。再臨運動は、大戦を機にパンデミック前に始まるが、流行性感冒は運動にリアリティーを与えた。上中はこの時期の世界情勢分析にシオニズム運動を加え、究極の解決をめざす再臨運動に「地の塩」の役割を観る。戒能信生が読み解く内村鑑三、柏木義円、金井為一郎、高倉徳太郎の日記においては、柏木義円と高倉徳太郎の比較が興味深い。戒能は、今回の調査で最も深刻に考えさせられたのが高倉の日記であると言う。高倉は教会員や親友を失いながら、流行性感冒そのものには全く関心を寄せておらず、世界大戦への神学的な問いもない。一方、世界大戦とスペイン風邪の関連を捉え、大戦の経済への影響を洞察する柏木の炯眼に驚かされると言う。柏木の家族も罹患し、次男策平は急逝する。柏木は我が子が絶息する悲痛の中で十字架の贖いに感謝し、天父に信頼する子の心を天父が喜び給うことを知ったという。
巻頭には、共同研究の意義を語る神田健次の「まえがき」があり、巻末には30ページにわたる「各教派の機関紙等に見るスペイン風邪の記録」の貴重な一覧表がある。また感染症対策コンサルタントであり神学生でもある堀成美の五つのコラムは、さまざまな感染症の中で生命をかけて福音に生きた教会の歴史に学び、今日の教会に深く問いかけている。百年前「日常的」だった感染症の記憶は、関東大震災(1923年)など大事件の陰に隠れてしまったが、これを丹念に掘り起こした本書は、類書がなく、新型コロナ・パンデミックの時代に生きる私たちにとって不可欠無二の一冊である。

100年前のパンデミック
日本のキリスト教はスペイン風邪とどう向き合ったか
富坂キリスト教センター編
A5判・191頁・定価1650円・新教出版社
教文館AmazonBIBLE HOUSE書店一覧

山口陽一
やまぐち・よういち=東京基督教大学特任教授