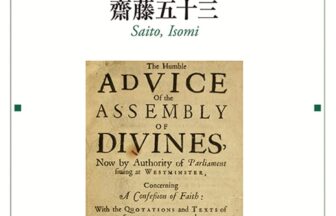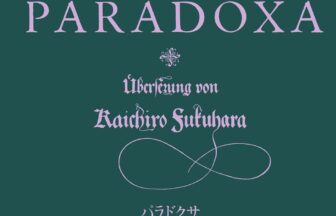自分の傷を見つめ、奉仕する人になるために
〈評者〉英隆一朗
ある人の本を読み続けると、その人ととても親しくなることがある。会ったこともないのに、実際に話をしたわけでもないのに、その人が自分の親友であるような錯覚を抱くことがある。ヘンリ・ナウエンはまさにそのような著者の典型と言えるかもしれない。それは、彼の著作の中で、自分の喜びや悲しみを素直にわかち合ってくれるからだろう。それを読む私たちも、「分かる分かる、そのとおり」という感じで同感してしまう。だから、昔からの友人であるように思えるのではないか。ということは、彼の生きた時代は、私たちの時代そのものであって、その中であがき苦しんでいたナウエンは、もう一人の自分なのだ。
酒井陽介神父の『ヘンリ・ナウエン 傷ついても愛を信じた人』という評伝を読むことは、ナウエンを再発見し、自分を再発見する貴重な機会となるように思える。自分のいだくナウエン像はその人なりでかまわないが、このような評伝を通して、より広い観点から見つめ直すと、さらに理解が広がり深まるのではないか。
まず、第一章現代の霊性の変遷と第二章ナウエン自身の霊的変遷は、彼のバックグランドを理解するのに役立つ。どんな霊性も突然変異のように現れることはまれだ。ともに暮らした家族や社会の息づかいを反映しているからだ。
特に、現代の霊性の変化を概略するところ(18頁から)と、ナウエンの両親の記述(35頁から)が印象深い。それを読むと、ナウエンの人となりがさらに明瞭になる。人は誰しも父母から多大な影響を受けているし、時代の空気を吸っているから。このようなバックグランドは、ナウエンの霊性を理解するためだけでなく、自分の霊性を理解する上でも重要な要素だと思う。自分自身が社会の流れからどのような影響を受け、家族から何を受け継いでいるのかをふり返るのも有意義だろう。なぜなら、ナウエンを読む人は、自ずと自分の信仰のあり方が問われてくるのだから。
第三章以下はナウエンの霊性の特徴をさまざまな角度から分析し、興味深い。これらの記述を読み進めていくと、ナウエンの霊性が多角的に理解できるようになっている。と思いながらも、結局は、ナウエン自身、たった一つのことしか言ってない気がしてくる。彼の一番のキイワード「傷ついた癒やし人(the wounded healer)」である。評者自身、このことばに出合ったときの衝撃は今でも忘れられない。第五章でしっかりと分析されているが、結局、ナウエンはずっと傷ついた癒やし人であった。そして、彼の本を愛読する人びとも傷ついた癒やし人ではなかろうか。自分自身が傷を負いつつ、それと同時に、誰かのために役立ちたいと願って生きている。ナウエンを映し鏡として、自分を見つめ直すことができる。
特記したいのは、セクシュアリティに言及するところ(122頁から)だ。ナウエンに同性愛的傾向があったのはよく知られていることだが、それについて積極的に発言することはなかった。時代の要請がまだなかったのかもしれない。今はLGBTが教会でも意識される時代になった。彼が今、生きていれば何を語っただろうか。彼の未完のことばを、今の私たちがどう語るのか、それが問われている。