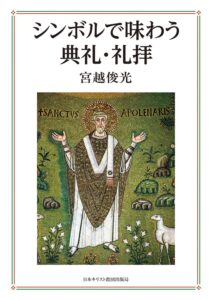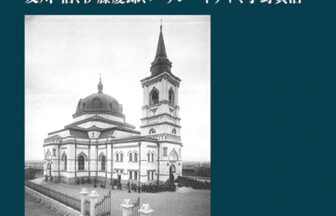教派を超え神の臨在を証しする典礼・礼拝の諸要素に親しむ
〈評者〉加藤博道
季刊誌『礼拝と音楽』(日本キリスト教団出版局)は、国内唯一と言える歴史ある礼拝と音楽の専門誌であり、礼拝の神学や実践、教会音楽について毎号充実した論文や記事を掲載している。本書はその『礼拝と音楽』誌の二〇一四年夏号から二〇二二年冬号にかけての三〇回にわたる連載をまとめ、タイトルも連載時の「礼拝とシンボル」から改めたもので、著者は日本カトリック教会において重要な働きを担う典礼学者である。
典礼・礼拝におけるシンボルという主題は、各教派によってかなり理解や実践が異なるもので、宗教改革以降、分裂さえ招いたような事柄でもあるが、著者はカトリック教会の視点を中心としつつも、同時に多様な伝統があることを常に念頭において配慮を持った記述をしている。
全六章で扱われる事柄は七〇項目に近く、すべては紹介出来ないが概要は以下の通りである。〈第一章 所作・動作〉立つ、座る、オランス、礼、接吻、胸を打つ、行列、〈第二章 諸秘跡の典礼〉パンを裂く、浸礼・滴礼、按手、塗油、歌う、沈黙、〈第三章 典礼暦〉主の日、典礼色、アドヴェント・クランツ、プレゼピオ(飼い葉桶)、40日、洗足、8日目、〈第四章 祭服〉アルバ、ストラ、ミトラ、パリウム、〈第五章 祭器・祭具〉パテナとカリス、祭壇布、朗読用聖書、ろうそく(ランプ)、香、灰、受洗者の白衣、十字架、聖水、〈第六章 礼拝の場〉祭壇(聖卓)、聖書朗読台、説教台、聖櫃、洗礼盤・洗礼槽、東と西、等々。それぞれについて、聖書的な背景と歴史的な発展や変化、とくにカトリック教会においては第二バチカン公会議(一九六二年から六五年)の典礼刷新に伴う変化、そして日本の文化や環境における適応についても丁寧に述べられている。とくに二〇世紀における典礼・礼拝の刷新は、教会論、サクラメント論、会衆の行動的な典礼・礼拝参加の強調、典礼・礼拝の場の刷新等、広範な出来事であり、さまざまなシンボルに対しても無関係ではありえない。
「古来、多くの文化や宗教は、人間が神的、超越的、神秘的な何ものかを捉えるために、人間の感覚で理解できる自然物や図像やしぐさなどをシンボル(象徴)として用いて」きた。シンボルは「それを用いる人々がシンボルの示す意味についての共通理解をもっているときに機能し、共同体のきずなを深める」。キリスト教においては何よりも「わたしを見た者は、父を見た」(ヨハネ十四・九)という言葉の通り、「イエスの生涯が最も根本的なシンボルとなり、神との出会いへと招く」(三─四頁)。そうであれば教会の中の種々のシンボルも、すべて神の救いの計画、キリストの過越の秘義(受肉・生涯・死と復活)にこそ関わり、それを指し示そうとしているのだと再認識した。そして神の民の典礼・礼拝それ自体が、神の臨在を証しする中心的なシンボルであること、それは教派を超えた教会の存在理由ではないだろうか。先に教派的な伝統によって理解や実践が異なると書いたが、むしろ共有している大切なシンボルの方が多いと気づかされる。イラストも含めて親しみやすく連載中から愛読していたが、今こうして一冊にまとまり全体を通してみると、本書はこれまでにない典礼・礼拝のシンボルに関する総合的で充実した一冊となっている。