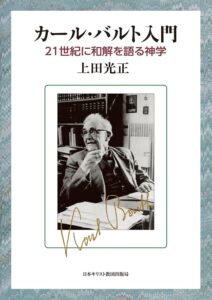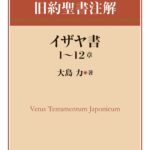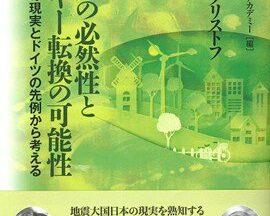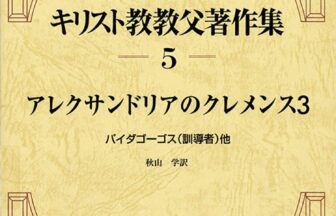著者上田光正氏の 「白鳥の歌」
〈評者〉近藤勝彦
上田光正氏は、60年に近い伝道者の奉仕を踏まえ、「残りの人生で日本の教会に貢献し得る最大の事柄」を期して、本書を著わした。本書は、牧師たちや神学を学ぼうとする人たちに対する上田氏のいわば遺言に当たる。白鳥はその生の最後に見事に歌うという。上田氏は本書によってカール・バルトの神学を自分の「白鳥の歌」とする一群の人々に加わった。
バルトが桁外れな神学者として巨大な雄姿を展開したのは、大冊13巻をもってなお未完に終わった『教会教義学』とそれ以前の『ロマ書』や他の諸著作と膨大な量の論文を含む一大著作群によってであった(その主要なものは本書の文献表に上げられている)。著者はその膨大な著作によって展開されたバルト神学を本書一七〇頁に集約して「バルトに入門せよ」との喝を与える。離れ業とも言うべきこの集約を可能にさせたのは、二つの方法である。一つは「バルト神学の神髄」を彼の「福音理解」、具体的には『教会教義学』の「神の選びの教説」と「和解論」第一部に見い出す道であり、もう一つはそれ以前や他のバルトの全著作をこの頂点に向かう稜線として理解する道である。
後者の道は、バルトの神学的進展の中に断絶や対立や飛躍を見ない立場である。そこで著者は、『教会教義学』の「三位一体論」を紹介しながら、「それはバルトが『ロマ書』の冒頭で啓示について述べたものの丁寧な語り直しであり、……アンセルムスから学んだ『神学するとは何か』ということの応用」であると言う。著者は巨大なカール・バルトの神学の歩みの中に「直線的な進展」を見る立場に立つ。
本書の主要部分をなすのは前者、つまり「神の恵みの選び」と「キリストによる神との和解」の中にバルト神学の神髄があると見て(本書の第5章と6章)、それがおよそカール・バルトの全神学の頂点をなすとする道である。「神の選び」の内容は、あらゆることに先立って「神、我らと共にいます」という神の自己規定の「原決断」がなされたことと言う。著者の言い方では、それゆえ人間が救われるのは人間の「はからい」ではなく、「一〇〇パーセント神の『はからい』であり、それ以外の何ものでもない」。「和解論」の方は、その福音は第一部に描かれた贖罪論にあるとされ、上田氏はそれを「裁き主が裁かれた」という強調に見て、「刑罰代償説」でなく「審判代受説」と呼ぶ。
バルト神学への入門の必要とその意味を力説する著者の熱誠は、本書によって十分に伝わるであろう。読者は、本書によってバルトの著作そのものへと促され、本書の意図は達せられるに違いない。
しかし、バルト神学をどう解釈すべきかという問題を言えば、当然本書に対する反論はあり得る。バルト自身がバルト主義者でなく「バルトを越える」(例えば『ロマ書』から『教会教義学』へ)と言ったのだから、バルト神学内における断絶や超克が指摘されよう。さらには「バルト入門」の後に、日本における牧師・伝道者の経験に基づいて「バルトとの対論」や「バルト神学を越える試み」もあるはずと、著者に対して求められるのではないだろうか。