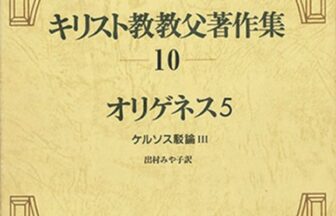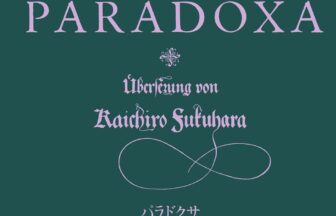ルター「祈り・省察・試練」の人間学
〈評者〉大島征二
全七巻別巻二巻で構成される壮大な企画の中でも、本書『ルターの思索』は別格ではなかろうか。名著『ルターの人間学』(創文社、一九七五年)以来金子氏の著作の多くは、限られた読者を対象として学会誌等に執筆された諸論文が基になっている。「あとがき」にあるように、本書も序論、・、そして「談話室」の九編の書下ろしをのぞき、初出論文が再考を経て集められたものである。シリーズ中の一書としてまとめられたことで、これまで触れることの出来なかった著者の業績を読めるようになった。「高校生の頃からルターの書物に親しんできた」(談話室)著者にとって、ルター研究はアウグスティヌスと並んで研究の大黒柱をなすが、先の著作拾遺もしくは第二巻ともいうべき本書により、著者のルター研究の豊富な成果が熟成された形で味わうことができる。
著者は第一巻の序論において、「人間とは何か」という問題、「とくに、人間の自己認識、つまり『自覚』の痕跡をたどりながらこの問題を今日いかに採りあげ、考察、会得すべきかを明かにすることは極めて重要である」と本シリーズの趣旨を述べているが、本巻においては、ルターにおける「自覚」がさまざまな資料の厳密な読みを通して明らかにされる。先の引用の前に、ヨーロッパ思想史には人間の自己理解の軌跡が、宝の山として残されていると比喩的に語った著者は、今回その中から選りすぐりの宝をわれわれが味読できるようにしてくれた。
元々単論文として書かれたものを本書で統一するに際して、著者が選択した中心概念は「思索」であり「省察」(メディタティオ)である。「省察」という思索の方法は、中世スコラ神学の演繹推理から「具体的な宗教体験に基づく帰納推理」へと転換したルターの思索では一貫して重要な意味を持っている、との認識から出発する。
「省察」というと多くの読者はデカルトの著書『省察』を想起するのではないだろうか。
二元論的立場に立って理性的思考の明晰化、精緻化に努めたデカルトとルターの省察は本質的に異なっている。さらに根底には、デカルトの心身二元論に対して、「霊・魂・身体」の「自然本姓的」三区分法及び「霊と肉」との「性質」における区分とからなるルターの複合的な人間観の相違が存在する。世界を起動させるために神に一つ爪はじきさせるだけで済ました、とパスカルに批判されたデカルトと異なり、ルターの思索の基底をなしているのは霊性における生き生きとした神体験である。自らの方法を、「祈り、省察、試練」の三者から成る「実験的知恵」と述べている通り、彼の神学は生きた神体験の言語化であり、著者はこのようなルターの神学の核心を練達の筆によって描き出している。「神」をほとんど一単語としてしか知らない時代にあって、本書は、ルターが開示する人間の「自覚」に照らして、改めて己の生を顧みることを促している。
「談話室」は本巻においても研究の裾野の広がりを垣間見させてくれて興味深い。