研究のために、文字になった歴史を語り続ける本や新聞・雑誌、その他の資料を日々手にする仕事をしている者として、しばらく前から自分の「本」に対する態度を疑いはじめた。読みたい本より読まなければならない本を優先したり、熟読した本の内容をすっかり忘れたりしている。もとより恣意的解釈、剽窃や焚書といった本への冒涜は研究者として避けてきたが、それでも本に対する自責の念が深まり、以前のように前向きな気持ちで本と接する時間が少なくなったように感じる。
この切ない気持ちを克服するために、私と本との出会いの原点に戻ってみた。未だ私の意識と本棚に残っている「最初に出会った」本は、家族の分区園(クラインガルテン=ドイツなどで行われている市民に貸し出された小規模農園)のバンガローで見つけた詩集である。九歳の私は、自分の手で耕して咲かせたアケライの花と分区園を通るせせらぎの水を楽しんでいたが、暇に飽かせてその本から一つの詩を選んで暗記した。テオドール・シュトルムが1855年に作った「夜鳴きうぐいす」であったが、今でも暗唱できる。九歳とはいえ、詩に描かれている夏と愛の目覚め(思春期の始まり)は、分区園での夏の経験と重なり、それを見事に表現するものであった。収録されていたその他の詩はあまり覚えていないが、詩集自体は自分史の一瞬をとらえているものなので、日本にも持ってきた。
そして日本で、この詩集が母の受けていた1960年代の社会主義教育の高学年国語の教科書であったことに気づいた。社会主義者によって作られた詩を「三世紀に亘るドイツ詩」の歴史に位置づける本であった。私が暗記した詩は、東ドイツの新体制における新しい人間の目覚めを語るものとされていたかもしれないが、そこにある「愛」と「目覚め」とは、時代と文化やイデオロギーなどを超えて語り続けられている。ああ、今の自分でもう一度読みたくなった。
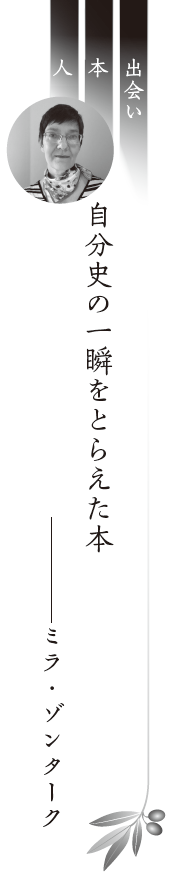

ミラ・ゾンターク
立教大学文学部キリスト教学科教授
Warning: Undefined variable $post_types in /home/hiram2/honhiro.com/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/author.php on line 1447
Warning: Undefined variable $post_types in /home/hiram2/honhiro.com/public_html/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/author.php on line 1486

















