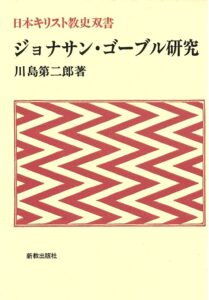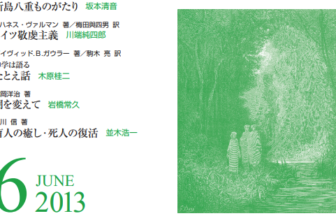聖書の言葉が他の言語・文化圏に伝えられる際、必ず翻訳という実践が必要になります。さまざまな言語に移し替えられることによって、人々は聖書の教えを理解し、信仰へと導かれました。それゆえ、一九世紀に来日したプロテスタントの宣教師たちが最初に取り組んだのは、聖書の日本語訳でした。日本語訳聖書に関する書物は、決して多くはないものの、その中には長く読み継がれている珠玉の良書がいくつかあります。たとえば、日本キリスト教史の大家である海老澤有道による『日本の聖書─聖書和訳の歴史─』(講談社)は、キリシタン時代から大正改訳までの聖書翻訳の歴史を俯瞰しています。門脇清と大柴恒の『門脇文庫日本語聖書翻訳史』(新教出版社)は、門脇が生涯を通じて蒐集した日本語訳聖書の書誌と共に、簡にして要を得た解説を加えています。そして、近年では、内村鑑三の研究で有名な鈴木範久による『聖書の日本語 翻訳の歴史』(岩波書店)は、日本語訳聖書の歴史を平易に解説しています。「日本語訳聖書の歴史を知るためのこの三冊!」といえば、右記の三冊を紹介すれば十分といえますが、今回は、さらに深く知るために次の三冊を紹介します。
① 高谷道男、有地美子共訳、岡部一興編『ヘボン在日書簡全集』 教文館 二〇〇九年
日本語訳聖書の立役者の一人といえば、ジェームス・カーティス・ヘップバーン(ヘボン)の名がまずあげられるでしょう。周知のように、明治元訳を生み出した翻訳委員会(翻訳委員社中)の中心的人物です。本書には、彼が一八五九年七月一九日に日本に向かう船上で書き記した手紙から、日本を離れ、死の一年前、一九一〇年八月二六日に日本に送った手紙までが収められています。この書簡集では彼の派遣元であるアメリカ長老教会に送った手紙が大半を占め、そこには聖書翻訳に関する報告が随所にみられます。ヘボンは聖書の日本語訳を始める前、まず、和英辞典『和英語林集成』の編纂に取り組みました。なぜ、すぐに聖書翻訳に着手しなかったのでしょうか。一八六六年九月四日付の手紙にはこのようにあります。「辞書編纂こそ正しい出発点と申せましょう。これなくしてまた日本語の十分な知識なくしては、聖書を翻訳する十分な資格に欠けるところが多いのです。」聖書の翻訳をするために、日本語の学習、言葉集めが必須とヘボンは考えたからです。ヘボンらの聖書翻訳の訳語の多くは、『和英語林集成』に含まれる語句と共通することから分かるように、この辞書があってはじめて日本語訳聖書は生まれたのです。約七年の歳月を費やし、一八六七年、ヘボンは『和英語林集成』を世に送り出します。その後、ヘボンと彼の同労者であるS・R・ブラウンは一八七二年になってようやくマルコとヨハネ福音書の日本語訳を刊行します。
このように、この書簡集にはヘボンが聖書翻訳を取り組む際、どのような問題に対処したのかが詳細に記されており、翻訳作業の息づかいが感じられます。日本語訳聖書の黎明時代の様子が直に伝わってきます。この書簡を傍らに置きながら、明治元訳やそれ以前の分冊を読むと、また違った味わいがあるでしょう。現在では入手困難ですが、S・R・ブラウンの書簡集、高谷道男編訳『S・R・ブラウン書簡集─幕末明治初期宣教記録』日本基督教団出版部を併せて読むと、翻訳当時の様子がより明瞭になります。
② 川島第二郎『ジョナサン・ゴーブル研究』 新教出版社 一九八八年
近代日本のキリスト教の歴史上、先のヘボンはよく知られた人物ですが、ジョナサン・ゴーブルの名を知る人はどれほどいるでしょうか。ゴーブルは日本国内で初めて日本語訳聖書を刊行した人物です。ヘボンらに先立って、一八七一年にマタイ福音書の日本語訳を公にしました。S・R・ブラウンは、一八六六年七月二日付の手紙でゴーブルについて次のような言葉を記しています。「バプテスト宣教師と称するゴーブル氏は、宣教師というほどの人物ではありません。(略)聖書翻訳者として、自分ではたいそう自負していますが、十分な教育がありません。彼は無学な民衆と、いつもいっしょにいるので、かなり適任だと、自分では考えているようです。ギリシャ語もヘブル語も読めません。」このように、S・R・ブラウンばかりでなく、彼とその翻訳に向けた当時の宣教師たちの厳しい言葉が、その後のゴーブル訳の評価を決定づけてしまいました。そのため、彼の翻訳はこれまでほとんど顧みられることはなかったのです。しかし、本書の著者である川島第二郎による精緻な研究により、ゴーブルの翻訳はS・R・ブラウンが評したような稚拙なものではないことが明らかになりました。ゴーブル訳は最新の本文批評研究を反映したものでした。その訳文は文語体も含んでいますが、主として口語体であり、彼は高い教育を受けていない一般の読者、いわゆる庶民でも理解できるように、易しい日本語で訳そうと試みたのです。
先の明治元訳の訳文は、漢文訓読調の文語体であり、漢語や漢文の素養がある読者を重視しています。しかし、ゴーブルは平易な日本語で訳すことにとって、誰もが分かる聖書を日本人に提供しようとしました。現代の翻訳学の用語を用いて説明すれば、ゴーブルは目標テキストとその受容者を最大限意識した受容化(同化)翻訳を試みたといえるでしょう。このような翻訳方略は、ゴーブル訳から約一〇〇年後に試みられた、日本聖書協会による共同訳のそれと部分的に響き合うものがあります。日本語訳聖書といえば、ヘボンらの翻訳に目が向きがちですが、ゴーブルの働きとその翻訳も決して忘れてはいけない一面であることを教える好著です。ゴーブルと同じくバプテスト派の宣教師であったネイサン・ブラウンの聖書翻訳も、分かりやすい日本語で訳しています。川島第二郎の解説付きの『ネイサン・ブラウン訳「志無也久世無志與」覆刻版』(新教出版社)もぜひ手に取っていただきたいです。
③ 金成恩『宣教と翻訳 漢字圏・キリスト教・日韓の近代』 東京大学出版会 二〇一三年
東アジアの近代キリスト教史全体から日本語訳聖書を捉えると、また違った視点が私たちに与えられます。日本語訳聖書が中国語訳聖書から大きな影響を受けていることを鑑みるならば、東アジアの他の翻訳と日本語訳とを比較することが必要です。本書は、中国、日本、朝鮮におけるキリスト教の宣教活動と翻訳の関係を説き明かした意欲作です。とりわけ、日本最初のキリスト教の週刊紙『七一雑報』の文体の変遷を探った考察が興味深いです。当初、『七一雑報』の編集部は婦女子を読者層に想定したため、記事の文体を漢字平仮名交じり文とすることを旨としましたが、漢字片仮名交じり文の投書が多くなり、この二つが混在します。「こうした文体の混在は、平易な文章でも多くの人にキリスト教的な文明開化思想を啓蒙することを目指す編集部と、漢字片仮名交じり文で信仰の表現を知的に行おうとする日本人読者との間の緊張関係を背景にしているとは考えられないだろうか」(八八頁)と問いかけます。平易な文体にするか、硬質な文体かという問いは、明治元訳の翻訳作業においても議論になったことです。平易な文体を求めるヘボン、ブラウンら宣教師と漢文訓読体を主張する日本人補佐者たち(奥野昌綱、松山高吉、高橋五郎)との対立は、しばしば語られています。補佐した日本人はみな、漢学の素養があり、漢籍に親しむ社会的階層(士族)の出身でした。
彼らのような社会的階層に訴える文体でなければ、日本でのキリスト教宣教において支障をきたすと思い至ったのでしょう。どの文体で訳すかという問いは、いかなる社会層に訴えるか、ひいてはどのような宣教戦略を練るべきかという問いへとつながっていきます。宣教と翻訳は切っても切れない関係にあることを改めて教えてくれる内容です。また、中国、日本、朝鮮の視点から「神」の訳語問題を捉えなおそうと試みた近著、金香花『神と上帝 聖書訳語論争への新たなアプローチ』(新教出版社)も合わせてお勧めします。