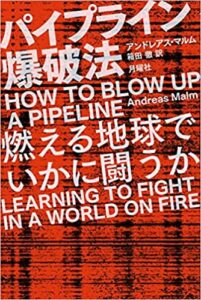わたしが信頼する旧約学者は、キリスト者が「聖地」と呼ぶあの土地の紛争が解決しないかぎり、その地に足を踏み入れることはしないと言う。それは今や紛争地と化した「聖地」が危険だからではない。「聖地」を危険な状態にしているその責任がじぶんたちキリスト者にあると重く受け止めているからだ。
1948年の「イスラエル国家設立」は、ユダヤ人迫害に対するヨーロッパ・北米諸国のキリスト者たちの罪悪によって導かれ、推進された。しかし、「イスラエル国家設立」は、パレスチナ人にとって住まい、故郷、いのち、信仰、アイデンティティを同時に喪失する「大惨事」に他ならなかった。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻のはるか前からパレスチナは軍事占領下にあり、おびただしい軍事暴力と人権侵害がこの土地とそこに住まう人びとに振るわれつづけている。このようなパレスチナ人の歴史と現実に目を背けつつ、イスラエル行きの「聖地旅行」に出かけることは、今なおつづくイスラエルの占領と暴力を黙認・加担することになりかねない。
「パレスチナ問題」とは、「パレスチナの問題」なのではない。イスラエルによるパレスチナの軍事占領、土地の強奪、人権侵害を含むイスラエル−パレスチナをめぐる深刻で未解決の問題をさす。同時に、「パレスチナ問題」とは現在のイスラエルを「約束の土地」と単純に同定し、イスラエルの非人道的な振る舞いを看過しつづける世界中のキリスト者の問題でもあるのだ。
「パレスチナ問題」について日本語で書かれた書籍は数多あるが、今回は比較的最近出されたもので、わたしが関心を寄せている「解放の神学」の視点から、以下の三冊を分かち合いたい。
ナイム・アティーク『サビールの祈り パレスチナ解放の神学』
パレスチナ人キリスト者が著した本はたくさんあるが、ナイム・アティーク『サビールの祈り パレスチナ解放の神学』を推したい。エルサレム・中東聖公会司祭であり、「サビール・エキュメニカル解放の神学センター」ではたらくアティークは、1948年のイスラエル占領時に生まれ故郷であるベイサンから家族共々に難民となった経験をもつ。アティークは、パレスチナ解放の神学のコンテクストを1948年の「イスラエル国家設立」によってパレスチナ人に加えられた「三重のナクバ」(人間、アイデンティティ、信仰のナクバ)に置き、「約束の土地」に固執するシオニスト・イデオロギーとイスラエルによるパレスチナの土地への入植がいかに正統性のない欺瞞に満ちたものなのかを2000年にわたるこの土地の歴史から詳細に論じていく。
アティークが本書で最もおおくのページを費やすのは、聖書、とりわけ旧約聖書に見られる自民族中心的・排他主義的な記述や、土地の占有とそれにともなう排除に関するテクストに対して厳しい批判を重ねていく作業である。アティークがこの作業におおくの労力と紙幅を割くのは、これらのテクストがパレスチナの占領や排除を正当化するシオニスト・イデオロギーの根拠として利用されつづけているからだ。アティークは聖書のシオニスト的解釈がイスラエルの占領政策を進める上でいかに重要な役割を果たしてきたかを明らかにする。また、聖書におけるイスラエルの地を現代の特定の領土にあてはめることは、パレスチナ人をこの土地の「よそ者」として追放することを正当化してしまうと警告する。聖書における「約束の地」は特定の領土・空間・場所をさす言葉ではなく、神の民が生きる場を指し示すメタファーとして受け止めるべきであり、それはイエスの「神の国」理解と通底するものだというアティークの読みは、「約束の地」をはじめとする聖書のあらゆる記述がパレスチナの占領を正当化する政治的イデオロギーとして利用されていることを黙認しつづける世界中のキリスト者を鋭く問うものだ。
村山盛忠『パレスチナ問題とキリスト教』
アティークたちパレスチナの草の根の運動に呼応し、「パレスチナ問題」とキリスト教の責任を問いつづけた人びとは世界中におおぜいいる。たとえば、村山盛忠『パレスチナ問題とキリスト教』には、日本のキリスト教における「パレスチナ問題」への取り組みの一端がまとめられている。
1964年から1967年にかけてエジプトのコプト福音教会で産業伝道の組織化にかかわり、中東のキリスト教と出会った村山は、1967年の第3次中東戦争を間近で経験してもなお、「パレスチナ問題」が「見えていなかった」と告白する。その後、エルサレム聖公会主教のリアーハ・アブ・エル・アサルとの出会いをつうじて、村山はユダヤ人問題を放置し解決することができないまま、政治的シオニズムを容認しつづけるキリスト者こそが「パレスチナ問題」の当事者であると考えるようになり、パレスチナの運動に深く関わっていく。
村山も、アティークたちの解放的な聖書解釈に呼応し、「イスラエル史観」で聖書の物語を読むことの危険性を指摘する。ラテンアメリカをはじめとする解放の諸神学において、解放的モデルとして参照される出エジプトの物語もまた、パレスチナの側からすれば、モーセらイスラエルの民の「帰還」によってその土地に住んでいた土着の人びと、つまり「パレスチナ人」を追い出し、征服する物語にすぎない。
「あとがき」でも述べられているとおり、本書は「パレスチナ問題の解説書」ではなく、この問題と取り組んできた一人の運動家、キリスト者による手記である。過去さまざまな媒体で書かれたそれらの手記を集成した本書は、扱われる時代やテーマも幅広い。それぞれの時代状況から紡がれる村山の言葉は、「パレスチナ問題」をめぐる運動史の記録としても意義がある。また、パレスチナを含む中東キリスト教についての詳細な説明は、「パレスチナ問題」を理解する上で欠かせないものであるだけでなく、ヨーロッパ中心のキリスト教史で後景化されやすい中東に生きるキリスト者の実像を伝えるものとして、いまなお貴重である。
アンドレアス・マルム『パイプライン爆破法 燃える地球でいかに闘うか』
アンドレアス・マルム『パイプライン爆破法 燃える地球でいかに闘うか』は、現在の地球温暖化をはじめとする気候変動とそれに対するラディカルな社会運動について論じたものだ。「パイプライン爆破法」という物騒な(あるいは心踊る)タイトルは、「気候を破局的な事態へと進ませない」ために、火力発電所など化石燃料インフラの損壊、あるいはそのオペレーションを阻害・停止するためにパイプラインを爆破するといった直接行動をさしている。
マルムはこのような直接行動の「パイオニア」としてパレスチナの抵抗運動をいくつも参照する。第一次世界大戦後、ペルシャ湾で発見された油田から欧米に輸出するためにイギリス委任統治領パレスチナにパイプラインが建設された。しかし、1936年にパレスチナ人が起こしたゼネストの最中にパイプラインが破壊され、石油利権を目論む英国人入植者は収入源とエネルギー源を同時に失った。1969年にもイスラエル占領地域の数カ所のパイプラインがパレスチナ解放人民戦線(PFLP)によって爆破されている。
何十年もパレスチナ人は占領の現実と闘いつづけてきた。その具体的な標的はイスラエル兵やイスラエルの民間人といった人間ではなく、占領を可能にし、それを強力に推進するインフラだった。2018年、包囲下にあったガザ地区で展開された「イスラエルの物や設備を燃やすために、発燃性の物質を運ぶ凧」や「ヘリウムを注入して膨らませたコンドームを分離壁の向こう側まで飛ばす技術」を、マルムは「骨の髄まで収奪された人びとが発射するルンペン・ミサイル」と表現する。
「開発」や「インフラ整備」の名の下にパレスチナの土地が収奪されつづけ、樹齢数百年のオリーブの木が切り倒され、家々が破壊され、その横暴に抗議する人がブルドーザーで轢き殺される最悪の現実から、非武装の、独創的な抵抗運動が立ち上がる瞬間を活写し記録する本書は、現在の「聖地」で何が起きているかを知るための手がかりとして、また「化石燃料の採掘」や「開発」や「インフラ整備」を口実に進められる占領の実態を問うために、読んでおきたい一冊だ。