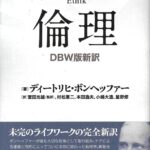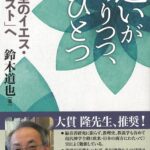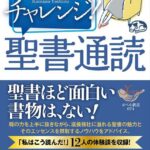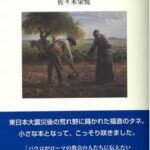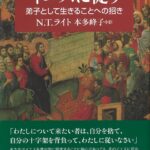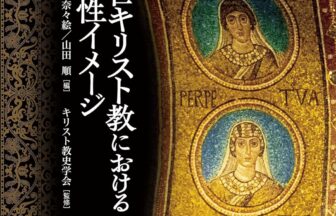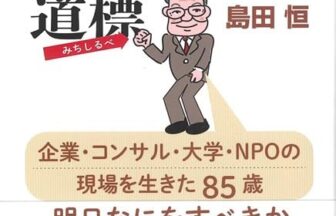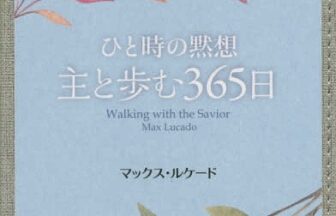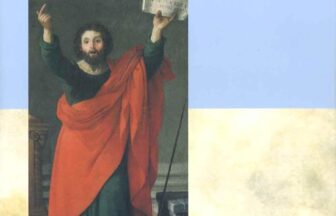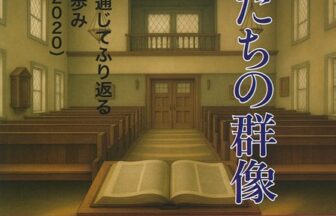赦し、和解、共生を求めた現場からの提言
〈評者〉佐藤司郎
本書を驚きをもって読ませていただきました。何よりもよく勉強しておられること、「伝統的な聖餐論と開かれた聖餐論」など、歩み寄りなど当事者がはじめから考えていないように見える問題に大胆に切り込んで、新たな議論の地平を開こうとしていること、そしてそれらを分かりやすく提示しようとする努力など、今までにない独特の書物に仕上がっています。著者は日本基督教団花巻教会の鈴木道也牧師。牧会十三年目の気鋭の研究者です。
はじめに目次に従い主な内容を簡単に紹介しておきます。
「第一部 違いがありつつ、ひとつ──四福音書の相違と相互補完性」。ここでは、福音書に関する五つの疑問を提示した上で(第一章)、各福音書の固有の「キリスト像」を明らかにし、最後に(第八章)四福音書が相違しつつも相互補完的に理解されるべきことを、キリスト教の歴史に即して明らかにしています。ここで把握された「相違と相互補完性」が、以下本書で取り上げられている今日的諸問題の分析モデルです。
「第二部 「十全のイエス・キリスト」へ──伝統的な聖餐論と開かれた聖餐論の相違と相互補完性」。ここでは最初に聖餐とは何かを明らかにし(第一章)、次いで聖餐をめぐる現代の論議として、伝統的な聖餐論と開かれた聖餐論の二つの違った立場を解説し、それらの根底に「キリスト像」の相違のあることを指摘しています。キリスト観でもキリスト論でもなく、「キリスト像」を一貫して問題にしているのは著者の慧眼です。第三章は、本書の神学的な思考の基本でもある「十全のイエス・キリスト」論が展開されます。「十全のイエス・キリスト」という用語は本書の造語であると著者は断っています。そこには「ひとつの欠けもないこと」と「多様性がありつつひとつであること」の意味が込められています。神学の歴史に古くからある「全体的キリスト」(トートゥス・クリストゥス)とは違うようです。また人間論的領域も含むものとしてバルトなどが使った「包含的キリスト論」などとも異なり、やはり著者独特の概念です。しかしとてもリアリティがある捉え方です。最後に、今後の課題として、第四章「内住のキリスト像」が記されます。
引き込まれて読んだのは、第二部、伝統的な聖餐論と開かれた聖餐論の相違と相互補完性の部分です。日本基督教団の聖餐論議をていねいに検証し、それぞれの立場の背景にキリスト像の相違があること、伝統的な側には「信仰告白のキリスト像」が、他方には「生前のイエス像」のあることが説得的に論証されています。その上で著者の立場ははっきりしていて、こう述べています。「伝統的な聖餐論に立つ一部の人々によってなされた北村慈郎氏に対する『戒規免職』処分は本来、撤回されるべきです」。著者によれば、仮にどんなに神学的に正しくとも正当な手続きを軽んじていいことにはならないし、意見の異なる人々の尊厳を軽んじていいということにもならない。「早急に教団内において聖餐の在り方についての対話が始められていくことを願っています」(二七三頁)。トランプ大統領が再び登場し、対立と分断が深まりかねない今日、赦し、そして和解と共生、これらを大切にする教会、また学校でありたいと、本書を読んで改めて思わされました。