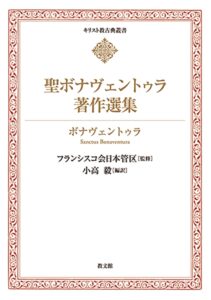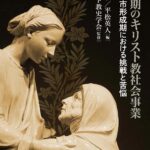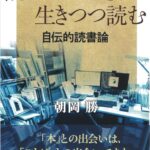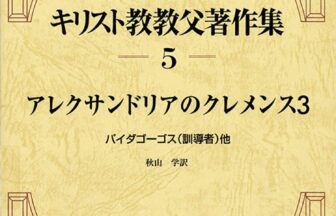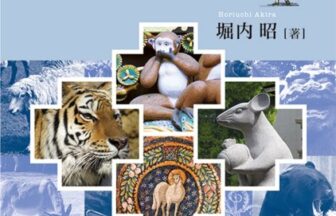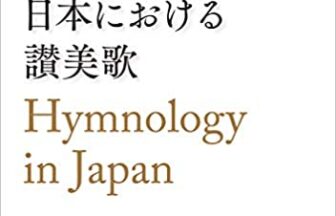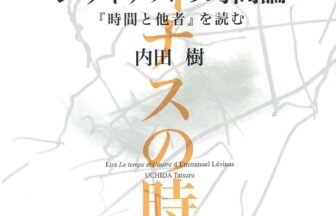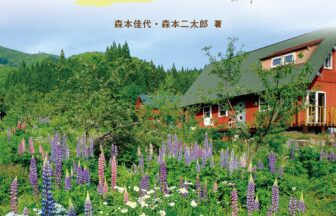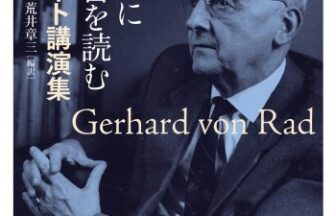中世を代表する巨匠の珠玉の作品を精選
〈評者〉松村良祐
本書は二〇二四年に没後七五〇周年を迎えたボナヴェントゥラの著作から一六篇の作品を精選し、その全文を訳出したものである。
本書に収録されている作品は、(1)『三様の道』や『生命の完成』をはじめとする霊性神学に関するもの、(2)小さき兄弟会の全会員に宛てた『第一回状』などの書簡をはじめとする同会の総長としての活動に関するもの、(3)聖フランシスコや聖体の秘跡を主題とする各説教、(4)神学的著作(『ブレヴィロクィウム』)の四つに分類され、パリ大学教授や小さき兄弟会の総長をつとめたボナヴェントゥラの多様な著述活動の全体を見渡すことができる構成になっている。
これら全一六篇のうち本邦初訳のものが七篇あるが、そのどれもがボナヴェントゥラの思想の特徴がにじみ出た珠玉の作品である。なかでも「一二六二年の夕べの説教」にはフランシスコが受けた聖痕に対するボナヴェントゥラの省察が示されているが、それは師父フランシスコに対して深い畏敬の念を寄せる修道士としての彼の姿を浮かび上がらせるものである。なお、巻末には本書に収録されている作品やボナヴェントゥラの思想を紹介する解説がおかれ、読者が本書を読み進めるうえでのよき同伴者となることが期待されている。
ところで、本書が企画された背景には、ボナヴェントゥラの思想が今日においてあまり顧みられなくなってしまったことがあるという(六四九─六五〇頁)。確かに、ボナヴェントゥラとともに一三世紀を代表する神学者であるトマス・アクィナスの著作が次々と邦訳・出版されていることに比べ、ボナヴェントゥラの著作がほとんど邦訳されていないことは編者の懸念を裏付けるものであるかもしれない。しかし、二〇二四年はボナヴェントゥラと同じくトマスの没後七五〇周年にあたり、二人の神学者に関連した様々なイベントや国際シンポジウムが世界各地で開催された。一〇月にリスボンで開かれた学会で選ばれたテーマのひとつは「今日の哲学に対するトマスもしくはボナヴェントゥラの影響」であったが、それはトマスとボナヴェントゥラの思想を比較するだけでなく、両者が今日の哲学に対して持つ可能性を問おうとするものであった。日本における状況とは異なり、ボナヴェントゥラに対する関心は未だ衰えていないように思われる。また、近年ではボナヴェントゥラのみならず、彼がパリ大学で学んだラ・ロシェルのヨハネスやヘールズのアレクサンデルなど初期フランシスコ会士の思想を扱う研究も相次いで公刊され、ボナヴェントゥラの思想を新たに捉え直すにあたっての土台が整えられつつある。そして、そのような今日的な状況からみたとき、本書の出版はまさに時宜にかなったものだと言えるだろう。
しかしながら、ボナヴェントゥラの没後から七五〇年を迎えた今日において、彼の思想はどのような意義をもつのだろうか。巻末において、編者は三位一体の神に関するボナヴェントゥラの考察が相互に愛し合うのみならず、ともに愛し、ともに愛される個々のペルソナによる力強い愛の交わりに彩られ、われわれをそこへと導き入れようとするものであるという(六五一頁)。それは人間同士の交わりから遠ざかり、希薄になった社会を生きるわれわれに圧倒的なちからをもって迫り、われわれの生のあり方を揺さぶるものであるといえるだろう。本書に収められた一六篇の作品から何を読み取るのかは読者であるわれわれに委ねられている。しかし、編者と同じく、ボナヴェントゥラの思索が現代において意義あるものとして受けとめられることを期待したい。
本書の訳文は、ときに複雑な議論が含まれているにもかかわらず、とても読みやすい滑らかなものである。本書をもとに日本におけるボナヴェントゥラ研究がさらに深められ広げられることを期待するとともに、中世を代表するこの巨匠の作品をこのように翻訳してくださった訳者の多大な労に心から感謝したい。