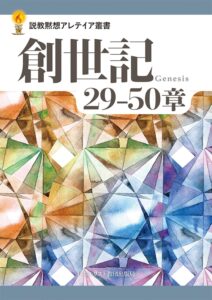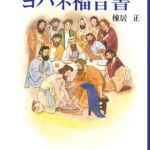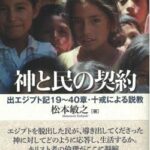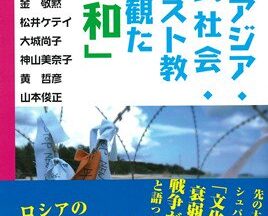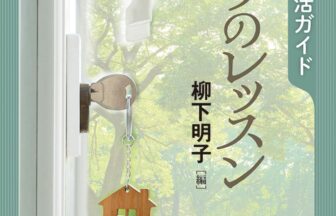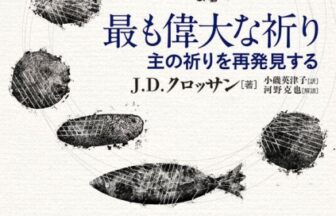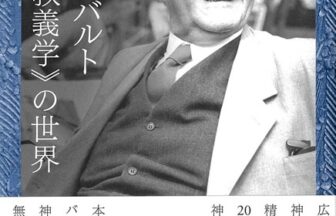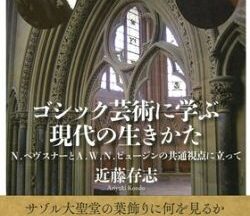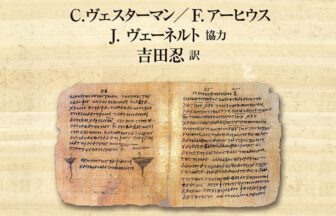分断世界における信仰リアル・ストーリー
〈評者〉宮﨑 誉
日本の多くの教派の牧師たちに、礼拝説教の備えとして愛読されているシリーズに創世記後半が加わりました。
礼拝での説教箇所として創世記をシリーズで用いることは珍しいことと思います。それは、礼拝で聴く説教が、主イエス・キリストの福音として聞かれる目的があり、つまり受肉された主イエスが登場する新約聖書を聖書テキストとする方が、どうしても自然になるからです (本書224頁)。しかし、それゆえにあえて旧約聖書からの講解にチャレンジすることはとても貴重で、意義深く感じます。そして、何といっても創世記は面白い! そこからアピールする説教を紡ぎ出そうと生みの苦しみをする牧師たちの思索は、魅力的で引き込まれる味わい深さに溢れています。
黙想では、創世記の後半の物語の主要な設定を「争い」の視点で位置付けています(6頁)。登場人物はアブラハム、イサク、ヤコブという信仰の民の族長物語ですが、旧約聖書学者のブルッゲマンの視点を借りるならば、「争い」をコンテキストとした「嘆き」に人間のリアリティが現れていると言えます。ヤコブとエサウ兄弟に騙し合いが起き、妻たちは競争心に駆られ、そして、ヤコブの息子たちは若いヨセフを妬み、奴隷として売り飛ばすという悲劇が起きます。神の民らしくない痛ましい家族像で、神礼拝の場で語られるのにふさわしくないようにも感じるのですが、しかし、むしろそのようなリアルな泥沼の分断の中で、それでもなお神の恵みと和解が備えられているということに、引き込まれていきます。争いの苦しみの中で、人はうめき祈り、天よりの御声に導かれていくのです。
このような信仰の姿をあらわす祈りの手引きが、二段階の祈りとして紹介されています (22~23頁)。①祈りとは、惨な世界から目を天に向けること、そして、②「キリストの目をもってこの世に目を注ぐこと」(カトリック司祭ミシェル・クオスト)。まさしく、これこそ族長たちが荒野で経験した信仰のレッスンだったと感じます。使徒パウロもまた族長の信仰をこう言い表しています。「望み得ないのに、なおも望みつつ信じた」(ローマ4・18、口語訳)。
この「争い」は現代の差し迫った課題です。共生を求めた理想が崩れ、こんなにも「紛争」が激化する時代を迎えています。また、「争い」は「分断」とも言い換えられるでしょう。国家内で分断しているのに、自国第一主義を掲げて世界中に分断を広げ続けている悲しい世界情勢を、私たちは痛みを感じつつ目撃しています。いえもっと身近に、信仰理解や人権意識という大切なテーマの理解の差異によって、教会に分断が生じてしまっています。創世記32章28節では、ヤコブは「あなたは何者か?」と問われます。そして、「ヤコブ(押しのける者/争う人)です」と答えたことは、ヤコブの罪の告白 (58頁) であり、心砕かれた者がキリストの恵みに生かされている自己を発見できるのです。
争いうめく私たちの罪深い自己存在が神に問われる姿を、創世記は描き出します。まさにそこに与えられる神の恵みのリアリティがあるのです。この説教黙想を通して読者は、自己を福音によって受け止め直すきっかけを得られるでしょう。はじめての方もぜひ手にとって、黙想に浸っていただきたいと願います。