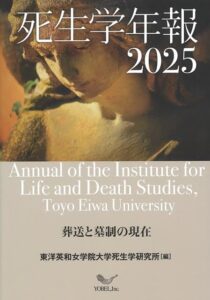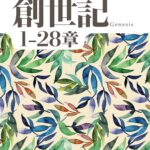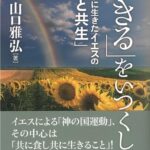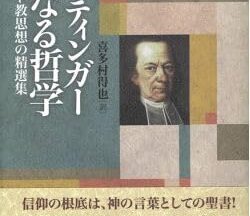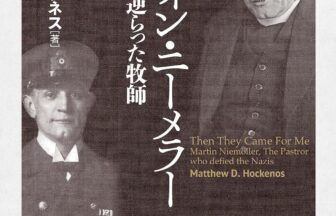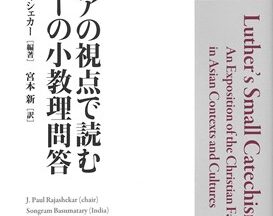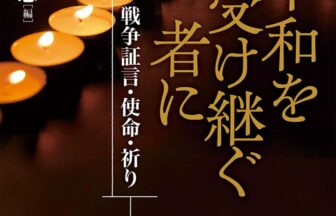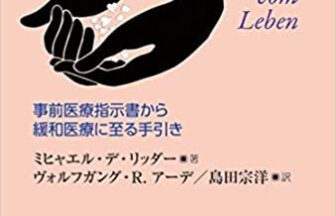「死生学」の最前線を展望しつつ、身近なところから光をあてる
〈評者〉高橋 原
「死生学」という名前がついた講座や学科を持つ大学には、東京大学、東北大学、上智大学などがあるが、その先駆けとなった東洋英和女学院大学の死生学研究所による『死生学年報』が、通巻第二十一号を迎えた。日本の死生学は、医療やケアの分野と宗教学隣接領域の研究者が合流して、現代社会の諸問題への対応を考えてきたが、そのもっとも新しい関心はどこに向かっているのだろうか。
ひとつの焦点は「看取り」である。一九七七年に病院死が在宅死を上回って以来、「穏やかな」とか「自分らしい」とか形容される望ましい死に方は、常に人々の関心の的であり続けている。本書の巻頭には、普通の人の死を題材とするドキュメンタリー作品を世に問うた二人、映画『エンディングノート』(二〇一一年)の砂田麻美監督と、『あなたのおみとり』(二〇二四年)の村上浩康監督による対話的寄稿が置かれ、〈看取りの文化を構想する〉という特集への導入となっている。
特集の中で、山田千香子は五島列島の調査に基づき、医療福祉の資源が乏しく、一見不便な離島で、「自宅死率」が高く、「顔の見える関係」の中で暮らす高齢者の生活満足度が高いことを示す。また、浮ヶ谷幸代は、臨床宗教師が常駐し、「自宅に限りなく近い形」で運営されるシェアハウス「アミターバ」(大垣市)を素材に、人生の幕引きのあり方について考察している。いずれも、先進的な事例の中に、孤独死が問題視され、七割が病院で死ぬという都市生活の中の死を考えなおすヒントを求める試みである。
本書が特集している死生学のもうひとつの焦点は、〈葬送と墓制の現在〉である。この二十年ほどのあいだに、「葬式はいらない」という主張が現れたり、「自然葬」や、「墓じまい」がメディアに取り上げられたりしてきた。東日本大震災はきちんとした弔いの重要性について再考する機会となり、「葬式仏教」を再評価する流れもあったが、一方で、「家族葬」という言葉がすっかり定着し、コロナ禍以降は葬儀の簡略化に拍車がかかっているとも言われる。
人が死ぬと僧侶を呼んで通夜・告別式でお経を聞き、火葬場では「これが喉仏です」などと説明され、遺骨を寺院や霊園にある自分の家の墓に収める、というのが、型通りの弔いのイメージであろうか。しかし、「○○家」の墓石の下の空洞に遺骨を収める「カロート式家墓」は実は関東大震災後に現れて昭和期に普及した新しいもので、しかもすでに過去のものとなりつつある(問芝志保論文)。火葬場での「収骨」は日本に独特な習慣だが、遺族の心の安定にとって極めて重要な意味を持つ「儀式」である(坂口幸弘・赤田ちづる論文)。そもそも「葬式仏教」が批判的に見られてきた背景には、一九六〇年代以降に民間企業が墓地開発に乗り出し、寺院の側がそれに乗ったという事情がある(辻井敦大論文)。これらは当たり前のこととして見過ごしている事実に光を当てる論考である。
他にも、宗教学者岸本英夫の死生観(宮嶋俊一)、臨死体験研究(大門由依)、ファッションデザイナーのアレキサンダー・マックイーン(岸根紗葵)が死生学の問題として取り上げられている。文献紹介もあり、死生学の最前線を展望しながら生と死の問題を身近なところから、ちょっとアカデミックに考える手がかりとなる一冊である。