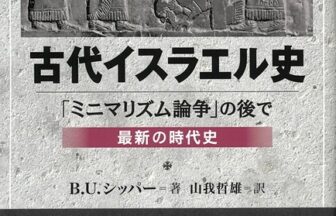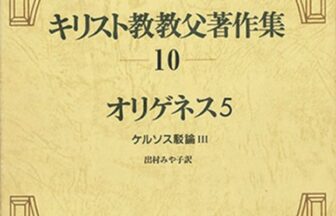「愛」の観点から『三位一体論』を読み解く良き道標
〈評者〉出村和彦
『キリスト教思想史の諸時代』別巻2として待望の「アウグスティヌス『三位一体論』を読む」が刊行された。本書の特色は、三位一体の教義をアウグスティヌスが「カリタス=聖い愛」の本性から一貫して解明していることを明確にしたことにある。
著者金子晴勇先生は、彼の三位一体の神についての根本的思想を教義論争の断片的な主張からではなく、紆余曲折(付録資料「アウレリウス宛書簡一七四」参照)を経て全一五巻に結実した『三位一体論』でアウグスティヌスが長い時間をかけて取り組んだ三位一体の神を「信仰しつつ理解を求める探求」の諸相として示す。それはまた、若き日の最初の学術的取り組みから七〇年を経てついに本書を完成した著者の心を貫く『三位一体論』への持続した関心から汲み取られた味わい深い成果である。
本書は、古代教会での論争点をコンパクトにまとめ(第一章)、全巻の構成を第一巻から第七巻(第二章)第八巻から第一五巻(第三章)に分けて、各巻で取り組まれている問題を見通しよく整理しているので、原典や翻訳を読解するのに良き道標となっている。
「アウグスティヌスの説く聖い愛カリタスは神への愛と自己への愛とを融合させた統合体となっている」ことを本書は強調する(本書一四〇頁)。確かに、『三位一体論』は、愛の経験的な現象から「愛する者」「愛されるもの」「愛」の三肢を取り出し、ここに三つでありながら一体である「三位一体」の痕跡を見出し、さらに、精神内部で三つが一致した「精神・自知・自愛」の三肢から知性的認識における「記憶・知性・意志」の三肢が発展的動的に立てられており、「存在・認識・愛の三一構造として一般化できる」(本書一五三頁)という三位一体なる神の像の内的探求は、われわれ人間がそれを生きそれによって生かされている神の愛の探求でもある。
本書は、古代教会の歩みに従いながらも受肉したキリストの前での自己認識が必要であることを説いた彼の受肉の神学(第四章)、「神の像」の理解(第五章)、著者の研究の出発点である『三位一体論』における信仰と理性(第六章)、知性的認識と照明説(第七章)、神への超越機能と三位一体神秘主義(第八章)、ルターとの相違への示唆も含むアウグスティヌスの現代的意義(第九章)の各論で、三位一体の教義理解が今日のわれわれにとって哲学的にもチャレンジングに迫ってくることを知らせる。
さらに本書は、神の本質である知恵に関与することが神への礼拝であるとアウグスティヌスが考えて、「記憶・知性・意志によって行われる礼拝は、一般に人間精神が神の像であるところの知恵の内実を制限している」(二二〇頁)と指摘するシュマウスの「三位一体的神秘主義」といった性格付けを見据えて、現世においてできる限り「三位一体」の「礼拝」として「一つの霊」となることへと読者を誘うのである。
本書刊行をもってシリーズ全7巻別巻2が完結し、著者の霊性理解の深みから一貫した視点で教父時代から宗教改革、近代・現代までを手に取りやすい新書の形で総合的に展望することが可能となった。この企画の完成を心より喜びたい。