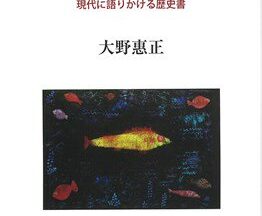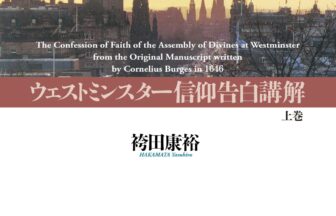バルト神学の原点がここに!
〈評者〉牧田吉和
本書は“小さな書物”である。しかし、訳者の一人加藤常昭が本書で繰り返し訴えるように“必読の書”である。評者も、神学に携わる者にとって、そして何よりも説教者にとって必ず読むべき書であると確信する。決して分かりやすい書ではない。しかし、根本的に問われ、深く考えさせられる“重い書”である。
本書にはバルトの二つの講演が収められている。一つは「キリスト教会の宣教の困窮と約束」(一九二二年六月 加藤訳)、今一つは「神学の課題としての神の言葉」(一九二二年一〇月 楠原訳)である。本書のタイトル『説教と神の言葉の神学』は本書の中心内容を明示する適切な書名である。二つの講演はすでに『バルト著作集1』で訳出されている。本書では“原文の趣を忠実に伝える”ことよりも“原文を解きほぐした訳”が意図されている(一〇頁)。本書の出版の意味もそこにある。
二つの講演は、「危機神学」・「弁証法神学」の端緒となった『ロマ書』第二版(一九二二年)後に、ゲッティンゲン大学改革派神学教授に就任して間もなくなされたものである。本書を読む時、「危機神学」・「弁証法神学」と呼ばれた意味が良く理解できる。
これらの講演によって、バルトの神学の原点はまさに「説教」の問題であったことがわかる。“どのように説教を作るのか”の問題ではない。“どうしたら説教することができるのか”という根源的問題である(二九頁)。説教者は「困窮」の中に立たされる。一方では“人間の生の未曾有の矛盾と問題性”、他方では新しい謎として立つ“未曽有の聖書のメッセージ”。両者の狭間で“語らねばならない”しかし“語ることができない”という説教における出口のない「困窮」の状況。この「困窮の中から、救出を待つ大いなる望みを抱いて叫ぶ叫び」(二三─二六頁、他に二八頁)こそ、神学の課題そのもの。神学体系の問題ではない。この出口のない状況と問いとを表現することこそ神学の課題そのものである(二五頁)。この意味において、神学は、われわれが立つことができない「数学的点」、「視点」、一種の「欄外注」とも表現される(一六─一七頁)。このような「困窮」を理解するのであれば「危機神学」と呼ばれる理由も判明する。第二講演は、第一講演をより神学的に整理されて語られている。「弁証法神学」の意味も明確に理解できるであろう。
問題は「危機神学」や「弁証法神学」への知的興味の問題ではない。バルト自身もその立場にとどまったわけではない。キリストの恵みの圧倒的勝利を語るようになり、「欄外注の神学」から進んで「教会教義学」への道に至る。問題は“何が原点だったのか”という点である。それは説教者が神の言葉を語るとはいかなることかを根源的に問うたことである。これはどのように説教を語るか以上に核心的問題である。本書によって読者が迫られるのはまさにこの問いである。バルトに反対する人も、この問いから逃れてはいない。そしてこの問いからこそ神学も始まるのである。本書が加藤常昭の最後の仕事となったことは象徴的である。本書こそ加藤の原点であり続けたのだと思う。それゆえ、日本の教会に残した加藤の遺言としての意味をも持つであろう。