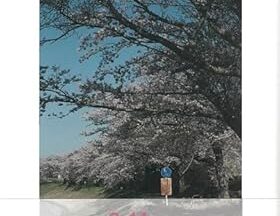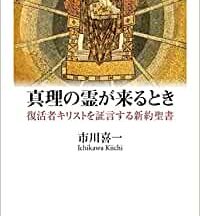神学の自己反省から生じた人文学的学問の可能性を問う
〈評者〉片柳榮一
本書は著者が長年追究してきた「キリスト教学」に関する理念と方法についてまとめたものである。それは信仰告白的な「コミットメントの共同体に根差した研究共同体」の営みとしての神学とは区別された「どこまでも理性的な学問の規範に従う」(四五頁)ものであるという。そしてそのような方向性は、神学自体、近代の苦渋にみちた自己反省のなかで、追究しつつあるものであり、このような流れは、一九世紀後半から二〇世紀初頭のドイツ神学界にすでに登場していたという。最近でも例えばトレルチ研究の第一人者のF・W・グラーフが、トレルチに言及しつつ神学を「キリスト教の歴史的・解釈学的な文化科学」(八〇頁)と位置づけていることは、現在神学そのものの流れの方向が「キリスト教学」に近づいていると著者は考える。そしてこのことは、キリスト教的生そのものの将来についても、深い示唆を与えているように思われる。
このような神学そのもののうちから生じている自己反省を決定的に推し進めたのは、著者によればシュライアマハーであり、その課題を最も深く受け止めたのはトレルチであるという。著者によればシュライアマハーにとっては、神学の目指すところは「生き生きとしたキリスト教信仰と、あらゆる面に解放され独立独歩営まれる学問的研究との間に、永遠の契約(ein ewiger Vertrag)を締結」(三七頁)しようとすることであったという。トレルチによれば、「不断に新しい創造的総合は、絶対に対して各瞬間に可能な形姿を与えるが、しかも真の、究極的な、普遍妥当的な価値への単なる接近にすぎないととの感情をいだき続ける」(一七一頁)ものであるという。
確かにこのような試みはシュライアマハー、トレルチが考えた以上の困難を孕んでいる。周知のように、弁証法神学の旗手カール・バルトは、「信仰にとって破壊的な作用を及ぼす近代的な歴史的=批判的方法を、神学から一掃しようと」(四〇頁)した。しかし著者は言う。「バルト神学やブルトマン神学が活況を呈した後に、再びシュライアマハーやトレルチの神学が注目を浴びているのは、いわゆる弁証法神学なるものが本質的な問題解決を与えなかったことの証左ではないでしょうか」(四一頁)。
詳細にキリスト教学の可能性について省察を加えたこの貴重な書に励まされながら、一つの問いが生まれる。確かに著者が言うようにキリスト教学は、信仰告白的な「コミットメントの共同体に根差した研究共同体」の営みではなく、「どこまでも理性的な学問の規範に従う」(四五頁)ものである。しかし人文学が持つ独特の「事柄への関与」(生への深いコミットメント)ともいうべきものがあるのではないかという問いである。殊に日本の人文学研究においては、この点が曖昧にされ、客観性という言葉を、傍観者への逃げ道にして、「関与によってのみ切り開かれる知」への熟慮が等閑にされてきたのではないか。「追体験的に再構成する」(二四八頁)ことに含まれる「自己関与」がである。「キリスト教学」における「知と信」をめぐる苦闘は、この点で、人文学への或る積極的な貢献の可能性があるように思われる。著者の人文学への深い洞察を思いながら、共に考えを深めて行ければ、と思う。