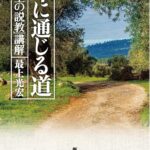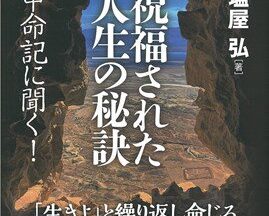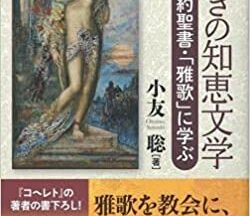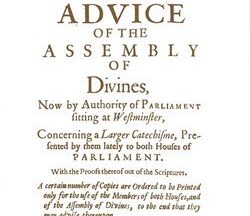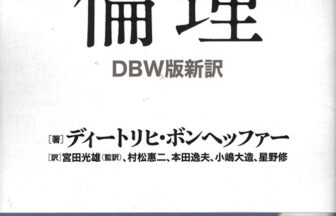バルトが切り開いた前人未到の道を案内する
〈評者〉福嶋 揚
『教会教義学』はキリスト教史上最大の単著である。その難解なテキストを一行一行辿る道のりは、長くて厳しい。読み通すだけでも数年はかかる。それだけに、細部を見るだけでなく全体像を展望できるようなオリエンテーションがどうしても必要となる。細部の地形だけでなく、グーグル・アースのように上空からその地の大まかな特徴を見せてくれる、学びの手助けが不可欠である。
寺園喜基氏による『カール・バルト《教会教義学》の世界』は、この『教会教義学』全体を鳥瞰して要約する、日本語ではおそらく初めての、適切な分量の概説書である。本書は、遺稿集も含めれば一万頁を超える『教会教義学』の全体を、何十分の一かの分量に圧縮して再現している。バルトのドイツ語テキスト約三十ページが、本書の約一ページの日本語に凝縮されているのである。『教会教義学』を構成する全四巻─プロレゴメナ、神論、創造論、和解論─の各巻の各部分が、どこにも偏ることなく、きめ細かく再現されている。しかもバルトの原文に特有な難解さをひきずることなく、簡潔かつ平易に書かれている。
それに加えて本書では、『教会教義学』に至るまでのバルト神学の形成過程も解説されている。政治的社会的な背景にも折に触れて言及されている。索引や聖書箇所も充実している。神学教育の参考書や教科書にも相応しい一書である。
ちなみに書評者自身は、たまたま今、カトリック神学者ハンス・キュンクの翻訳に取り組んでいて、そのさなかに本書をひもとく機会を与えられた。教派の壁を超えて青年キュンクを深く魅了し、カトリック教会の勇敢な変革へと向かわせた『教会教義学』の力、すなわちバルトの説く福音の力を、寺園氏の本書を通して、改めて認識させられた。
その一方で、本書を読みながら次のようなことも考えた。『教会教義学』は、西欧キリスト教世界の内側に根差して築き上げられた、最後にして最大の神学的な巨大建造物だったのではないかと。一九六〇年代、キュンクが全世界を旅行することによってキリスト教世界をはるかに超えて視野を拡大していった頃、バルトはこの巨塔を完成することなく世を去った。改めて思う、この『教会教義学』が探求して残したものは何だったのだろうか。
それを敢えてつきつめて言えば、人間が何を企てようと、神と呼ばれる力が人間に向って到来するということではないだろうか。バルトによれば、神は神以外の何ものでもない。神より大いなるものを考えることはできない。神は自らに相応しく自らを貫徹する。だとすれば、人間が神について語ることなど不可能だろうか。語りえないものについては沈黙すべきだろうか。
バルトはそのようなアポリアを突破して、神のほうから神自身を語らしめるという道、つまり「神の言葉の神学」を見出した。それも、ほかならぬイエス・キリストという一点を突破口としての「神語り(theo-logia)」、すなわち語の本来の意味でのキリスト教神学(theology)を企てたのである。寺園氏の最新著を読むことによって、そのようなバルトが切り開いた前人未踏の道に刮目させられる。