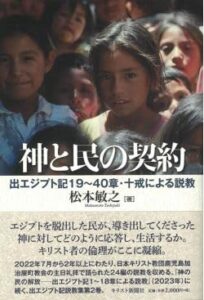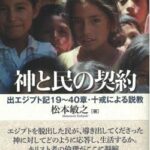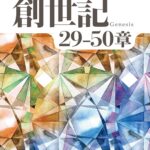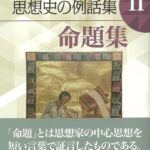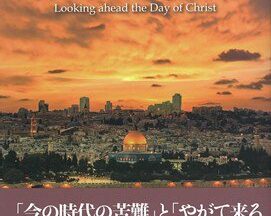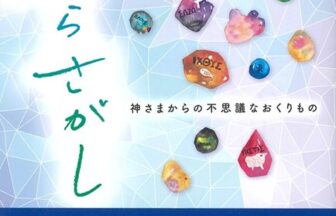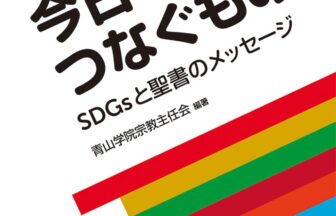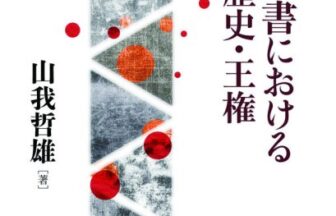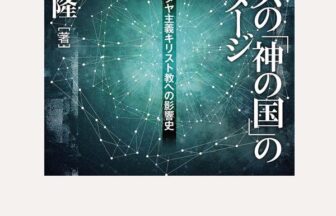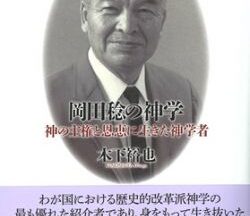現代に呼びかける神の言葉の響き
〈評者〉荒井 仁
鹿児島加治屋町教会の牧師として2022年から24年の間に説教をした原稿をもとに本書はまとめられている。既刊の説教集『神の民の解放』で出エジプト記1章から18章を扱ったが、本書はその続きとして19章から40章までと申命記32章を取り上げる。24編中、十戒についての説教が11編収められている。律法が記された箇所も概略を分かりやすく紹介している。
説教集全体を読んだ第一印象として、出エジプト記の物語や律法を取り扱いながら、現代の問題と結びつけているので、神の言葉が現代に呼びかける響きを聞く思いがする。例えば「8 生命」は第六戒の「殺してはならない」を扱っているが、殺戮、憎しみなどと結びつけるだけではなく社会構造的な罪にまで踏み込んでいる。「例えばアメリカや日本が豊かな生活を享受するために石油を確保することと中東の戦争は無関係ではありません。利権争いに巻き込まれ、そのような戦争の犠牲になっている多くの人は、現地に住む、貧しい人や弱い立場の人なのです」。日本に住む私たちが日常生活を送る中に潜む罪を思い起こさせてくれる。同じ説教で「妊娠中絶」にも触れるが、その際、胎内に宿った時から一つの命であるので、自由に殺しても良いというのは人間の傲慢であると言い切る一方で、「妊娠中絶を考えざるをえないような状況、母親を追い込んでいく社会構造の問題」を考える社会の責任を問うている。
二つ目に印象に残ったこととして、歴史との関係がある。説教の中でしばしば「ハイデルベルク信仰問答」が引用されている。筆者も以前には目を通したことがあるが、松本先生の取り上げ方は聖句の意味が理解しやすいように用いている。「10所有」で第八戒の「盗んではならない」の意味を広く解釈するために、信仰問答に記された「神の賜物の不必要な浪費」を取り上げる。現代の日本に生きる私たちには耳の痛い解釈である。またナチス・ドイツの問題とディートリッヒ・ボンヘッファーにしばしば言及する。「偽証してはならない」についての説教である「11真実」で、ボンヘッファーが、先生と一人の児童の話をしたことを紹介する。「君のお父さんは、酔っぱらってうちに帰って来ることが多いというのは本当かね」と先生に問われて、この児童は「ぼくのお父さんはそんな人間ではありません」と答えた。この嘘は事実に即した言葉ではないが、事実に即した言葉よりも真実だとボンヘッファーが述べている。これを受けてボンヘッファーの置かれた状況を説明しながら、「私たちはそこで神様に対して真実であること、隣人に対して真実であることを貫いて、言葉を選ばなければならないのです」と、守るべき者を守る姿勢の大切さを示す。
松本先生はいつも笑顔で人と接しておられ、腹話術で楽しませユーモアのセンスもある。その一端が「21再生」にも垣間見られる。モーセが神と会って神の栄光を受け顔が輝いていたときの描写である。「光をいっぱい受けて、その光が去った後も、まだ光が残っていたのです。ちょっと夜光塗料のような感じもします」。「夜光塗料」の4文字に思わず笑いがこぼれた。入門の書としてもぜひ、勧めたい一冊である。