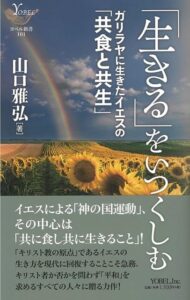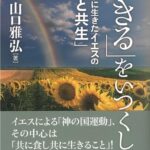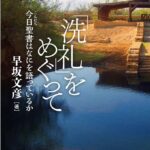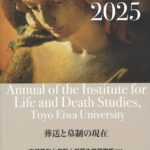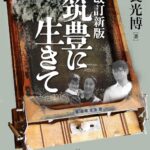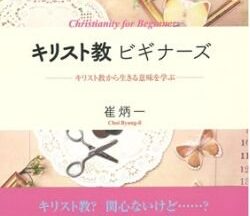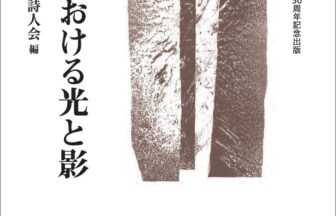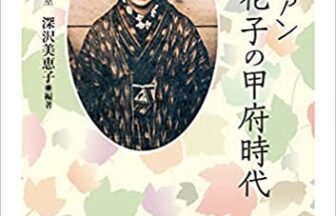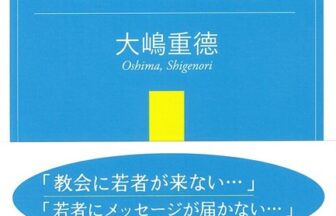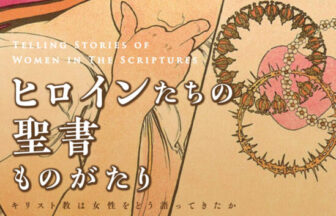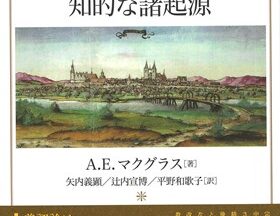イエスと一緒にご飯を食べよう
〈評者〉富田正樹
地上は暴力に満ちている。
その暴力により、多くの人が戦闘や殺戮で命を奪われ、困窮の中で飢え渇き、尊厳を奪われ、恐怖と不安に押し込められている。
この暴力は、イエスが生きていた時代、社会にも見られるものであった。しかしイエスは、その暴力に抗って生き、「共食」によって人が共に生きてゆけることを示した。
本書は、イエスがどのように生まれ育った家を飛び出し、彼の同伴者・協働者たちと、どこを旅し、何を教え、伝え、どんな人と出会ってどのように関わり、誰と何を食べたのか。それを、聖書学、歴史学、考古学、社会学、比較文化人類学などの知見を援用しながら、「『人間学』の立場から『推測』に基づき」(12頁)探求している。
ここで描かれるのは、多くの神学書や宗教教育が示してきた護教的なイエスではない。むしろ私たちがこの世の悪の「黙認(黙殺)の加害者」(3頁)にならないために、自らを厳しく問うことを迫るイエスである。
しかし、そんなイエスの言葉と活動の根底にあるのは、「共食と共生」である。つまり「共に楽しくご飯を食べること」(63頁)に、イエスの原点があるのだ。そして、その生き方は必ずしもイエス・オリジナルではなく、ガリラヤ地方の民衆の逞しい生き方にそのルーツがあった。
イエスはガリラヤの貧しい民衆と共に、「食べ、飲み、笑い、歌い、踊った」(103頁)。それがイエスの生き方と思想であり、社会的弱者に生きる力を与えた。人びとはそんなイエスの生き方を「胃袋で知った」のだ(197頁)。
そしてイエスは、社会的弱者や罪人を「非人間化」する「社会的・宗教的権威・権力者」たちを激しく糾弾した結果、「晒し柱(さらしばしら)」につけられて殺害される。
しかし、そんな彼の生き方に共感・共鳴した、女性たちを初めとする最初期のキリスト者たちは、彼の「共食と共生」の生き方に倣って生きるようになった(182頁)。なぜならイエスは、決して孤立して闘う人ではなく、「共食」によって「連帯」する人だったからである(211頁)。そして、その「共食」による「共感・共苦」の生き方は、今風に言うならば、まさに「ヒューマニズム」であり「ホスピタリティ」である(228、230頁)。
そして、今もイエスは各自の心に内在し「生きている」。「今」「イエスの協働者」となって生きる。それが「復活」なのである(258、261頁)。
本書は、イエスに倣う「共食と共生」の社会を体現できずにいる、現代のキリスト者に対する「警告」でもある。
本書のタイトルは「生きること」(名詞)をいつくしむ、ではなく「生きる」(動詞)をいつくしむ、となっている。「生きること」と客観的に眺め、過去の人物としてイエスを研究するのではなく、イエスと共に今を「生きる」。
「神の国の宴」(134頁他)を具体化し、共に食べ、飲み、笑い、歌い、踊る。そして地上の暴力に抗って平和を生み出し、今や効力を失った贖罪論や形骸化した聖餐論などぶっ飛ばして、すべての人と「受容」し合い、「今」イエスと共に「生きる」をいつくしみ合いながら、喜びの人生を生きてゆこう。
そんな生き方へと、本書は誘っている。