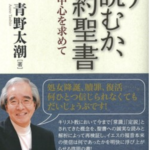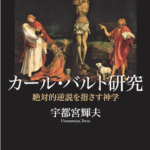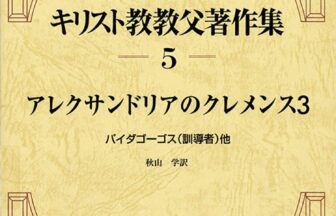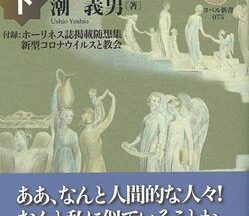御言葉の臨場感を楽しんで!
〈評者〉関 真士

大頭眞一先生より、思いがけず書評を頼まれた。身に余る光栄とは、この事である。ワクワクしながら本書のページをめくらせていただいた。
本書を読んで感じたことを一言で表現すると、それは「臨場感」である。まるでノンフィクションの映像を見ているような感覚になった。この臨場感をもたらしているものは何だろうか?
まず、大頭先生のメッセージに一貫しているのは、人間を神への応答者として理解しているところにある。
「私たちには神さまがおっしゃることを受け入れることもできるし、拒否することもできます。神さまに招かれるとき、それを拒否することもできます。そのように、人は神さまにとって応答関係の存在なのです。神さまにとって、私たちは『命令を聞かなかったらダメ』と済ますことのできない存在、それが私たちなのです。」(三一頁)
神のことばを研究し、正しい解釈を求めることは尊い作業だ。しかし、大頭先生は、そこに留まらずに、その神のことばに対する応答者としての人間の人格を大切に、尊く扱っておられる。そのことによって、紙に書かれた脚本が俳優によって実際に演じられるかのように、文字である御言葉が動き始め、語り始める。それが臨場感となり、まさに神のドラマに自分も参加しているような感覚になる。
ただしその応答は、神のことばに対する応答という「枠」を決して超えない。どんな応答であっても、あくまでも神に対してなのだ。だからその応答は神との交わりとなり、そこに人格的関係がもたらされる。
大頭先生は、真理のみことばの前に立たされた人間の応答は様々であること、そしてその応答を神が求めておられることを明らかにされる。「聖書は、ただの書かれた言葉ではなく、一言一言が人格的な交わりを求める、神さまの愛のことばです。」(七六頁)
さらにこの臨場感は、大頭先生自身がそこにいることでもたらされていると思われる。
大頭先生は、確かにそこにおられたようだ。モーセが燃える柴を見たとき、エクソダスのために立ち上がったとき、シナイ山から下りて来たとき、幕屋を建てたとき、その時、そこにいたようだ。荒野の岩場のかげで焚き火をしながら神のことばに耳を傾けている先生の姿が思い浮かぶようだ。
その時の大頭先生は、もしかしたら人間としての苦悩や、嘆き、弱さを抱えたいのかもしれない。しかし、その時、そこで聴いた神のみことばを私たちに語ってくれるからこそ、メッセージの受け手に対して、神が今ここで語っておられるという臨場感をもたらすのだろう。そして、大頭先生のメッセージの真骨頂は、常に主の十字架に焦点を当て、私たちを主の十字架のもとに導くことだ。
ある死刑囚の「誰が私の罪を責めうるのか」ということば対して「責めうるとするとすれば、それは神さましかいない。でもその神さまが、御子イエス・キリストの十字架によって、もう私を罪に定めないと言ってくださった、だから私は神を喜ぶ。喜びながら光の中を生きる。」(一三八頁)と答えている。主の十字架が臨場感をもって迫り、この喜びと光の中に招かれていることに感謝が溢れてくる。メッセージを通して、主の熱情とも言える愛が迫ってくる。
引用したい箇所は山ほどあるが、それは叶わない。どうぞ本書を開いて御言葉の臨場感を楽しんでいただきたい。

関 真士
せき・しんじ= ホノルル・キリスト教会牧師