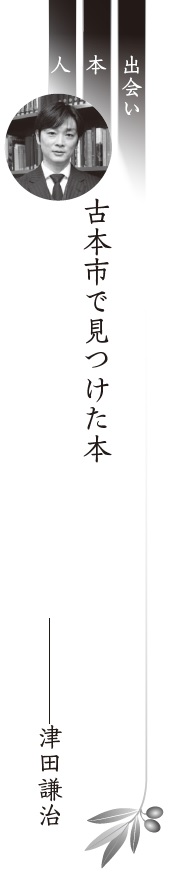
勤務校に隣接する寺院の境内では、秋になると定期的に古本市が開催される。感染症の予防に細心の注意を払いつつ開かれた会場に足を運ぶと、所狭しと様々な本が並んでいる。
キリスト教関係の書籍は、年々少なくなっている印象を受けるものの、何軒か廻ると、まとまって扱っているお店があった。時間をかけて見てみると、学生時代に図書館で借りて読んだ、近代ドイツのキリスト教思想について書かれた本がある。私自身は主に古代の教父思想の文献を読むことが多いが、授業などの準備で読み直したいと思い、手に取った。表紙を開くと、著者が自分の恩師に献呈した様子が書かれていた。そこに書かれているお名前は私の研究室の遠い先輩にあたり、恐らく亡くなられたのち、ご家族が売却されたものと思うが、古本に丁寧に引かれた線や書き込みを拝見しながら、この書は私にとって、とても大事な学びと導きの一冊となった。
自分の恩師に書いたものを読んでもらうというのは、緊張するとともに、何かしらの達成感を伴うものであるように思う。学生時代に、何度も自分の書いた拙い論文を読んでもらい、足りない部分を繰り返し指摘されて落胆し続けてきたはずだが、本として書いたものは、その時点までの自分のある種の集大成として、何か勝負に出るようなところがある。執筆中、時折、恩師の顔が浮かぶ。こんな軽率なことを書いたら怒られるだろうとか、もう少し分析を丁寧に行わないと出版後になったらもう訂正できない、など色々なことを考える。書き終わった後からやって来る評価や感想は、何か恐ろしい審判のようでもある。
古本市で見つけた一冊の書物を開きながら、著者はどのような心持ちで執筆し、本を献呈したのかを考えた。しかし、何よりも、最も手に取って欲しかった読者に、これ程までに丁寧に本を読んで頂いたことは、幸せなことだろうと感じた。
(つだ・けんじ=京都大学大学院・准教授)


















