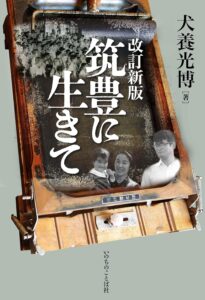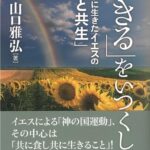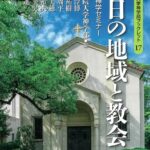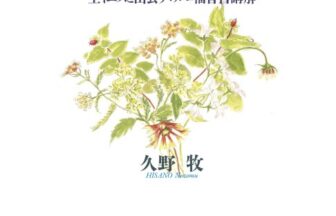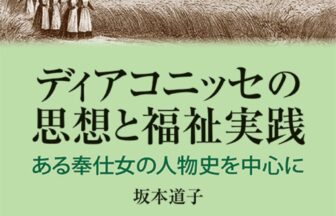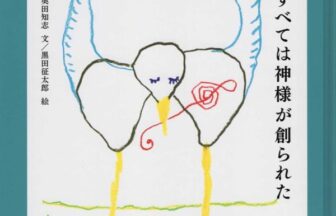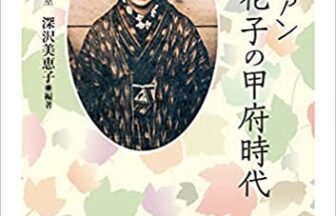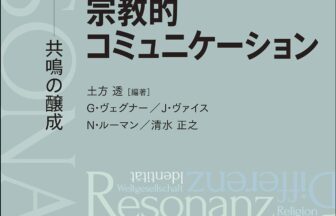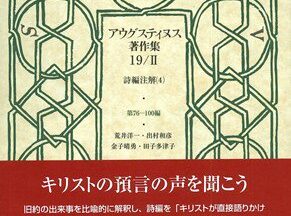荒野を歩きつづけたひとりの牧者・その苦悶と祈り
〈評者〉崔 善愛
本書の著者・犬養光博牧師は一九三九年大阪市に生まれた。まもなく八十六歳になられる。同志社大学神学部時代、筑豊(福岡県)のこどもたちに出会い、その輝く笑顔にひきこまれ、その地に「就職」する決意をされた。本書には、二十歳代だった犬養牧師が、いかにして苦しむ人の隣人たりえるか、模索し苦悶する信仰の軌跡が記される。
一九六〇年代、その地はまさに荒野だった。今では三池炭鉱などが「明治日本の産業革命遺産」に登録され、炭鉱は日本の繁栄を導いた栄光の歴史と語られる。しかしその「栄光」は誰のものだっただろうか。その栄光のもとでどれほどの犠牲が強いられただろうか。本書を読み進めてゆくと、まるで戦場の跡地に立たされているような思いすら抱くのだ。
かつて二八〇もの炭鉱がひしめきあった筑豊。著者が「就職」した地には「福吉炭坑」があった。福吉は、小山が真ん中にあり、その両側の谷間に開かれた炭坑で、そこにある炭住に最初の八年間住んでおられる。閉山によって失職した人たちは生活保護を受給せざるをえなかった。犬養牧師は本書の基になった『月刊福吉』をガリ版で刷り、それを手に町のすべての家、九二戸(約四六〇人)の門戸を叩き、一軒一軒まわった。伝道所に人を招くのではなく、自ら他者のもとに赴き、「出会わせていただく」。これこそが犬養牧師の牧会だった。
私の家族も同時期のまさに一九六〇年、父・崔昌華牧師が北九州市小倉北区にある在日大韓キリスト教小倉教会に赴任した。教会には筑豊の炭鉱に強制連行あるいは徴用された朝鮮人の家族らが集まっていた。
「日本人と同じ部屋に寝るのはこわい」と、牧師の研修旅行で同室になった犬養牧師に父は言った。父だけでなく教会員の在日一世は日本統治時代の辛い体験を負っていたため、日本に住みながら日本人を信じることができないというトラウマを抱えていた。がしかし教会員も父も、犬養牧師を誰より信頼しつつ共に歩むようになっていった。その姿は私にとって何ものにもかえがたい宝であり、希望だった。
にもかかわらず私自身は、犬養牧師が何に悩み、何を喜びとしていたのか、知ろうとしなかった。そしてはじめて「月刊福吉」(本書)で触れることができた。
閉山後の「ヤマ」に残されたのは、縦横無尽に地下奥深くまで石炭を掘り出しつくされたあとの穴だ。それにより地面が崩落し、水道もままならず、その「鉱害」を「復旧」することが当時の大きな課題だった。その「復旧」の一端をも担いつつ、犬養牧師は牧会だけでは生活できず、トラック運転手、土建作業員などの肉体労働を続けながら、並行して地元のこどもたちのために「そろばん教室」「学習塾」、そして妻の素子さんは「保育園」を開き、奉仕した。
現在は長崎県松浦市に転居しておられるが、「犬養の思いは筑豊にある」と素子さんがこぼされる。
ただひたすらに「他人の苦しみを自分の苦しみにできるか」とご自身に問いつづけ、戸惑いや嘆きを吐露し、祈る。その犬養牧師の「告白」に接するこの一冊は、私に問いかける。「同じ北九州市に住みながら、あなたはどこにいたのか」と。
もっとも苦しいひとのところに自ら赴き、友となり隣人となる。その厳しさと喜び。
多くの人に読んでいただきたい。